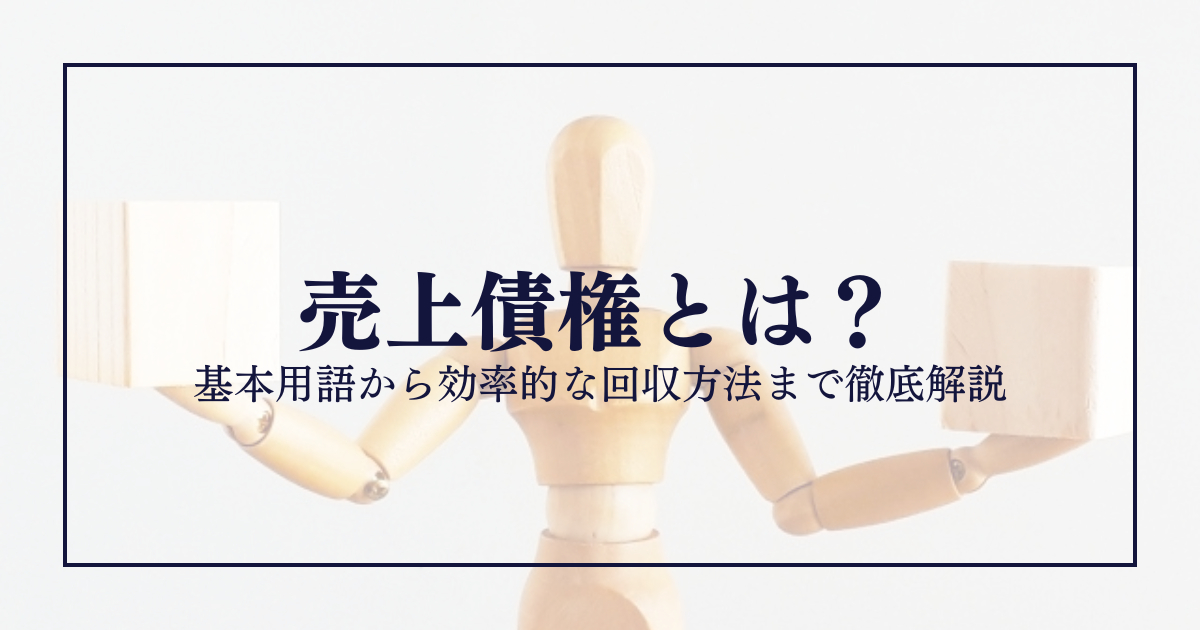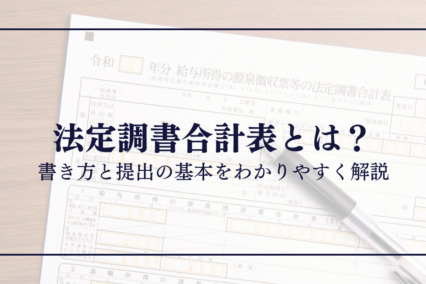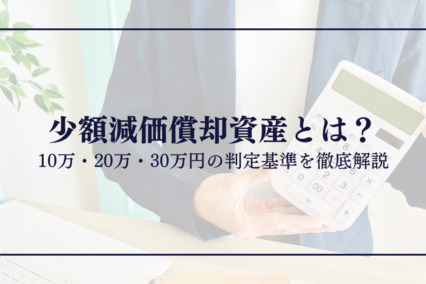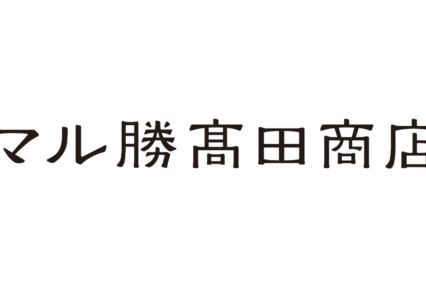企業間の取引では、営業活動から生じる売上債権が頻繁に発生します。この売上債権は会社の資金繰りに深く関わるため、適切に管理し、できるだけ早く回収することが非常に重要です。
この記事では、売上債権の種類やその管理方法、さらには回収方法について解説します。加えて、経営状態を把握するための重要な指標である売上債権回転期間などについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
売上債権の種類
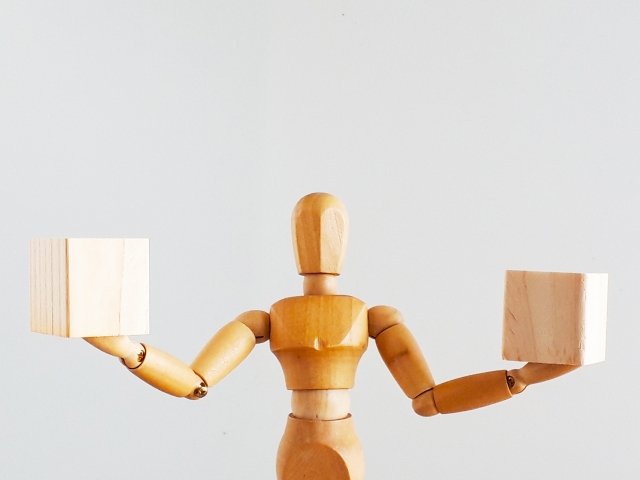
売上債権には売掛金と受取手形があります。
売上債権の勘定科目1:売掛金
売掛金とは、企業が商品やサービスを提供したものの、まだ代金を受け取っていない未回収の金額を指す勘定科目です。これは会計上、貸借対照表の「流動資産」として計上されます。
商品やサービスを売り上げた時点で売上として記録されますが、実際の入金は後日になるため、回収が滞ると会社の資金繰りに影響が出かねません。そのため、取引先ごとの入金状況を正確に把握して回収不能リスクを抑制することは、経理担当者にとって非常に重要な業務です。
売上債権の勘定科目2:受取手形
受取手形も売掛金と同様に、商品やサービスの販売代金として将来的に金銭を受け取る権利を指す勘定科目です。売掛金との違いは、相手が発行した証書(約束手形など)を受け取る点です。具体的には、取引相手から受け取る約束手形や為替手形を「受取手形」と呼びます。
受取手形には支払期日が設定されており、その期日に金融機関で手形に記載された金額を受け取ることができます。また、期日よりも前に手数料を支払って現金化することも可能です(これを手形割引と言います)。
売上債権を適切に管理する方法

与信管理と与信限度額の設定
与信管理とは、取引先の信用度や支払い能力を詳しく調べて、取引できる金額、つまり与信限度額を設定することで、未回収になるリスクを極力低くする活動です。適切に与信管理を行えば、掛取引の安全性を高めることができます。
与信限度額は、安全性を確保しつつ、必要な取引ができる範囲で上限を設定しましょう。特に、営業部門と管理部門の間で意見の相違が生じやすいので、無駄な手間を避けるためにも、取引先の格付けに関する社内ルールは全社員に周知しておくことをお勧めします。
取引書類の発行・送付
債権を正確に管理し、確実に回収するためには、取引内容を整理して書類に記録しておくことが不可欠です。与信限度額や取引条件が決定したら、まずは契約書を作成し、取引先に送付しましょう。
また、取引中に必要となる受発注書や請求書などの書類については速やかに発行・送付し、特に請求書は支払い期限の2〜3週間前までに送付するように心がけましょう。
債権管理ルールを策定・周知する
債権管理の方法を決めたら、その内容を反映した社内規程を作成しましょう。通常、この規程は債権管理に精通した法務部などが中心となって作成を進め、最終的に取締役会の承認を得て制定されます。
規程が完成したら、従業員への周知を徹底することが重要です。債権を適切に管理するためには、その重要性を全従業員が理解している必要があります。債権管理に関する教育セミナーや研修を実施するなど、社内規程が組織全体に浸透するような取り組みを行いましょう。
売上債権回転期間をチェックする
売上債権回転期間は、商品やサービスの売上から代金が回収されるまでの期間を示す指標で、商品やサービスを提供する企業側に発生します。
一般的に、売上債権回転期間が短いほど、売掛金が現金化されるスピードが速いことを意味します。もし仕入債務回転期間が売上債権回転期間を下回るような状況では、支払いが必要な時に資金調達が難しくなり、資金繰りが悪化している状態を示します。
売上債権回転期間(年)は、以下の計算式で求められます。
売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ 売上高
日数を単位として計算する場合は、次のようになります。
売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ (売上高 ÷ 365日)
また、月を単位として計算する場合は、次の式を使います。
売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ (売上高 ÷ 12ヶ月)
売上債権が増加する主な原因とは

売上債権が増加する理由の一つとして、現金決済の割合が減少することが挙げられます。例えば、これまで現金のみで商品を販売していた事業者が、掛け取引を始めたり、キャッシュレス決済を導入したりすると、必然的に売上債権の割合が増えるでしょう。
また、債権の回収遅れも売上債権が増える大きな要因です。基本的に売上債権を減らすには代金を回収する必要があります。そのため、代金が未回収のまま商品の販売などを続けると、売上債権は一方的に増え続けてしまいます。
未回収の売上債権回収のための流れ

未回収の売上債権を回収するためには、以下のような手順を踏むことになります。
1. 取引先へ連絡
売掛金が入金予定日までに入金されなかったり、入金額が違っていたりした場合は、まず回収ルールに従い取引先の担当者へ確認します。
2. 督促状や内容証明の送付
担当者が催促しても入金がないケースでは、督促状などを送付し、支払いを促す必要があります。
3. 訴訟を起こす
督促状や内容証明郵便を送付してもなお入金されない場合は、弁護士に相談し、簡易裁判所に調停手続きを申し立てます。
4. 強制執行
売上債権を回収するための法的手段にはいくつか種類があります。
一つ目の「支払督促」は、正式な裁判手続きを経ずに、裁判所から債務者に対し金銭などの支払いを命じる督促状を送付してもらえる制度です。
二つ目は「民事調停」。これは、裁判官と調停委員が当事者の間に入り、双方の主張を調整して和解を目指す非公開の手続きです。
最後の「強制執行」は、判決などに基づいて、裁判所の執行官が行う強制的な手続きを指します。
まとめ

ここまで売上債権について説明してきました。
売上債権の管理・回収についてご不明点がある場合などにおいては会計アウトソーシングのご利用がおすすめです。
請求書の作成から入金確認、そして時には督促まで、売掛金管理は多くの企業にとって時間と手間がかかる業務です。もし、これらの業務でつまずくことがあるなら、会計アウトソーシングがその解決策となるかもしれません。
会計アウトソーシングが売掛金管理の悩みを解決する3つの理由は以下の通りです。
- プロの専門知識に裏打ちされた安心感:複雑な売掛金管理を、経験豊富な専門家が代行します。専門的な知識が必要なケースでも、専門家によるサポートがあるため安心して任せられます。
- 業務効率の大幅な向上とコスト削減:管理業務から解放されることで、貴社はコア業務に集中できます。これまで売掛金管理に割かれていた時間やリソースを、製品開発やマーケティング、顧客サービスなど、貴社の成長に直結する活動に投入できます。結果として、組織全体の効率の向上や人件費や管理コストの削減にも繋がります。
- リスクの軽減と正確な経営判断:専門家による管理は、人的ミスを減らします。正確な売掛金状況を把握できるため、キャッシュフローの改善や、より的確な経営判断が可能になります。不正確なデータに基づく意思決定のリスクを回避し、安定した企業運営に貢献します。
会計アウトソーシングを導入することで、貴社は売掛金管理の負担から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。
売掛金管理の負担を減らし、ビジネスを加速させませんか?ご興味があれば、ぜひ一度ご相談ください。貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
経理BPOならBPIOにお任せください

経理・労務・総務等のバックオフィス業務の代行だけでなく、業務設計やDX支援など幅広く業務を支援します。
業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
RANKING
お役立ち情報
CASE