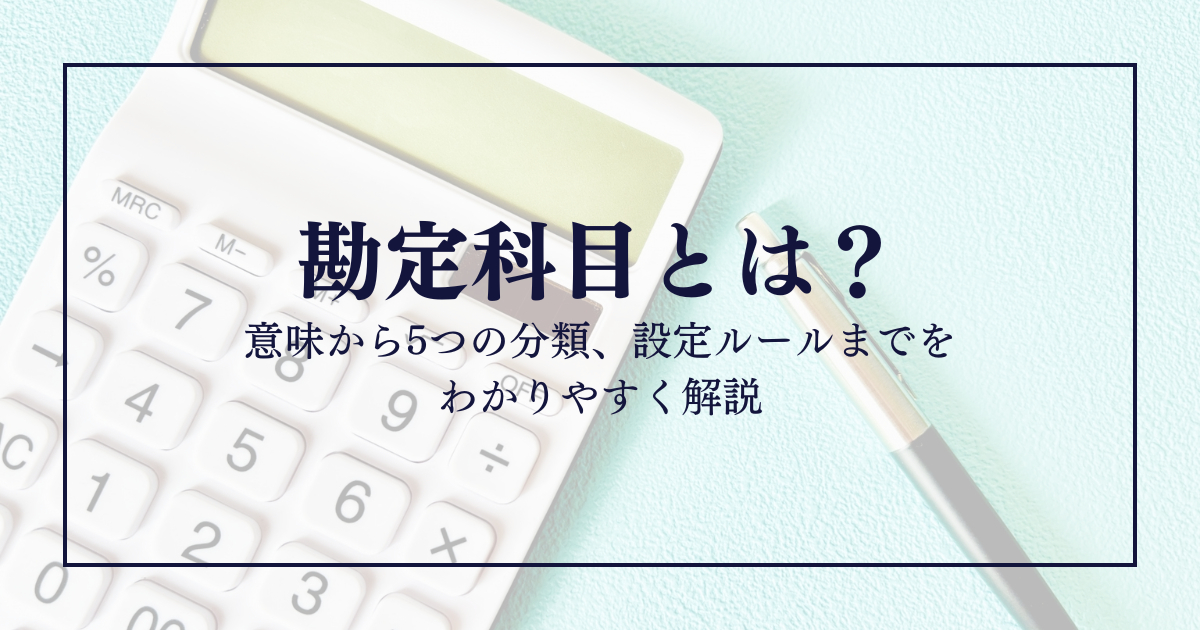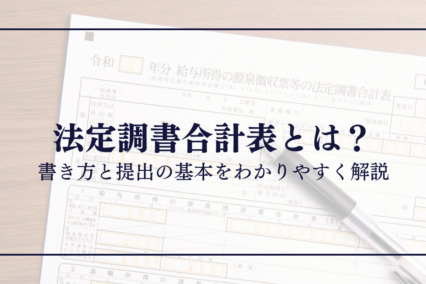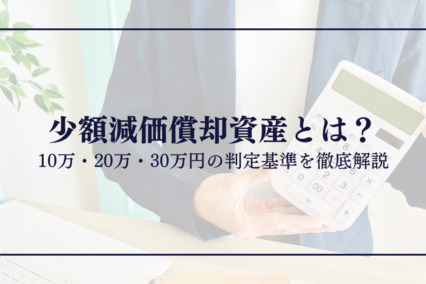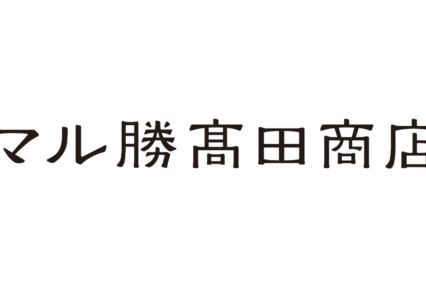企業や個人事業主にとって、お金の流れを正確に把握することは経営の根幹をなします。そのために不可欠なのが「勘定科目」です。勘定科目は単なる帳簿上の分類ではなく、事業の現状を理解し、未来の戦略を立てるための強力なツールとなります。
そこでこの記事では、勘定科目の本質からその分類、設定ルール、そして実務での活用方法まで、経理初心者の方にも分かりやすく解説します。
勘定科目とは?
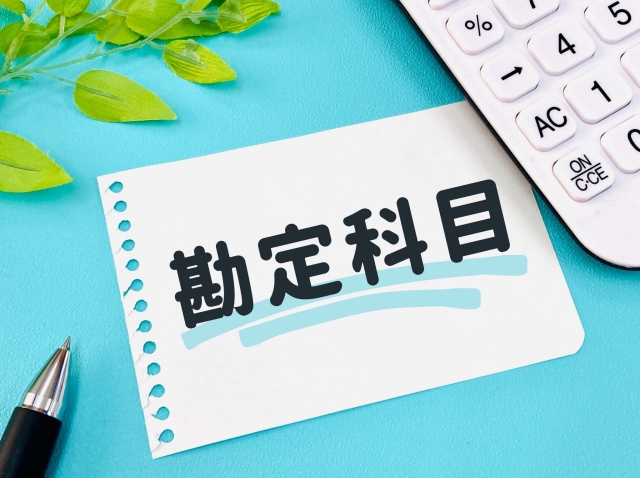
勘定科目(かんじょうかもく)とは、企業や個人事業主の取引において発生するお金の流れ、要するに、「どこに支出したのか」や「入金の理由」を示す「見出し」のことをいいます。読み方は「かんじょうかもく」とされています。
家庭で家計簿をつける際に「光熱費」や「家賃」といった項目で支出を分類するように、会社や個人事業主でも「売上」や「消耗品費」といった勘定科目を用いてお金の流れを分類・記録します。これにより事業の家計簿をつけ、経営の状態を知ることが可能になります。
勘定科目が使用される主な目的は以下の通りです。
取引の分類と記録
日々の膨大な取引を適切に分類し、整理して記録するための基準となります。勘定科目を用いることで、誰が帳簿を見ても同じ理解が得られるようになります。
決算書の作成
日々の取引を勘定科目ごとに振り分けて記録する「仕訳」を行った結果、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などの決算書が作成されます。
これらの決算書は、会社の利害関係者(株主や銀行など)に経営状態を知ってもらうための重要な資料となります。
経営分析のためのデータ提供
勘定科目ごとに集計された数字を見ることで、何にいくら使ったのか、いくら入金・出金の予定があるのかを把握し、経営状況を可視化できます。
これは、事業の方向性を判断し、改善点を見つけるための重要な情報となります。また、法人税や消費税の確定申告の材料としても使用されます。
5つの主要な分類 勘定科目の例と一覧
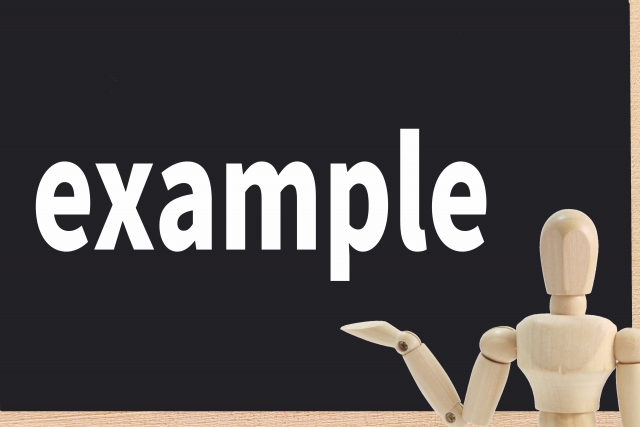
勘定科目は大別して以下の5つのカテゴリーに分かれます。これらのカテゴリーは決算書のうち「貸借対照表」に表示される「資産」「負債」「純資産」と、「損益計算書」に表示される「収益」「費用」に分かれています。
資産 Assets
会社が保有する財産であり、将来的に会社に収益をもたらすと期待されるものを指します。
貸借対照表では、流動資産(1年以内に現金化しやすいもの)、固定資産(1年を超えて保有・使用し、現金化しにくいもの)、繰延資産(支出はあったが効果が長期に及ぶもの)の3つに分けられます。
主な勘定科目例
- 流動資産: 現金、預金、売掛金、商品、原材料、短期貸付金など
- 固定資産: 建物、土地、車両運搬具、ソフトウェアなど
- 繰延資産: 創立費、社債発行費等、開発費など
負債 Liabilities
将来の支払い義務を示す負債を表す勘定科目です。銀行からの借入金や、取引先への買掛金などが該当します。
返済期限に応じて、流動負債(1年以内に返済義務のあるもの)と固定負債(1年を超えて支払うもの)の2つに分けられます。
主な勘定科目例
- 流動負債: 買掛金、支払手形、短期借入金、未払金、預り金など
- 固定負債: 長期借入金、社債など
純資産 Net Assets
「会社の純粋な資産」を指し、資産から負債を差し引いた額となります。株主からの出資金や、会社が生み出した利益の蓄積が含まれるため、返済の必要がありません。
主に株主資本(株主からの出資金や留保利益)と株主資本以外(新株予約権、評価・換算差額等など)に分けられます。
主な勘定科目例
- 資本金、その他資本剰余金、繰越利益剰余金、新株予約権など
収益 Revenue
会社が事業活動などで得た収入を指します。売上高(本業で得た収入)、営業外収益(本業以外の収入)、特別利益(臨時に発生した収入)の3つに分けられます。
主な勘定科目例
- 売上、受取利息、雑収入、固定資産売却益など
費用 Expenses
収益を生み出すためにかかった支出を指します。多くの人が「経費」としてイメージするのはこの費用の勘定科目です。
売上原価(売れた商品の仕入れや製造にかかった費用)、販売費及び一般管理費(商品販売や会社管理にかかる費用)、営業外費用(本業以外で定期的に発生する費用)、特別損失(臨時に発生した損失)の4つに分けられます。
主な勘定科目例
- 売上原価: 仕入高、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高
- 販売費及び一般管理費: 給料(給料手当)、広告宣伝費、消耗品費、旅費交通費、租税公課、地代家賃、交際費、会議費、新聞図書費、車両費など
- 営業外費用: 支払利息、雑損失など
- 特別損失: 固定資産売却損、災害損失など
勘定科目設定の重要性とルール

勘定科目の設定には、法的な決まりがないため、会社や個人事業主が自由に決めることができます。しかし、正確で効率的な会計処理を行うためには、守るべきいくつかの基本的なルールがあります。
一般的な勘定科目を設定する
自由に設定できるとはいえ、勘定科目をもとに作成する財務諸表は外部に示される機会も多いため、第三者が見ても理解できるよう、一般的な勘定科目を採用することが推奨されます。
適当な名前をつけたり、場当たり的な社内ルールで仕訳したりすることは避けるべきです。会計ソフトにはあらかじめ一般的な勘定科目が用意されていることが多いため、それらを基準にカスタマイズすると良いでしょう。
一度決めたら継続して使用する(継続性の原則)
企業会計には「継続性の原則」という重要な決まりがあり、一度決めた勘定科目は使い続ける必要があります。同じ取引なのに毎回違う勘定科目を使用することは認められていません。
社内で統一した名称を使用する
勘定科目は社内で名称を統一して運用することが大切です。部署や担当者ごとに呼び方がばらつくと、会計処理が混乱する恐れがあります。
特に経理部門外の社員が伝票を作成する場合でも、誰もが理解できる明確な名称を設定し、社内規定として一覧を整備することが望ましいとされています。
分かりやすい名称を心がける
勘定科目の名称は、取引内容が「一目で理解できるような分かりやすいもの」を設定すべきです。
業界の専門用語や難解な用語、漠然とした表現は避け、実際の業務内容を反映した具体的な名称を用いることで、入力ミスを防ぎ、効率的な会計処理が可能になります。
勘定科目と経理業務の効率化

勘定科目を正確に運用することは重要ですが、日々の仕訳作業は多大な手間と時間を要します。特に取引件数が多い場合、入力ミスや計算ミスなどのリスクも伴います。
現代の経理業務では、会計ソフトの活用が一般的であり、勘定科目を用いた仕訳作業を大幅に効率化できます。
勘定科目を用いた自動仕訳機能
多くの会計ソフトでは、銀行口座やクレジットカード、決済サービスと連携することで、取引明細を自動で取り込み、AIが勘定科目を自動で推測して仕訳を登録してくれます。
これにより、入力の手間を大幅に削減し、経理初心者でも安心して仕訳作業を行えます。リアルタイムな経営状況把握: 会計ソフトが自動集計するレポート機能(例:残高試算表)を活用すれば、自社の財務状況をリアルタイムで確認できます。これにより、経営の意思決定に役立つ正確なデータが迅速に提供されます。
経費精算システムとの連携
経費精算システムと法人カードを連携させることで、法人カードの利用明細が自動的に取り込まれ、入力ミスや不正防止に繋がり、仕訳作業がさらに効率化されます。これにより、経理担当者の負担軽減や生産性向上を実現できます。
- あわせて読みたい
まとめ

勘定科目は、事業におけるお金の流れを分類・整理するための「見出し」であり、会社や個人事業の経営状態を正確に把握するために欠かせないものです。
勘定科目の理解と適切な運用は、経理業務の基本であると同時に、会社の経営を可視化し、成長へと導くための土台となります。難しいと感じる部分もあるかもしれませんが、この記事を参考に、ぜひその本質を深く理解し、ビジネスの成長に役立ててください。
そして勘定科目の設定方法などについてご不明点がある場合は会計アウトソーシングのご利用がおすすめです。様々なメリットがありますので是非ご利用をご検討ください。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
RANKING
お役立ち情報
CASE