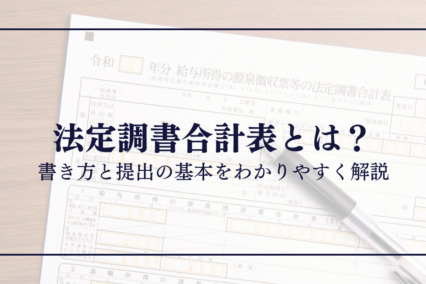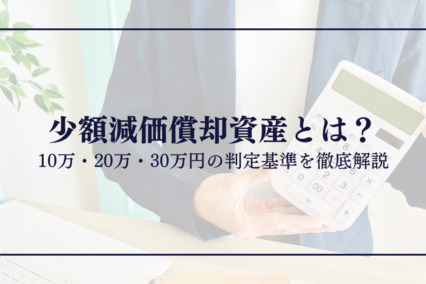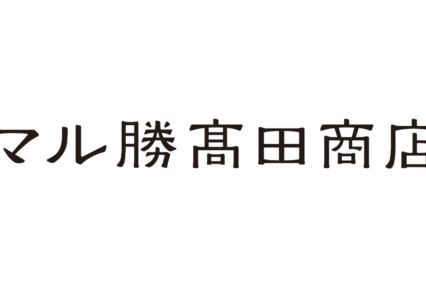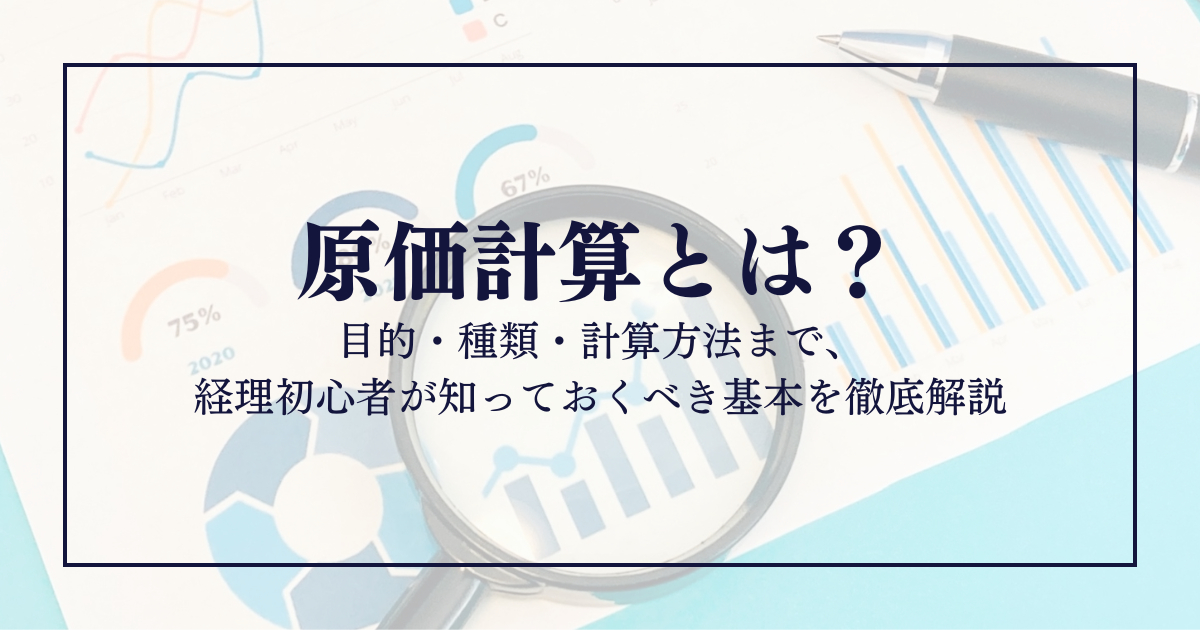
「この製品の価格は、どうやって決まっているのだろう?」「うちの会社は、本当に儲かっているのだろうか?」
経理業務に携わると、このような疑問に直面することがあります。その答えの鍵を握るのが、専門的で少し難しく感じられる「原価計算」です。
原価計算は、単なる数字の計算ではありません。会社の経営状態を正確に把握し、未来の戦略を立てるための重要な羅針盤となる業務です。
この記事では、経理の初心者や、改めて基本を学びたい方に向けて、原価計算の目的や種類、具体的な計算方法まで、基礎から分かりやすく徹底解説します。
原価計算とは?会社の経営を支える重要な仕組み

原価計算は、一言でいえば「製品やサービスの開発・製造にかかったコスト(原価)を正確に計算する手続き」のことです。しかし、その役割はコストを算出するだけにとどまりません。
そもそも原価とは?
原価とは、製品やサービスを生み出すために直接・間接的にかかった費用全体を指します。
例えば、パン屋の「あんぱん」1個の原価には、以下のようなものが含まれます。
- 小麦粉、あんこ、砂糖などの材料費
- パン職人の給与(労務費)
- 工場の家賃、オーブンの電気代、機械の減価償却費(経費)
これらの費用を正確に集計することで、初めて「あんぱん1個作るのにいくらかかったか」が分かります。
「会社の健康診断」としての原価計算
原価計算は、よく「会社の健康診断」に例えられます。定期的に健康診断を受けることで、体の状態を把握し、病気の予防や早期発見に繋がるように、原価計算を行うことで会社の収益構造という「健康状態」を可視化できます。
「材料費が高騰している」「特定の工程で時間がかかりすぎている」といった問題点を早期に発見し、コスト削減や生産性向上といった改善策を打つための重要な判断材料となるのです。
なぜ原価計算は重要なのか?その3つの目的

原価計算は、主に以下の3つの重要な目的のために行われます。
目的1:正確な財産評価と損益計算
会社は、決算時に財務諸表(貸借対照表や損益計算書)を作成する義務があります。このとき、売れ残った製品(在庫)がいくらの価値があるのか、そして、当期に売れた製品のコスト(売上原価)はいくらだったのかを正確に報告しなければなりません。原価計算は、この「在庫の価値」と「売上原価」を算出するための根拠となります。
目的2:適正な価格設定
製品やサービスの価格を決める際、その製品を作るのにかかった原価が分からなければ、利益が出る価格を設定できません。原価は、いわば価格設定の最低ラインです。原価を正確に把握することで、利益を確保しつつ、市場で競争力のある価格を設定することが可能になります。
目的3:経営管理への活用
原価計算で得られたデータは、経営の意思決定に役立つ貴重な情報源となります。
- コスト削減: どの部門や工程でコストが多くかかっているかを分析し、改善目標を立てる。
- 予算管理: 次期の生産計画に基づき、必要な予算を精度高く見積もる。
- 業績評価: 部門ごとの収益性を評価し、より効率的な経営を目指す。
このように、原価計算は過去の数値をまとめるだけでなく、未来の経営戦略を立てるためにも不可欠です。
原価計算の種類と分類

原価計算を理解するために、まずは原価がどのように構成され、分類されるのかを知る必要があります。
原価の3つの要素(材料費、労務費、経費)
原価は、その発生形態によって大きく3つに分類されます。
- 材料費: 製品の製造のために消費された物品のコスト。(例:木材、鉄、部品)
- 労務費: 製品の製造のために費やされた労働力への対価。(例:工員の賃金、給与)
- 経費: 材料費、労務費以外のすべてのコスト。(例:工場の家賃、水道光熱費、減価償却費)
原価の分類(直接費・間接費)
上記の3つの要素は、さらに「特定の製品に直接結びつけられるか」という観点で2つに分類されます。
- 直接費: どの製品のためにいくらかかったかが明確に分かる原価。
- 直接材料費: 特定の製品に使われた主要な材料。
- 直接労務費: 特定の製品の加工に直接従事した工員の賃金。
- 間接費: 複数の製品にまたがって発生するため、どの製品にいくらかかったか直接分からない原価。
- 間接材料費: 複数の製品に共通して使う補助的な材料(例:接着剤、釘)。
- 間接労務費: 管理監督者の給与など。
- 間接経費: 工場の家賃、水道光熱費など。
この「間接費」を、後述する「配賦」という手続きで各製品に按分することが、原価計算の重要なポイントです。
原価計算の代表的な方法(実際原価・標準原価)
計算のタイミングや目的によって、いくつかの方法があります。
- 実際原価計算: 製造後に「実際に発生した金額」を基に計算する方法。正確な原価を把握できますが、計算に時間がかかります。
- 標準原価計算: 事前に「目標とすべき標準的な原価」を設定し、実際にかかった原価と比較してその差(差異)を分析する方法。予算管理や業績評価に役立ちます。
【初心者向け】原価計算の具体的な流れと計算方法

ここでは、実際原価計算の基本的な流れを3つのステップで解説します。
ステップ1:費用の収集と分類
まず、その期間(通常は1ヶ月)に発生したすべての費用を経理データから収集します。そして、それらを「材料費」「労務費」「経費」に分類し、さらに「直接費」と「間接費」に仕分けしていきます。
ステップ2:製造間接費の配賦
次に、ステップ1で分類した「間接費」を、各製品に公平に割り振る「配賦(はいふ)」という作業を行います。どの製品にどれだけ割り振るかを決めるための基準を「配賦基準」といい、生産量、作業時間、機械の稼働時間などが用いられます。
(例)
| 項目 | 全体コスト | 配賦基準 | 製品Aへの配賦基準 | 製品Bへの配賦額 |
| 工場家賃 | 100万円 | 使用面積(A:60%, B:40%) | 60万円 | 40万円 |
ステップ3:製造原価と売上原価の算出
最後に、これまでの計算結果を基に、製品の原価を算出します。
- 当期総製造費用を計算
当期総製造費用 = 直接材料費 + 直接労務費 + 直接経費 + 製造間接費(配賦後)
- 売上原価を計算
売上原価 = 期首の在庫製品額 + 当期製品製造原価 – 期末の在庫製品額
※「当期製品製造原価」とは、その期間中に完成した製品の製造にかかったコストの総額です。この金額を計算する際には、期首と期末の「仕掛品(作りかけの製品)」の金額を考慮する必要があります。
この計算により、最終的に損益計算書に記載される売上原価が確定します。
よくある疑問Q&A
Q. 原価計算と売上原価の違いは?
A. 「原価計算」は製品1個あたりのコストなどを算出する一連のプロセスや仕組みを指します。一方、「売上原価」は、その会計期間に販売された製品の原価の合計額を指し、原価計算によって算出される結果の一つです。
Q. 会計ソフトは必須ですか?
A. 小規模な事業で製品の種類が少なければExcelでの管理も不可能ではありません。しかし、間接費の配賦など計算が複雑になるため、ミスが発生しやすく多大な時間がかかります。一般的には、原価計算機能を持つ会計ソフトの利用が強く推奨されます。正確性と効率が格段に向上します。
Q. 担当者がいなくてもできますか?
A. 原価計算は専門的な知識を要するため、経理の知識があるだけでは正確な計算が難しい場合があります。特に、経営判断に活用するためには、数値を分析するスキルも必要です。担当者がいない、または担当者の負担が大きい場合は、次の選択肢が有効です。
手間やコストを削減!原価計算業務をアウトソーシングする選択肢

原価計算は重要ですが、専門性が高く、手間のかかる業務です。社内での対応が難しい場合、専門家にアウトソーシング(外部委託)する方法があります。
専門家に任せる3つのメリット
原価計算を専門家に任せることには、単に計算を代行してもらう以上の大きなメリットがあります。
業務の専門性と正確性が確保
まず第一に、専門知識を持つプロが担当することで、業務の専門性と正確性が確保されます。 これにより、複雑な計算が正しく行われるだけでなく、法令に準拠した信頼性の高い原価計算が実現します。
より付加価値の高いコア業務に集中できる
社内の経理担当者が煩雑な計算業務から解放されるため、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。日々の計算作業に追われるのではなく、算出されたデータを基にした経営分析や業務改善の企画といった、企業の成長に直結する戦略的な業務に時間を使うことが可能になるのです。
客観的な視点で経営分析を行える
外部の専門家は客観的な視点で経営分析を行えるという利点もあります。社内の人間では気づきにくいコスト構造の問題点や非効率な部分を、第三者の立場から的確に指摘し、具体的な改善策を提案してくれることも少なくありません。
アウトソーシングを検討すべきタイミング
では、どのようなタイミングでアウトソーシングを検討すべきでしょうか。
例えば、製造業を始めたばかりで社内に十分なノウハウがない場合や、現在の原価計算が正しくできているか不安がある場合には、専門家のサポートが有効です。
また、経理担当者の負担が大きく、残業が増えているといった状況も、業務の見直しや外部委託を考えるべきサインと言えるでしょう。
さらに、経営的な視点からコスト削減を進めたいものの、どこから手をつければ良いか分からないという課題を抱えている場合にも、専門家による客観的な分析が問題解決の糸口となります。
まとめ:原価計算から始める効率的なバックオフィス業務

原価計算は、単なる数字合わせの作業ではなく、会社の経営状態を可視化し、より良い未来を築くための強力なツールです。正確な損益の把握、適切な価格設定、そして戦略的な経営判断のすべてが、精度の高い原価計算の上に成り立っています。
経理初心者にとっては複雑に感じるかもしれませんが、まずは今回ご紹介した基本的な考え方や流れを理解することが、大きな一歩となります。
そして、原価計算を正確に行うことは、バックオフィス業務全体の効率化と高度化の始まりでもあります。もし自社での対応に課題を感じているなら、専門家の力を借りることも視野に入れ、より強く、筋肉質な経営体質を目指してみてはいかがでしょうか。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
RANKING
お役立ち情報
CASE