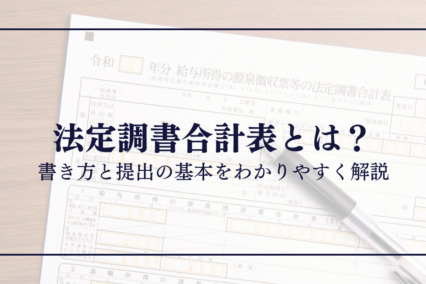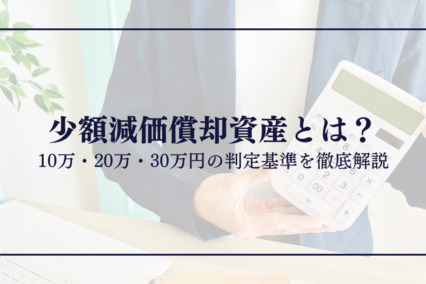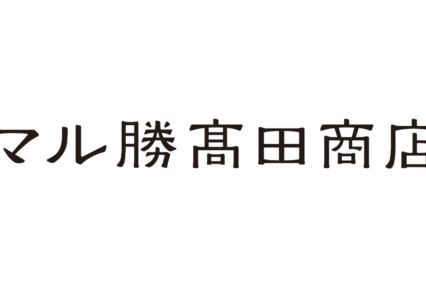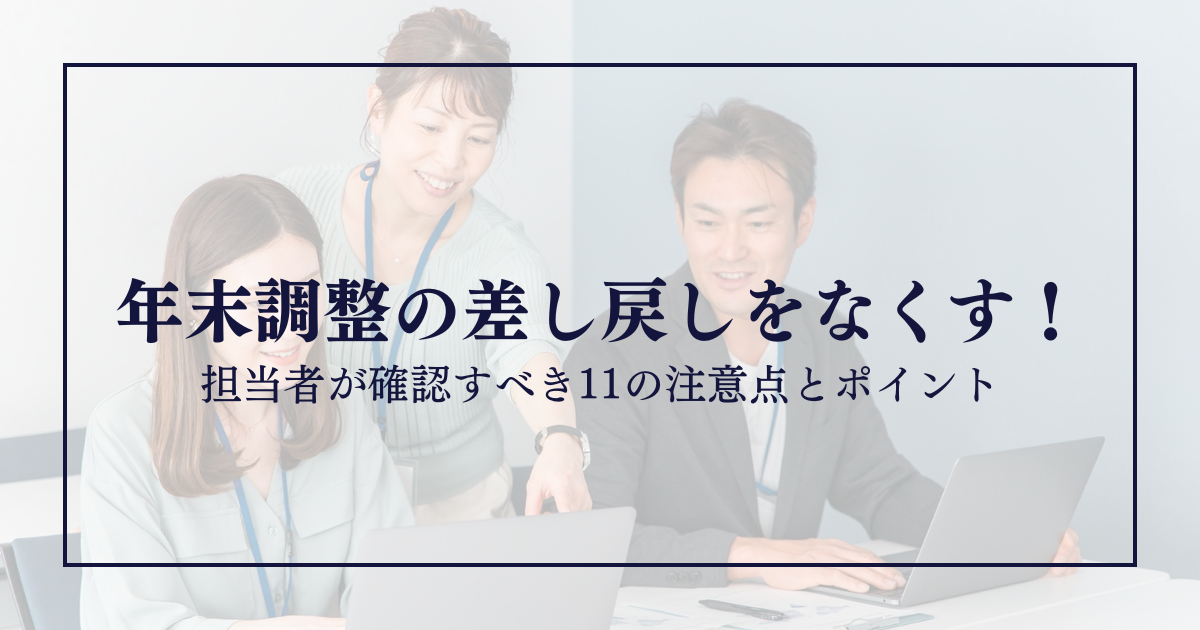
年末調整のシーズンが近づき、書類の山や差し戻しの対応に頭を悩ませていませんか? この記事では、準備段階から提出まで、担当者が陥りがちなミスを防ぐための11の具体的なチェックポイントを徹底解説します。業務の属人化を防ぎ、効率化を図るヒントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
はじめに:年末調整業務に潜むリスクと「確認」の重要性

毎年、年末が近づくと多くの企業で本格化するのが「年末調整」です。従業員の所得税を正しく計算し、過不足を精算するこの業務は、企業の義務であり、従業員の生活に直結する非常に重要な手続きと言えます。
しかし、その一方で「従業員からの書類提出が遅れる」「記入ミスによる差し戻しが多発する」「問い合わせ対応に追われて本来の業務が進まない」といった悩みを抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。
年末調整のミスは、単なる手戻りの発生だけでなく、追徴課税や延滞税といったペナルティにつながる可能性も否定できません。また、従業員からの信頼を損なう原因にもなり得ます。
こうしたリスクを回避し、円滑に業務を進めるために不可欠なのが、各工程における「丁寧な確認」です。本記事では、年末調整の準備段階から計算・提出段階までの流れに沿って、担当者が特に注意すべき11のポイントを分かりやすく解説します。
【準備段階】業務開始前に確認すべき3つの注意点

年末調整をスムーズに進めるためには、事前の準備が成功の鍵を握ります。本格的な業務開始前に、以下の3つの点を確認しておきましょう。
①今年の税制改正点は把握できていますか?
所得税に関連する法律は、毎年のように改正が行われます。控除額の変更や申告書の様式変更など、その年の改正点を正確に把握しておくことは、正しい年末調整を行う上での大前提です。
「去年と同じだろう」という思い込みは、重大なミスにつながる可能性があります。国税庁のウェブサイトなどで最新情報を必ず確認し、変更点を社内の関連部署や従業員へも周知する準備を進めましょう。
②対象者の洗い出しは万全ですか?(中途入退社・休職者など)
年末調整の対象となるのは、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員です。しかし、正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、一定の要件を満たす場合は対象に含まれます。
一方で、年収が2,000万円を超える従業員や、年の途中で退職し再就職の見込みがない従業員などは対象外となります。中途入社・退職者、長期休職者、役員など、判断に迷うケースを事前にリストアップし、対象者を正確に確定させることが、後の手戻りを防ぐ第一歩です。
③従業員へのアナウンス計画は具体的ですか?
担当者側の準備が万全でも、従業員の協力がなければ業務は円滑に進みません。従業員に対して、具体的で分かりやすいアナウンスを計画することが重要です。
「いつまでに」「どの書類を」「どこへ」提出するのかという基本的な情報はもちろん、今年の変更点やよくある記入ミスなどをまとめた資料を配布すると親切です。提出方法(紙または電子)、問い合わせ窓口、全体のスケジュールを明記し、計画的に周知しましょう。
【書類回収・確認段階】担当者が陥る5つの落とし穴

従業員から申告書が提出されたら、内容を正確に確認する作業が始まります。ここでは特にミスが多く、差し戻しの原因となりがちな5つのポイントを見ていきましょう。
扶養控除申告書:16歳未満の扶養親族の記入漏れ
16歳未満の扶養親族は、所得税の計算における「控除対象扶養親族」には該当しません。しかし、住民税の計算にはこの情報が必要となります。所得税に関係ないからと、従業員が記入を省略してしまうケースが散見されますが、これは典型的な記入漏れです。申告書下部の「住民税に関する事項」欄に、16歳未満の扶養親族の氏名などが正しく記載されているかを確認しましょう。
配偶者控除申告書:夫婦双方の「所得要件」の確認
配偶者控除や配偶者特別控除には、従業員本人と配偶者の双方に所得要件が定められています。従業員が配偶者の所得を低く見積もっていたり、自身の所得要件を超えていることに気づかなかったりするケースは少なくありません。特にパート収入などは、交通費が非課税かどうかなど、細かな確認が必要です。提出された所得見積額に疑問点があれば、給与明細などで確認を促すことも大切です。
保険料控除申告書:証明書原本の添付と金額の不一致
生命保険料や地震保険料などの控除を受けるためには、保険会社などが発行する「控除証明書」の原本を添付するか、「電子的控除証明書」のデータを提出する必要があります。紙の証明書をコピーしたものや、スマートフォンで撮影したデータなどでの提出は認められないため、ご注意ください。必要があります。コピーやデータでの提出は認められないため、必ず原本が添付されているかを確認してください。また、申告書に記載された金額と証明書の金額が一致しているか、計算は正しいかといった基本的なチェックも、見落としやすいポイントです。
住宅ローン控除申告書:2年目以降の申告内容のチェック
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目は従業員本人が確定申告を行う必要があります。年末調整の対象となるのは2年目以降です。この手続きには、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2種類が必要です。両方の書類が揃っているか、記載内容に矛盾がないかを確認しましょう。
マイナンバー:収集・管理・廃棄ルールの再確認
年末調整では、従業員本人や扶養親族のマイナンバーを取り扱います。マイナンバーは法律で厳格な管理が義務付けられている特定個人情報です。収集目的を明確に従業員に伝え、施錠できる場所で保管するなど、安全管理措置が適切に行われているかを再確認してください。また、法定保存期間を過ぎた書類は、復元不可能な形で速やかに廃棄する必要があります。
【計算・提出段階】最終工程でミスを防ぐためのポイント

書類の確認が終われば、いよいよ最終工程です。計算から行政機関への提出まで、最後まで気を抜かずに進めましょう。
ポイント①:年税額の算出:システム任せにしないダブルチェック体制
多くの企業では給与計算システムを導入しており、年税額の計算は自動化されているかもしれません。しかし、システムも万能ではありません。最初の設定ミスや、従業員情報の入力ミスがあれば、計算結果も誤ってしまいます。システムによる計算結果を鵜呑みにせず、必ず別の担当者が検算する、あるいは計算プロセスを確認するといったダブルチェック体制を構築することが、ミスの防止に極めて有効です。
ポイント②:過不足金の精算:給与明細への正確な反映
算出された年税額と、1年間に徴収した源泉徴収税額との差額(過不足金)を精算します。還付または追加徴収する金額は、通常12月または1月の給与で調整されます。この精算額を給与明細に「年末調整還付」や「年末調整徴収」といった分かりやすい項目で正確に記載することが重要です。従業員が自身の給与明細を見て、正しく手続きが行われたことを確認できるようにしましょう。
ポイント③:法定調書の提出:期限と提出方法の再確認
年末調整が完了したら、税務署や市区町村へ法定調書などを提出します。「給与所得の源泉徴収票」や「支払調書」などを、定められた様式で作成し、原則として翌年の1月31日までに提出しなければなりません。提出先や提出期限を改めて確認し、遅延のないようにしましょう。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)やeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告は、業務効率化の観点からも推奨されます。
年末調整業務の「属人化」と「非効率」を解消しませんか?

ここまでのポイントを実践してもなお、「年末調整の時期は特定の担当者に業務が集中して大変だ」と感じる企業は多いかもしれません。それは、業務の「属人化」や「非効率」が原因であると考えられます。
『あの人にしか分からない』はもう限界!問い合わせ対応の時間を削減
年末調整に関する問い合わせが、特定の担当者に集中していませんか?担当者が不在の際に業務が滞るリスクは非常に大きいと言えます。まずは、誰がどのような問い合わせに、どれくらいの時間をかけているのかを把握することから始めましょう。
毎年同じ問い合わせに対応していませんか?FAQ化のすすめ
問い合わせの内容を分析すると、毎年同じような質問が繰り返されていることに気づくはずです。「配偶者の年収がいくらまでなら控除を受けられますか?」「この保険は控除の対象ですか?」といった頻出の質問は、回答とあわせてFAQ(よくある質問)として文書化し、社内で共有しましょう。従業員が自己解決できる環境を整えることで、担当者の問い合わせ対応時間を大幅に削減できます。
その業務、担当者以外でも対応できますか?マニュアル化の重要性
業務が特定の個人の知識や経験に依存している状態は、非常に不安定です。担当者の異動や退職によって、業務品質が低下するリスクを常に抱えています。誰が担当しても一定の品質を保てるよう、年間のスケジュール、作業手順、判断基準などをまとめた業務マニュアルを作成することが不可欠です。
根本的な解決策としての「電子化」と「アウトソーシング」
FAQやマニュアルの整備は有効な対策ですが、より根本的な解決を目指すのであれば、「電子化」と「アウトソーシング」が有力な選択肢となります。年末調整システムを導入して電子化すれば、書類の配布・回収・チェックといった作業を効率化でき、ペーパーレス化も実現します。また、専門知識を持つ外部の企業に業務自体をアウトソーシングすれば、担当者を煩雑な作業から解放し、より付加価値の高いコア業務に集中させることが可能です。
年末調整に関するQ&A

Q1. アルバイトやパートタイマーも年末調整の対象になりますか?
A1. はい、対象になる場合があります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで在籍している場合は、原則として年末調整の対象となります。年収が103万円以下であっても、月々の給与から源泉徴収されている場合は、年末調整によって所得税が還付される可能性があります。
Q2. 年の途中で退職した従業員の年末調整はどうすれば良いですか?
A2. 原則として、企業側で年末調整を行う必要はなく、退職者本人が翌年に確定申告を行います。ただし、「年内に再就職する見込みがない」「年間の給与総額が103万円以下」など、一定の条件を満たす場合は、退職時に企業が年末調整を行うこともあります。
Q3. 従業員がマイナンバーの提出を拒否した場合はどうすれば良いですか?
A3. 源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は法律上の義務であることを従業員に説明し、提出を再度依頼してください。それでも提出を拒否された場合は、提出を求めた経緯などを記録として残した上で、マイナンバーを記載せずに書類を作成・提出することになります。提出を強要することはできません。
おわりに:正確な年末調整で、企業の信頼性を高めるために

本記事では、年末調整の差し戻しやミスを防ぐための具体的な注意点と、業務改善のポイントについて解説しました。
年末調整は、年に一度の煩雑な業務と捉えられがちです。しかし、この手続きを正確かつスムーズに行うことは、法令を遵守するクリーンな企業姿勢を示すことにつながります。そして何よりも、従業員が安心して働くための信頼関係の基盤となるものです。
今回ご紹介したチェックポイントを参考に、ぜひ自社の年末調整業務を見直してみてください。一つひとつの丁寧な確認と、業務改善への取り組みが、担当者の負担を軽減し、企業全体の信頼性を高める一助となれば幸いです。
BPaaSや経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
RANKING
お役立ち情報
CASE