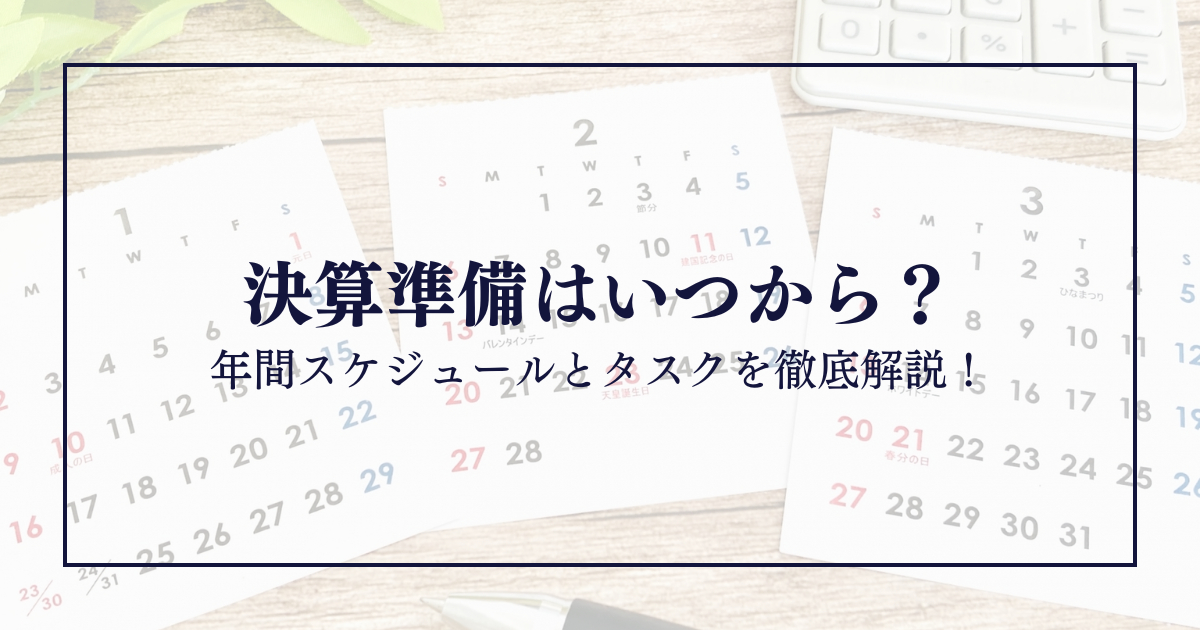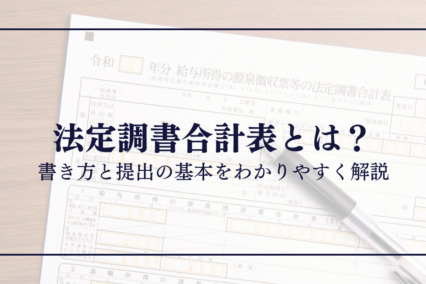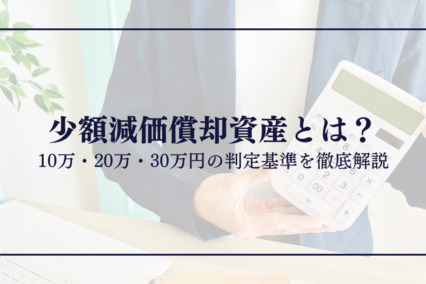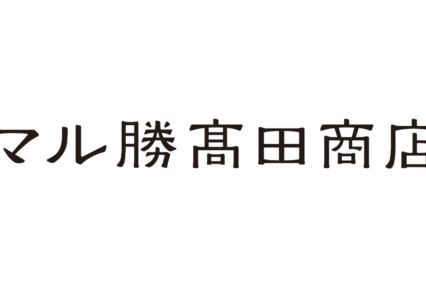決算期が近づくと、「一体いつから準備を始めれば良いのだろう」「毎年のことなのに、なぜか直前で慌ててしまう」といった不安や焦りを感じる経理担当者の方は少なくないでしょう。
決算は、企業の1年間の成績をまとめ、納税額を確定させる重要な業務です。しかし、その作業は多岐にわたり、計画なくしてスムーズに進めることは困難です。
本記事では、決算準備を始めるべき理想的なタイミングから、年間の具体的なスケジュール、そして抜け漏れを防ぐためのチェックリストまでを網羅的に解説します。さらに、業務を効率化するためのポイントやよくある疑問にもお答えします。
この記事を読めば、決算までの道のりが明確になり、余裕を持ったスケジュールで質の高い決算業務を実現できるはずです。
なぜ決算準備は早めのスタートが重要なのか?

決算業務を単なる「年に一度の義務」と捉えていると、その重要性を見過ごしがちです。早めに準備を始めることには、単に直前の忙しさを回避する以上の、企業経営にとって大きなメリットが存在します。
決算の正確性を高めミスを防ぐため
決算期末の限られた時間の中で膨大な作業を行おうとすると、どうしても焦りが生まれ、普段ならしないようなミスを誘発します。売上や経費の計上漏れ、在庫の数え間違い、単純な計算ミスなど、一つひとつのエラーが積み重なると、決算書の信頼性を大きく損ないかねません。
早い段階から準備に着手すれば、一つひとつの取引を丁寧に確認する時間が確保でき、複数人でのダブルチェックも可能になります。これにより決算書の正確性が向上し、税務調査などで指摘を受けるリスクを低減できます。
業務負荷の分散と残業を削減するため
決算期になると経理部門だけが深夜まで残業している、という光景は多くの企業で見られます。決算準備が遅れるほど、業務負荷は決算月から申告期限までの短期間に極端に集中し、従業員に大きな負担を強いることになります。
年間を通じて計画的に準備を進めることで、この業務負荷を平準化できます。特定の時期に残業が常態化することを防ぎ、従業員のワークライフバランスを保ちながら、健全な職場環境で決算を乗り越えることが可能になります。
経営状況の分析と次年度計画に活かすため
決算書は、税金を計算するためだけのものではありません。自社の財政状態や収益性を客観的に示す「経営の成績表」です。
早期に決算準備を進め、早い段階で年間の業績見通しを立てることで、経営陣は的確な手を打つ時間が生まれます。例えば、想定以上の利益が見込まれる場合は戦略的な節税対策を検討したり、設備投資のタイミングを計ったりできます。逆に業績が厳しい場合は、次年度に向けた具体的な改善策を早期に立案できます。
決算準備の年間スケジュール!いつから何をする?

決算準備は、決算日を過ぎてから始めるものではありません。理想は「決算期末の3ヶ月前」からのスタートです。ここでは、時期ごとにやるべきことを具体的に解説します。
【決算期末3ヶ月前】予測と準備の開始
この時期は、本格的な決算作業に向けた助走期間です。年間の着地点を予測し、大きな論点を洗い出します。
- 月次試算表の確認: これまでの月次試算表に異常な数値や不明な点がないかを確認します。
- 業績予測: 年間の売上・費用・利益の着地見込みを予測し、納税額をシミュレーションします。
- 大きな取引の確認: 固定資産の購入や売却、多額の修繕費など、特別な会計処理が必要な取引がなかったかを確認します。
- 節税対策の検討: 業績予測に基づき、実行可能な節税対策があれば検討を開始します。
【決算期末1~2ヶ月前】詳細の確認と整理
より具体的な勘定科目の整理に入ります。帳簿の数字と実際の残高を合わせる作業が中心です。
- 現金・預金残高の確認: 帳簿残高と実際の銀行口座の残高が一致しているかを確認します。
- 売掛金・買掛金の残高確認: 得意先・仕入先ごとの残高を確認し、回収や支払いに遅延がないかをチェックします。
- 棚卸資産(在庫)の準備: 実地棚卸の計画(日程、担当者、方法)を立てます。
- 仮払金・仮受金の精算: 内容が不明なまま残っている仮払金や仮受金を精算し、正式な勘定科目に振り替えます。
【決算月】取引の最終確定
いよいよ決算月です。この1ヶ月間の取引を正確に計上し、1年間の帳簿を締めくくります。
- 期中取引の完了: 決算日までのすべての請求書発行、経費精算などを漏れなく行います。
- 実地棚卸の実施: 事前に立てた計画に沿って、商品や製品、仕掛品などの在庫を実際に数え、数量と金額を確定させます。
- 決算整理仕訳の準備: 減価償却費の計上や、期をまたぐ費用の整理(未払費用・前払費用など)の準備を進めます。
【決算後~2ヶ月以内】申告と納税
決算日を過ぎたら、最終的な決算書と税務申告書を作成し、期限内に申告と納税を完了させます。
- 決算書の作成: すべての決算整理仕訳を計上し、貸借対照表、損益計算書などの財務諸表を確定させます。
- 法人税等の申告書作成: 決算書をもとに法人税、消費税、法人事業税などの申告書を作成します。
- 株主総会での承認: 作成した決算書を株主総会で報告し、承認を得ます。
- 申告と納税: 税務署や都道府県、市町村へ申告書を提出し、納税を行います。(原則、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内)
決算準備で抜け漏れを防ぐためのチェックリスト

年間のスケジュールに沿って、具体的なタスクをチェックリストにまとめました。自社の決算準備にご活用ください。
決算期末3ヶ月前までに行うこと
- 月次試算表の内容に異常がないか確認する
- 年間の利益と納税額を予測する
- 実行可能な節税対策を洗い出す
- 今期に大きな資産の購入や売却がなかったか確認する
- 税理士と決算の打ち合わせ日程を調整する
決算期末1~2ヶ月前までに行うこと
- 現金・預金の残高と帳簿残高を照合する
- 売掛金・買掛金の残高を得意先・仕入先ごとに確認する
- 回収不能な売掛金がないか(貸倒れの検討)を確認する
- 実地棚卸のスケジュールと担当者を決定する
- 仮払金・仮受金の内容を精査し精算する
決算月に行うこと
- 決算日までのすべての取引を記帳する
- 請求書や領収書などの証憑書類を整理・保管する
- 計画通りに実地棚卸を行う
- 減価償却費や各種引当金など、決算整理仕訳の対象をリストアップする
決算後に行うこと
- すべての決算整理仕訳を計上する
- 勘定科目内訳明細書を作成する
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)を作成する
- 法人事業概況説明書を作成する
- 税務申告書を作成し、社内承認を得る
- 株主総会で決算の承認を得る
- 期限内に税務申告と納税を完了させる
決算準備を効率化するための3つのポイント

毎年訪れる決算をよりスムーズに進めるためには、日頃からの仕組みづくりが不可欠です。ここでは、決算準備を効率化するための3つの重要なポイントを紹介します。
ポイント1:毎月の月次決算を徹底する
年次決算を「1年分の成績表」とするなら、月次決算は「毎月の小テスト」です。12回分の小テストを高い精度で実施していれば、期末にまとめて大きな負担がかかることはありません。毎月、帳簿と実際の残高を合わせ、その月の損益を確定させるプロセスを習慣化することで、問題点の早期発見に繋がり、年次決算はその集計作業が中心となります。
ポイント2:会計システムやツールを積極的に活用する
現代において、手作業や表計算ソフトのみで経理業務を行うのは非効率であり、ミスの温床にもなり得ます。クラウド会計システムを導入すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、仕訳作業を大幅に自動化できます。これにより、経理担当者は単純な入力作業から解放され、より高度な分析や管理業務に時間を使えるようになります。
ポイント3:税理士などの専門家へ早めに相談する
税法は非常に複雑で、毎年のように改正が行われます。自社だけの判断で会計処理や税務申告を行うと、意図せず誤った処理をしてしまったり、活用できるはずの税制優遇を見逃してしまったりする可能性があります。顧問税理士がいる場合は、決算の予測が見えた段階で早めに相談し、専門的な視点からアドバイスを受けることが、正確で有利な決算への近道です。
決算準備に関するよくある質問

Q. 決算準備でよくある間違いは何ですか?
A. 期末間際の経費計上漏れや、在庫・固定資産に関する計算ミスが挙げられます。また、賞与引当金や貸倒引当金といった、計上すべき引当金の計上忘れもよくある間違いです。これらは月次決算の徹底や、チェック体制の強化によって防ぐことができます。
Q.経理以外の部署の協力が得られない場合はどうすれば良いですか?
A. 決算は経理部門だけの仕事ではないことを、全部署に理解してもらう必要があります。経費精算の早期提出や、在庫確認への協力依頼など、具体的なタスクと締切を明記した上で、早めに全部署へ協力を要請しましょう。なぜその協力が必要なのかという理由を丁寧に説明することも重要です。
Q. もし準備が大幅に遅れてしまったら?
A. すぐに専門家(顧問税理士など)へ相談し、対応の優先順位を決めて作業を進めることが重要です。まずは納税申告に必要な最低限の作業から着手し、落ち着いて一つずつタスクを完了させていきましょう。無申告はペナルティのリスクが高いため、必ず期限内に何らかのアクションを起こすことが大切です。
決算準備のさらなる効率化ならBPIOにお任せ

これまで解説したように、決算準備には多くの工数がかかり、正確性も求められます。
「毎月の月次決算を徹底したいがリソースが足りない」「手作業によるミスをなくしたい」といった課題をお持ちではないでしょうか。
そのような課題を解決し、決算業務を抜本的に効率化するのが「BPIO」です。
BPIOは、経理業務の自動化やペーパーレス化を推進し、決算準備にかかる時間を大幅に削減します。
- 月次決算の早期化: 日々の取引データを自動で取り込み、月次決算プロセスを加速させます。
- ヒューマンエラーの防止: 自動仕訳機能により、手入力によるミスを減らし、決算の正確性を高めます。
- ペーパーレス化の推進: 請求書や領収書を一元管理し、書類を探す手間や保管コストを削減します。
決算準備の属人化を防ぎ、よりスムーズで戦略的な経理体制を構築するために、ぜひBPIOの導入をご検討ください。
まとめ|計画的な準備で、余裕のあるスムーズな決算を実現

決算準備をいつから始めるか、その答えは「決算期末の3ヶ月前」が理想です。
早めに着手し、計画的なスケジュールを立てることで、決算書の正確性を高め、経理部門の負担を減らすだけでなく、経営戦略に活かせる貴重な時間を生み出すことができます。
日頃から月次決算を徹底し、会計システムや専門家の力を有効に活用しながら、年に一度の決算を慌ただしい「イベント」から、企業の成長を確認する「マイルストーン」へと変えていきましょう。
本記事のチェックリストを活用し、今日からできる準備を始めて、余裕のあるスムーズな決算を実現してください。
BPaaSや経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
RANKING
お役立ち情報
CASE