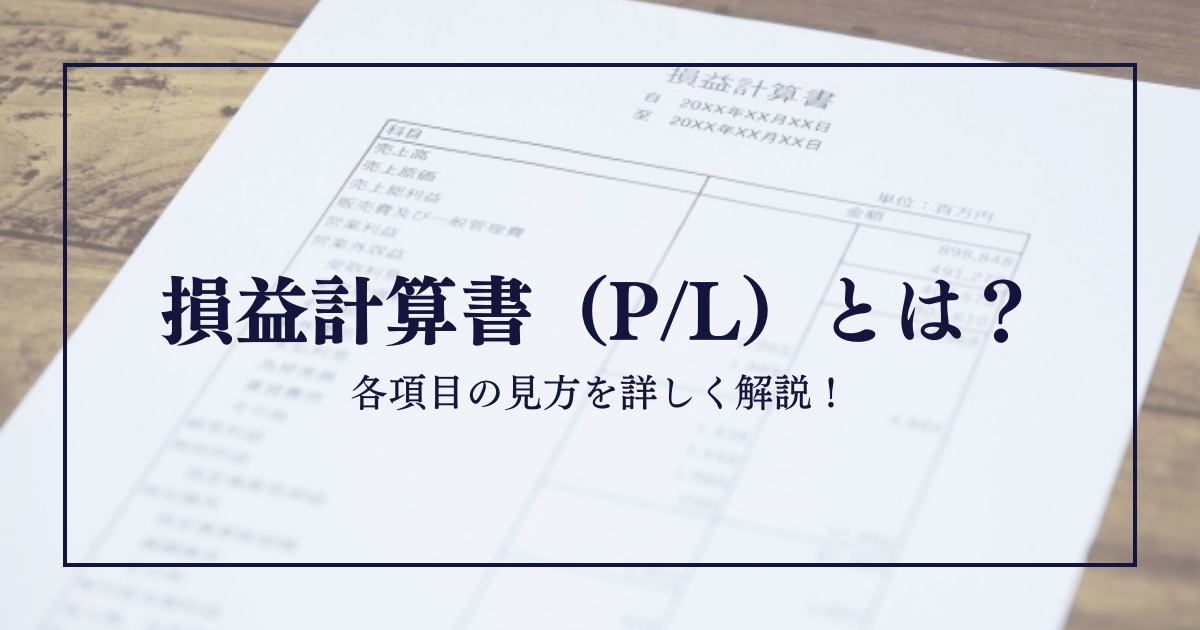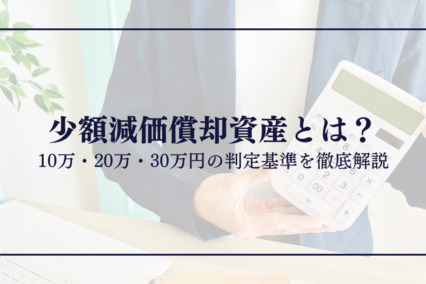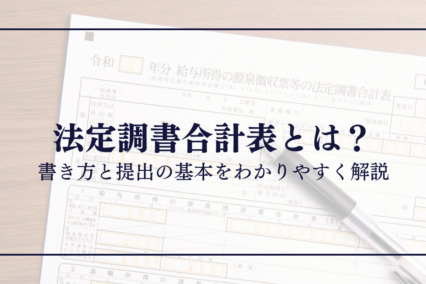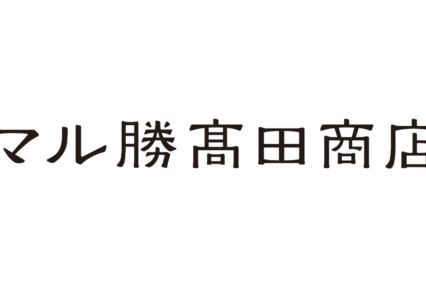損益計算書は、企業の経営状況を把握するために欠かせない決算書の一つです。売上高や費用、利益などを明確に示し、企業がどれだけ効率的に資源を活用しているか、またはどの部分で改善が必要かを把握する手助けをします。
本記事では、損益計算書の基本的な構成や、どのように活用すべきかについて詳しく解説します。
損益計算書は一定期間の業績を示す決算書

損益計算書は、会社の収益と費用に関する損益を一つの会計期間でまとめた書類で、決算書(財務諸表)の一部です。また、「PL(Profit and Loss Statement)」とも呼ばれます。
すべての企業は決算時に、この損益計算書を貸借対照表とともに必ず作成しなければなりません。
個人事業主の場合には所得税の確定申告で青色申告を選んだ場合、青色申告決算書の一部が損益計算書に相当します。
損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)の違い

損益計算書と貸借対照表は、構成される要素が異なります。
損益計算書は、収益と費用で構成されており、会社の経営成績を示す書類です。特定の期間(例えば1年間)における収益や費用の発生状況を元に、最終的な利益や損失を表します。
一方、貸借対照表は、資産、負債、純資産の3つで構成されており、会社の財政状態を示す書類です。特定の時点における資産と負債のバランス、そして資産から負債を引いた純資産の状態を示します。
損益計算書と貸借対照表は、どちらも会社の経営状況を把握するために重要ですが、それぞれ異なる観点から情報を提供します。
- あわせて読みたい
損益計算書における利益の種類と見方

損益計算書には以下の利益が記載されているのが通常です。
売上総利益
営業利益
経常利益
税引前当期純利益
当期純利益
この章では、それぞれの利益の特徴について説明していきます。損益計算書を見てみると、「利益」と名の付く項目がいくつも存在していることがわかります。損益計算書は収益と費用を段階的に区分し、5種類の利益を計算することで、会社の成績を多角的に評価できるようになっています。このため、会社がどのようにして利益を上げているのかがわかります。
売上総利益(粗利益)
売上総利益(粗利)は、売上高から売上原価を引いた金額で、製品・サービスの提供での直接的な利益を示します。
一方、営業利益は売上総利益から販管費を引いたもので、企業の本業における収益力を示します。営業利益は売上総利益だけでなく、販売費や管理費など、本業に関連する間接的なコストも考慮に入れているため、企業の本業の収益性をより包括的に表す指標となります。
営業利益
営業利益とは、損益計算書に記載される利益の一つで、売上総利益(売上高から売上原価を引いた金額)から「販売費および一般管理費」を差し引いた利益です。簡単に言うと、売上総利益から「販売費および一般管理費」を引いたものが営業利益となります。
営業利益は、売上総利益から「販売費および一般管理費」を引いたものとして、5つの利益の中で2番目に表示されます。
営業利益は、企業の営業活動による成果を示すもので、5つの利益の中でも、経常利益と並び最も注目される重要な指標です。
経常利益
経常利益とは、営業利益に本業以外の収益を加え、さらに損失などを差し引いたものです。本業で営業利益が出ていたとしても、本業以外での損失が大きければ、最終的な利益は圧縮されることになります。
営業外費用には、借入金の利息などが含まれます。
経常利益の計算式
経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用
税引前当期純利益
税引前当期純利益は、法人税を計算する際の元となる利益、経常利益に特別損益を加減したもので、会社が1年間で得た利益です。法人税等は、利益に対して課される税金のことです。
経常利益に臨時的に発生した特別損益を足したり引いたりして算出されます。
税引前当期純利益 = 経常利益 + 特別利益 - 特別損失
特別損益とは、例えば手持ちの土地を売って得た利益など、通常の営業活動とは関係ない臨時的な要因によって発生する利益や損失を指します。たとえ当期純利益が黒字であっても、土地を売って得た利益だけでは、必ずしも良い会社だとは言えません。
損益計算書ではこのような臨時的な要因も反映させることで、企業の業績を多角的に分析できるようになっています。
当期純利益
当期純利益は、「税引前当期純利益」から「法人税等」を差し引いた後の金額です。当期純利益を求めるための計算式は以下の通りです。
当期純利益 = 税引前当期純利益 - 法人税等
つまり、当期純利益は「会社の1年間の最終的な利益」を示すものです。
株主への配当金はこの当期純利益から支払われるため、投資家にとって非常に重要な金額となります。
損益計算書の見方とチェックポイント

損益計算書を理解するためには、どこを見ればどんな情報がわかるかを把握しておくことが重要です。これにより、企業が改善すべき点を見つける手助けになります。
「売上高総利益率(粗利率)」で企業の優良さをチェック
売上高総利益率は、売上高に対する売上総利益の割合を示します。売上総利益は、売上高から売上原価を引いた額なので、売上原価を抑えた企業ほどこの比率は高くなります。
売上高総利益率 = 売上総利益 ÷ 売上高 × 100
売上高総利益率が高いと、収益性が高い商品やサービスを提供している優れた企業であると判断できます。逆に、この比率が低ければ、商品やサービスの収益性が低いことを意味します。売上高総利益率が低い原因としては、過度の値引き、仕入れ価格が適切でない、在庫管理の不備などが考えられます。
「売上高営業利益比率」で本業の収益力を確認
売上高営業利益比率は売上高に占める営業利益の割合です。この比率を見れば、本業でどれほど利益を上げているかがわかります。
売上高営業利益比率 = 営業利益 ÷ 売上高 × 100
売上高営業利益比率が高ければ、本業で利益を生み出す力が強い企業だと評価できます。一方、この比率が低ければ、収益力が弱い企業であると言えるでしょう。
「売上高経常利益比率」で企業の総合的な収益性を確認
売上高経常利益比率は、売上高に対する経常利益の割合です。この指標は、企業の営業活動だけでなく、財務活動から得られる収益を含めた全体的な収益性を示します。
売上高経常利益比率 = 経常利益 ÷ 売上高 × 100
売上高経常利益比率が高い企業は、営業外収益も得ており、安定した経営がされていると考えられます。逆に、この比率が売上高営業利益比率より低い場合、営業外損益がマイナスである可能性が高く、借入金利息の負担が大きいことなどが考えられます。
経常利益は受け取った配当金など、財務活動に影響されるため、本業の収益力を確認するためには、売上高営業利益比率も一緒に確認することが重要です。
まとめ

損益計算書の作成は、企業が健全な経営を行うために欠かせない重要な業務ですが、その作成には専門的な知識と相当の時間を要します。売上高や利益、経費などを正確に把握し、経営戦略を立てるためには、細部にわたる慎重な作業が求められます。そのため、多忙な経営者や専門知識が不足している場合、損益計算書の作成を外部の経理アウトソーシングに委託することを強くおすすめします。
経理アウトソーシングを活用することで、専門家が最新の会計基準に基づき、正確かつ効率的に損益計算書を作成します。これにより、企業は自社の財務状況をリアルタイムで把握でき、迅速な意思決定が可能となります。また、専門家による作成が保証する精度と法的遵守は、経営者が安心して事業運営に集中できる環境を提供します。
さらに、経理業務を外部に委託することで、コスト削減が図れるだけでなく、経理担当者の雇用や教育にかかる負担を軽減することができます。これにより、企業はそのリソースを他の重要な事業活動に振り向けることができ、効率的な経営が実現できます。経理アウトソーシングは、企業の成長を支える強力なパートナーとなり、経営の安定性と競争力向上に寄与することでしょう。
経理BPOならBPIOにお任せください
株式会社BPIOが展開する「BPIO」は、バックオフィス業務を3つの軸で改善するBPOサービスです。

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
RANKING
お役立ち情報
CASE