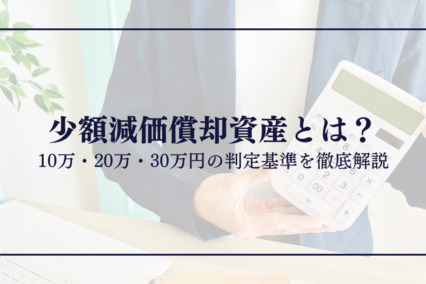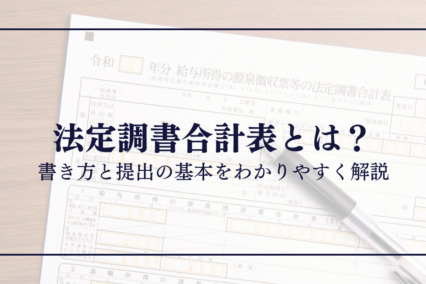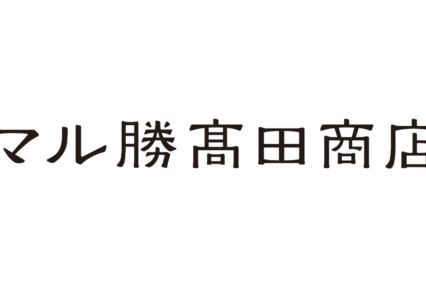貸借対照表は、企業の財政状態を一目で把握できる重要な会計書類です。企業の資産、負債、そして純資産がどのように構成されているかが示されており、企業の経営状態や財務健全性を理解するために欠かせません。
そこで本記事では貸借対照表の基本的な構成や役割などについて解説します。
貸借対照表とは?

貸借対照表は、大きく3つの区分に分けられています。それが「資産の部」「負債の部」「純資産の部」です。
さらに「資産の部」と「負債の部」については、1年を基準として短期と長期に分類され、結果的に5つの項目に分けて考えられます。それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
資産
流動資産
流動資産とは、1年以内に現金化される予定の資産を指します。例えば、売掛金や棚卸資産などが該当します。
また流動資産の中でも特に現金や現金に近い性質を持つもの(現預金・受取手形・売掛金など)は「当座資産」と呼ばれます。
当座資産を多く持つことで突発的な支出が発生した場合にも対応可能となり、企業の財務の安定性が高まります。
固定資産
固定資産とは1年以上の保有を目的とした資産、または現金化までに1年以上かかる資産を指します。以下の3種類に分類されます。
有形固定資産
建物や土地、機械などの「目に見える資産」が該当します。有形固定資産は、経年劣化する建物や機械などの減価償却資産と土地などの非減価償却資産に分けられます。
無形固定資産
「目に見えないけれども価値のある資産」が該当します。営業権や特許権、ソフトウェアなどが代表例です。やはり減価償却資産と非減価償却資産に分類されます。
投資その他の資産
投資を目的とした資産などが該当します。具体的には関連会社株式や満期保有目的の債券、長期前払費用などです。
負債
流動負債
流動負債とは、「1年以内に支払期限が到来する債務」を指します。主に仕入れ代金に関する買掛金や支払手形、他には短期借入金などが含まれます。
固定負債
固定負債は、「支払期限が1年以上先の債務」を指します。長期借入金や退職給付引当金などがこれにあたります。
純資産
純資産は企業が蓄積した利益や株主からの出資によって形成される部分です。負債が「他人資本」と呼ばれるのに対し、純資産は株主資本などから形成されています。
そして株主資本は、以下のような要素で構成されています。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金
- 自己株式
貸借対照表はこれらの要素を通じて企業の財務状況を明確に示しており、会社の安定性や健全性を判断するための重要な資料となります。
貸借対照表と損益計算書の関係性

貸借対照表と損益計算書は密接に関連しており、両方の情報を活用すれば、より正確な財務状況を把握可能です。
貸借対照表項目が損益計算書項目に与える影響
貸借対照表は企業の一時点での資産、負債、純資産を示しています。
この貸借対照表に記載された資産や負債の状況は、次期の損益計算書に大きな影響を与えます。例えば、負債が増加するとその利息などが次期の損益計算書に費用として反映されます。
財務指標の活用
貸借対照表と損益計算書を組み合わせれば、ROE(自己資本利益率)やROA(総資産利益率)など、企業の財務健全性を測る指標を計算できます。
これらの指標は、企業の収益性や資産活用効率を評価するための重要なツールとなります。
例えば、損益計算書で示された当期純利益を貸借対照表の自己資本で割るとROEが計算でき、企業の自己資本がいかに効率的に利益を生み出しているのかを評価できます。
- あわせて読みたい
貸借対照表の分析におけるポイントや注意点

経営者が経営の改善を図る際や投資家が企業の経営状況を正しく把握する上では、貸借対照表の各項目を活用した分析が欠かせません。
そこでこの章では貸借対照表の代表的なチェックポイントと、それを用いた分析手法や計算方法について解説します。
流動資産・流動負債
貸借対照表を確認すれば、企業の資金繰りが円滑に行われているかを分析できます。特に、短期的な資金繰りを把握する際には、貸借対照表内の「流動資産」と「流動負債」への注目が重要です。
- 流動資産:営業活動によって発生した資産や、1年以内に現金化される資産
- 流動負債:1年以内に返済が必要な負債
これらは短期間で現金が動く項目であるため、両者を比較すれば、資金繰りに問題がないかを確認できます。
基本的に「流動資産 > 流動負債」であれば、当面の資金繰りに大きな問題はないと判断できます。
流動比率・当座比率
企業の支払い能力を分析する際には、「流動比率」や「当座比率」を活用します。
流動比率は流動資産と流動負債の割合を示し、以下の計算式で求められます。
流動比率(%) = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
流動比率が高いほど、流動負債の支払い能力が高いと考えられます。一般的には、流動比率が100%以上であれば短期的な資金繰りは安定していると評価されます。
ただし流動資産には現金化が遅れる可能性のある資産も含まれるため、高ければ高いほど返済リスクが軽減されると言えます。
当座比率は、流動資産の中でも特に換金性の高い「当座資産」を用いて算出します。
当座比率(%) = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100
当座資産には現金や預金など流動性の高い資産が含まれ、棚卸資産などの換金性の低い資産は除かれます。
当座比率は流動比率よりも厳密に支払能力を判断する指標となります。
自己資本比率
「自己資本比率」は、負債と純資産の合計である総資本に対する自己資本の割合を示します。
式は以下の通りです。
自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資本 × 100
自己資本比率が高いほど、企業が負債に依存しておらず、財務の健全性が高いと考えられます。反対に、自己資本比率が低い場合、負債の割合が高くなり、倒産リスクが高まる可能性があります。
自己資本利益率
「自己資本利益率」とは、自己資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。
式は以下の通りです。
自己資本利益率(%) = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
この指標は株主にとって重要な評価ポイントの一つであり、出資した資金をどれだけ効率的に運用して利益を上げているかを測るものです。
自己資本利益率が高いほど、企業が収益性に優れていると判断されます。
負債比率
「負債比率」は、自己資本と比較した負債の割合を示します。
式は以下の通りです。
負債比率(%) = 負債 ÷ 自己資本 × 100
負債比率が低いほど財務の安全性が高いとされますが、業種によって適正な比率は異なるため、単純に小さいほど良いというわけではありません。
負債比率が小さい企業は安全性が高い一方で、積極的な事業展開に欠けている可能性もあります。
このように貸借対照表を正しく理解し、各指標を適切に分析すれば、経営改善や投資判断に役立てられます。
まとめ

ここまで貸借対照表について解説してきました。
貸借対照表の作成は、企業の財務状況を正確に反映させるために非常に重要な作業ですが、その作成には専門的な知識と時間が求められます。特に、複雑な取引や税務処理を伴う場合、誤った処理が企業の信頼性を損なうリスクもあります。
このような背景から、会計アウトソーシングの活用が非常に有効です。
専門家によるサポートを受ければ、正確かつ迅速に貸借対照表を作成し、経営者は本業に集中できる環境を整えられます。さらに、アウトソーシングを利用すれば、コスト削減や効率化が図れ、企業の成長に寄与するでしょう。
今回の記事が皆様の貸借対照表に関する理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
経理BPOならBPIOにお任せください
株式会社BPIOが展開する「BPIO」は、バックオフィス業務を3つの軸で改善するBPOサービスです。

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
RANKING
お役立ち情報
CASE