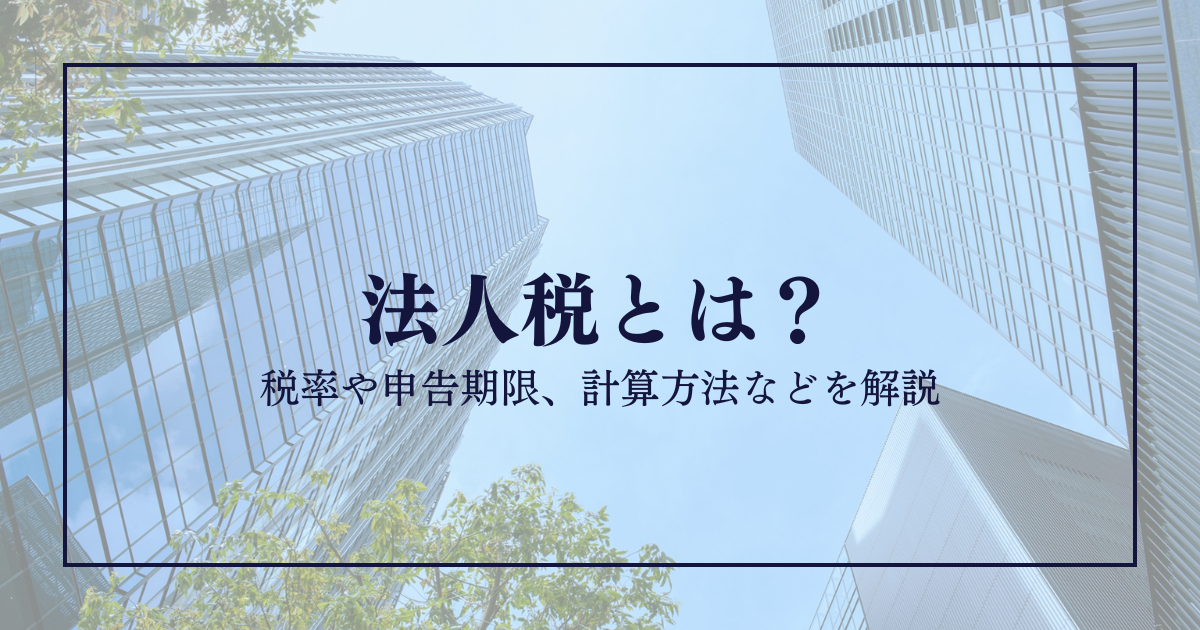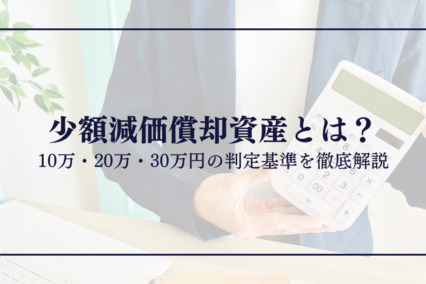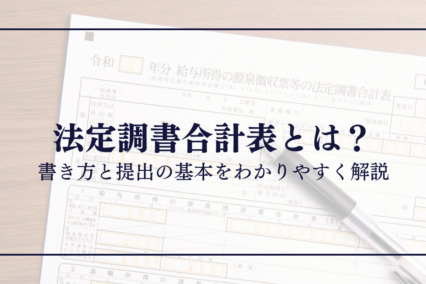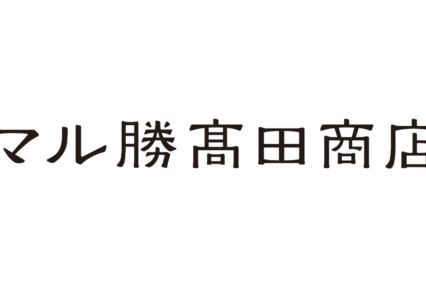法人が支払う税金の中で最も代表的なのが法人税です。法人は事業で得た所得をもとにして納付すべき法人税額を計算し、その後、税務署に申告して納付しなければなりません。それでは、法人税額はどのように計算すればよいのでしょうか?
本記事では、法人税の計算方法、申告手続き、納付時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
法人税とは企業の利益に課される税金

法人税は、法人全体の所得に課される税金です。法人税における重要なポイントは、それが「利益」に対する税金ではないということです。
通常の企業会計では「収益―費用=利益」と計算しますが、税務会計では「益金―損金=所得」として考えます。費用と損金の取り扱いには違いがあり、この点を理解しておくことが法人税を正しく理解するためには重要です。
例えば、役員報酬や交際費などは損金として認められないケースもあります。費用と損金の扱いが異なるため、結果として利益と所得の金額も異なります。
法人税率は基本的には23.2%で、法人税は「所得×23.2%」で計算されます。黒字の場合、法人税を支払う必要がありますが、所得が赤字の場合は法人税を支払う必要はありません。
法人税の対象となる法人の種類

法人税を納める義務のある法人は、法人税法によって内国法人と外国法人に分類されます。
内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を持つ法人を指し、外国法人は内国法人以外の法人を指します。内国法人は以下のように区分され、それぞれの法人の区分に基づいて納税義務などが定められています。
法人税法における内国法人の区分
- 公共法人:公共的性格を持つ法人。地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫、日本放送協会など
- 公益法人等:公益を目的とする事業を行う法人等。社会医療法人・学校法人・公益社団(財団)法人・宗教法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・認可地縁団体など
- 人格のない社団等:法人でない社団または財団で、代表者または管理人が定められているもの。PTA、同窓会、同業者団体など
- 協同組合等:組合員の相互扶助を目的とする法人。農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など
- 普通法人:上記以外の法人。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人(社会医療法人を除く)など
- あわせて読みたい
法人税の課税期間と申告期限

法人税の申告方法には、確定申告と中間申告があります。
法人税は通常、事業年度の終了時に確定申告を行い、税額を申告して納付します。一方、中間申告は、事業年度の途中で前払いとして半年分の税額を納付し、年度末の本決算時に残りの税額を納付する方式です。
ここでは、確定申告および中間申告それぞれの納付期限について説明します。法人税の確定申告と納付は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に実施する必要があります。例えば、事業年度の終了日が3月31日の場合、申告・納付期限は5月31日となります。ただし、納付期限が土曜・日曜または祝日と重なる場合、翌営業日が期限になります。
中間申告とは
法人税の中間申告とは、事業年度の途中で法人税の申告と納付を行うことを義務付けた制度です。
法人税を事業年度の途中で申告・納付するのには、法人の資金繰りを考慮した理由があります。
法人は個人事業主と比べて納税額が大きくなる傾向があるため、一度に多額の納税が発生すると資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。そのため、事業年度の途中で申告・納付を行う中間申告制度が導入されました。
中間申告を行うことで、納税額を分割して支払うことができ、資金繰りの負担を軽減するメリットがあります。
法人税の税率と計算方法
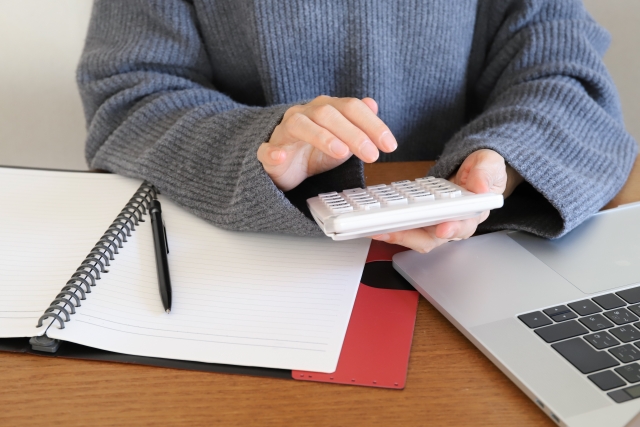
法人税の計算手順は、大きく3つのステップに分けられます。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
課税所得の計算
法人税を算出する際、最初に課税所得を求めます。先述の通り、課税所得とは会計上の利益ではなく、税法上の所得金額を指し、「益金-損金」の計算によって導き出されます。
「益金」には、製品の売上収入や不動産売却による収入などが含まれます。一方、「損金」には売上原価や販売費などの費用が該当し、いずれも調整が必要になる場合があります。
加算調整には、例えば役員報酬や寄付金などの損金不算入項目があります。また、減算調整には、税金の還付金や保有資産の評価益など、益金不算入となるものが含まれます。
法人税率の確認
課税所得を算出した後、適用される法人税率を確認します。法人の種類や規模により税率は異なります。例えば、普通法人で資本金が1億円を超える場合、法人税率は23.2%です。
協同組合等の法人は、普通法人より税率が低めに設定されており、所得金額が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は19%となっています。
中小企業には法人税の軽減措置があり、資本金1億円以下などの一定条件を満たす場合に適用されるため、どの税率が適用されるか事前に確認が必要です。
なお所得に対する法人の税金を考える際には法人税以外にも地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税などもかかるので実効税率を考慮すると良いでしょう。
実効税率とは法人が所得に対して実際に負担する所得に対する税の割合を示すもので、法人事業税・特別法人事業税が法人税法上損金として扱われる影響を考慮した上で算出した税率のことです。
実効税率は法人税率より高くなり約30%程度であると考えられます。
法人税額の計算
法人税額は、以下の計算式で求められます。なお、法人税法に基づき、1円未満の端数は切り捨てとなります。
- 法人税額 = 課税所得 × 税率
法人税の納付方法

法人税は、定められた期間内に申告書と必要な添付書類を所轄の税務署に提出して申告します。納付方法はクレジットカード納付・現金納付・ダイレクト納付・インターネット納付の4種類から選ぶことができ、それぞれについて詳細に説明します。
クレジットカードでの納付
「国税クレジットカードお支払サイト(外部サイトに移動します)」を通じて、クレジットカードで納付することが可能です。ただし、決済手数料が発生するなど、利用に際しての注意点があるため、納付前にウェブサイトに記載された情報をしっかり確認することをお勧めします。
現金での納付
金融機関や所轄の税務署の窓口で納付する場合、現金での納付が可能です。税務署から送付された納付書や国税庁のWebサイトにて作成可能な専用の二次元コードをコンビニに持参すれば、現金で支払いができます。ただし、二次元コードを利用した納付は、納税額が30万円までとなるため、注意が必要です。
ダイレクト納付の仕組み
ダイレクト納付は、e-Taxで申告書などを提出し、納税者本人名義の預貯金口座から納付金額を引き落とす方式です。事前にe-Taxの利用開始手続きを行い、税務署や金融機関に専用届出書を提出する必要があります。
インターネットバンキングでの納税
e-Taxの利用開始手続きを完了していれば、インターネットバンキングを通じて納付が可能です。法人税の納付期限は原則として、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」となっています。
まとめ

ここまで法人税について解説してきました。
法人税の申告の元となる決算書の作成は、単なる事務作業にとどまらず、企業にとって非常に重要で複雑な業務です。
会計基準の改訂などが頻繁にあるため、専門知識を持たないと適切に対応できない場合があります。これらの業務を社内で対応するのは、時間やリソースが限られている中で非常に負担が大きいです。
そこで、会計アウトソーシングを利用することを強くお勧めします。外部の専門家に業務を委託することで、最新の会計基準に基づいた正確な決算書の作成が可能になります。企業にとっては大きな安心材料となります。
また、会計アウトソーシングを利用することで、社内のスタッフは本業に集中できるようになり、経営資源を効率的に活用することができます。業務の専門化により、内部の作業負担を軽減し、コスト削減にもつながります。
さらに、決算書作成のプロセスがスムーズに進むことで、経営判断のための財務情報が迅速かつ正確に手に入るため、経営の意思決定をサポートする重要な役割も果たします。結果として、長期的な企業の成長に寄与することができるのです。
会計アウトソーシングは現代の企業運営において非常に有効な手段と言えるでしょう。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
RANKING
お役立ち情報
CASE