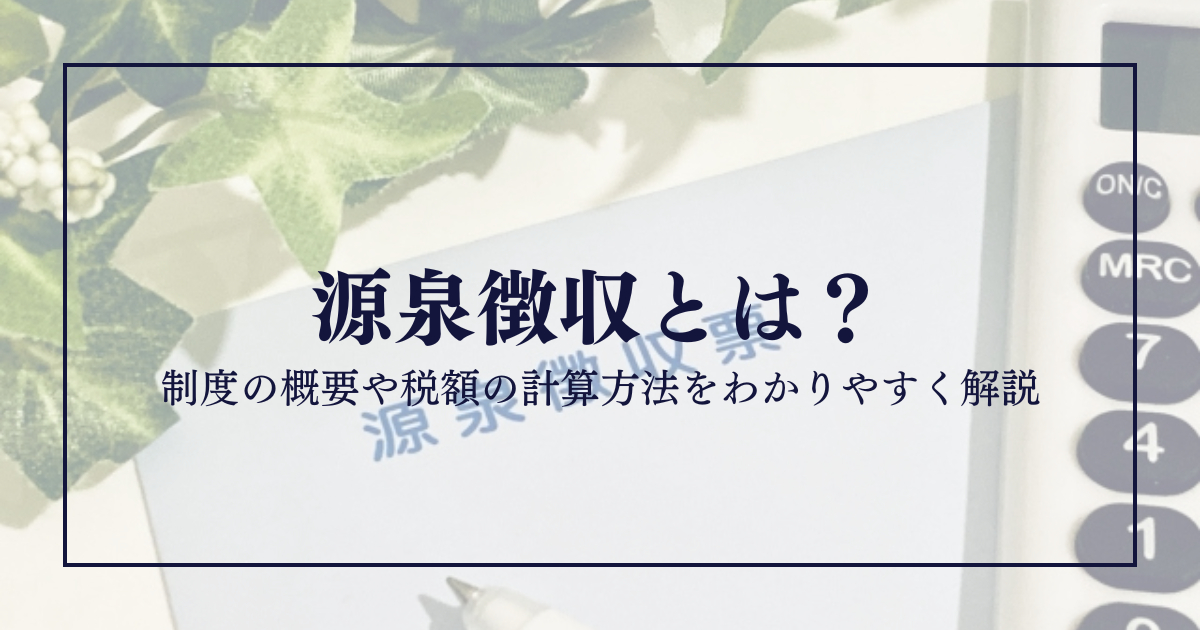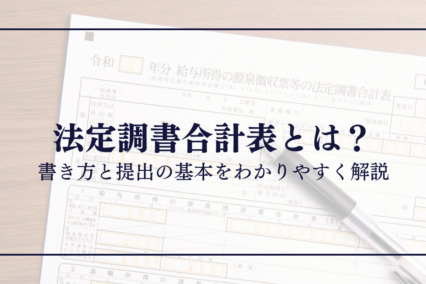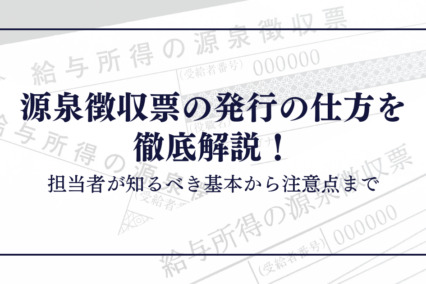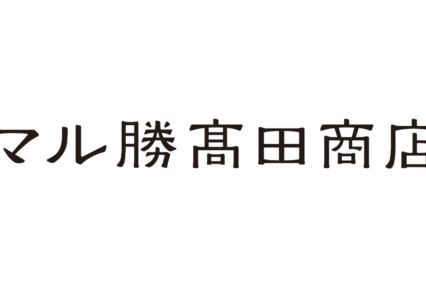源泉徴収の基本
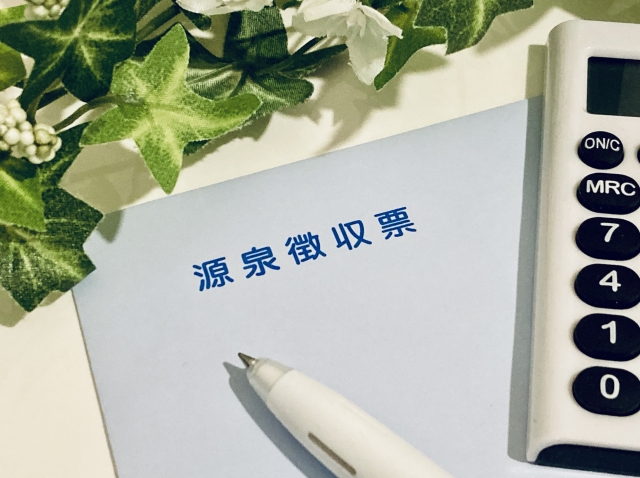
「源泉徴収」とは、給与や賞与から税金や保険料を差し引き、会社が従業員に代わって納税する制度のことを指します。
毎月の給与から差し引かれた所得税の合計額と、年間で本来支払うべき所得税額との差を調整する仕組みが「年末調整」です。
会社員の場合、年末調整は勤務先が行いますが、個人事業主は自ら税額を計算し、納付すべき金額を申告します。この手続きを「確定申告」といいます。
源泉徴収の対象となる範囲
会社が源泉徴収する対象には、以下の4つの項目があります。
- 給与・賞与
- 退職金
- 支払報酬
- 支払配当金
担当する業務によって関わる範囲は異なるかもしれませんが、人事部門であれば、給与・賞与や退職金にかかる源泉所得税の処理に深く関与しているでしょう。
経理部門の支払業務に携わっている場合、税理士・行政書士などの士業への報酬や、会社の講演・司会の報酬を支払う際に、源泉所得税を計算し、報酬額から控除して支払う業務を行っているかもしれません。
また、総務部門では、株主への配当金を支払う際に、源泉所得税を差し引いて支払う業務に関わることがあるでしょう。
源泉徴収票の対象期間
源泉徴収の対象期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。この期間内に支払われた給与が、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収は勤務した時期ではなく、給与が支払われたタイミングにより行われます。つまり、「いつ働いたか」ではなく、「いつ給与が支払われたか」が基準となります。
会社の給与制度で月末締めの翌月払いなどの方式が採用されているケースもあります。例えば12月分の給与が翌年1月に支払われる場合もあります。
このように12月分の給与が翌年に支払われたケースでは、その給与は翌年の源泉徴収の対象となって、当年の源泉徴収票には含まれません。
源泉所得税と年末調整
事業者は、1年間の給与総額が確定した時点で、各従業員に対する正確な所得税額を算出します。もし過剰に徴収していた場合は従業員に還付し、逆に不足していれば追加で徴収を行います。この一連の手続きを年末調整と呼びます。
源泉所得税はあくまで概算であり、年間の正確な所得税額は、1月から12月までの給与支給額が確定しない限り明確にはなりません。そのため、従業員の給与や賞与から差し引いた源泉所得税については、年末調整を通じて最終的な調整を行う必要があります。
一方で、報酬や料金に対する源泉所得税については、事業者が年末調整を行う必要はありません。この場合、源泉所得税と実際の納税額との調整は、報酬や料金を受け取った本人が確定申告で行うことになります。
源泉徴収税について

報酬・料金等にかかる源泉徴収税額の計算方法
報酬や料金に対する源泉徴収税は、1回の支払い額が100万円以下の場合と、100万円を超える場合で計算方法が異なります。
1回の報酬が100万円以下の場合
報酬が1回あたり100万円以下の場合、源泉徴収税額は所得税と復興所得税とで10.21%の税率を適用して計算します。計算式は次の通りです。
源泉徴収税額 = 報酬金額(税込) × 10.21%
基本的に、計算に使う報酬額は消費税込みの金額ですが、報酬額と消費税額が明確に区別されている場合、消費税分を除いた金額で計算しても問題ありません。
例えば、50万円(税込)の報酬の場合、計算式は以下のようになります。
50万円 × 10.21% = 51,050円(源泉徴収税額)
1回の報酬が100万円を超える場合
報酬が100万円を超える場合、税率が異なります。100万円以下の部分には10.21%を適用し、100万円を超える部分には20.42%を適用します。計算式は以下の通りです。
源泉徴収税額 =(報酬金額(税込) – 100万円) × 20.42% + 102,100円
例えば、200万円(税込)の報酬の場合、計算は次のようになります。
(200万円 – 100万円) × 20.42% + 102,100円 = 306,300円(源泉徴収税額)
給与所得・賞与にかかる源泉徴収税額の計算方法
従業員に支払う給与・賞与・退職金にかかる源泉徴収税額は、毎年国税庁が公表する「源泉徴収税額表」に基づいて算出されます。
税額は、給与の支払い方法(日払い・月払いなど)、社会保険料控除後の支給額、扶養親族の人数などによって異なり、細かく分類されています。そのため、従業員ごとに税額表を参照して確認する必要があります。
退職金にかかる源泉徴収税額の計算方法
退職金にかかる所得税は、基本的に他の所得と分けて計算されます。退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、勤務先が所得税および復興特別所得税を計算して源泉徴収してくれます。そのため、通常は確定申告を行う必要はありません。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、勤務先は退職金の支払額の20.42%を所得税および復興特別所得税として源泉徴収する必要があります。もし年間の所得を集計した結果、退職所得に対する源泉徴収額が多すぎると判明した場合、確定申告を行い、過剰に徴収された所得税および復興特別所得税の精算を行うことができます。
源泉徴収された所得税・復興特別所得税の納付方法

源泉徴収した所得税は、原則として、対象となる給与・報酬などを支払った月の翌月の10日迄に、税務署に納付する必要があります。例えば4月支払いの給与から源泉徴収した所得税については5月10日までに納付する必要があります。注意すべき点は、「何月分の給与か」ではなく、「実際に支払った月」で納付期限が決まるということです。
さらに、給与(役員報酬を含む)を支払う人数が常時10人未満の会社においては、源泉所得税を半年ごとにまとめて納付する特例が適用されます。この特例を使うと、1月から6月の源泉所得税は7月10日、7月から12月の源泉所得税は翌年1月20日が納付期限となります。
納期の特例を利用するためには、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」をe-Taxで提出するか、所轄税務署に直接提出する必要があります。申請書を提出した月の翌月から、特例が適用されます。
納付期限について
源泉所得税には納付期限が定められています。原則として、給与・報酬などを支払った月の翌月10日迄に、国へ納付する必要があります。
しかし、給与の支給対象者が常時10人未満の事業者には特例があり、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を半年ごとにまとめて納付できます。この特例を適用すると、1月から6月に源泉徴収した税額の納付期限は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日となります。
なお、納付が遅れた場合は、不納付加算税が課される可能性があるため注意が必要です。原則として税額の10%が課されますが、税務署の指摘を受ける前に自主的に納付すれば5%に軽減されます。
納税地の確認
源泉徴収税の納税地は、給与や報酬の支払いが行われた場所、つまり支払いを行った会社や事務所を所轄する税務署となります。
例えば、東京都荒川区の事務所で働いている神奈川県在住の従業員に給与を支払った場合、支払いが行われた場所である東京都荒川区の税務署に納税することになります。なお、会社や事務所を移転した場合、その新しい住所を管轄する税務署が納税地となります。
- あわせて読みたい
まとめ

ここまで源泉徴収について解説してきました。源泉徴収の管理には正確な会計処理が必要ですが、そのためには会計アウトソーシングのご利用がおすすめです。
企業の成長と安定的な運営を支えるためには、正確で迅速な会計処理が欠かせません。しかし、日々の会計業務に多くの時間やリソースを割くことは、経営者にとって大きな負担となります。
そこで、会計アウトソーシングを活用することで、専門的な知識と最新の技術を駆使したプロフェッショナルによる会計業務を任せることができます。アウトソーシングを導入する主な利点は以下の通りです。
内部で会計部門を構える場合、人件費や教育コストがかかります。アウトソーシングを利用することで、固定費を変動費に切り替え、コストを効率的に管理できます。また会計の専門家によるサービス提供が可能になり、税務や法令に対する最新の知識と対応が期待できます。これにより、会計業務の精度が向上し、法的リスクの軽減にも繋がります。
煩雑な会計業務をアウトソーシングすることで、貴社の社員がコア業務に集中でき、全体的な生産性向上に繋がります。事業の成長や変化に合わせた柔軟なサービス提供が可能で、規模に応じて最適な会計処理を行います。
会計アウトソーシングを利用することで、貴社の業務がよりスムーズになり、経営の意思決定に集中できるようになります。経営資源を効率的に活用し、競争力を強化したい企業にとって、導入を検討していただきたいサービスです。
会計の正しい入力を経て、税務に関するご質問などは税理士にご相談ください。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
RANKING
お役立ち情報
CASE