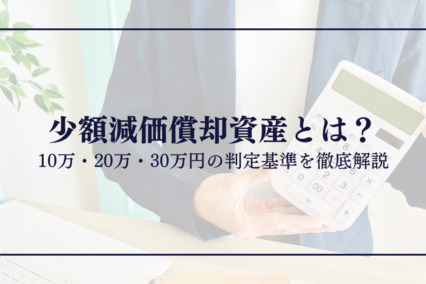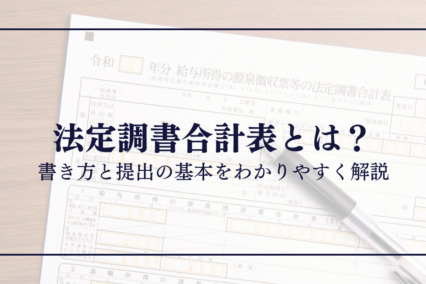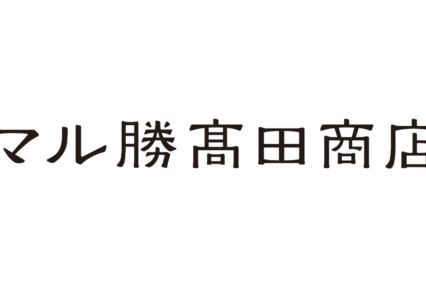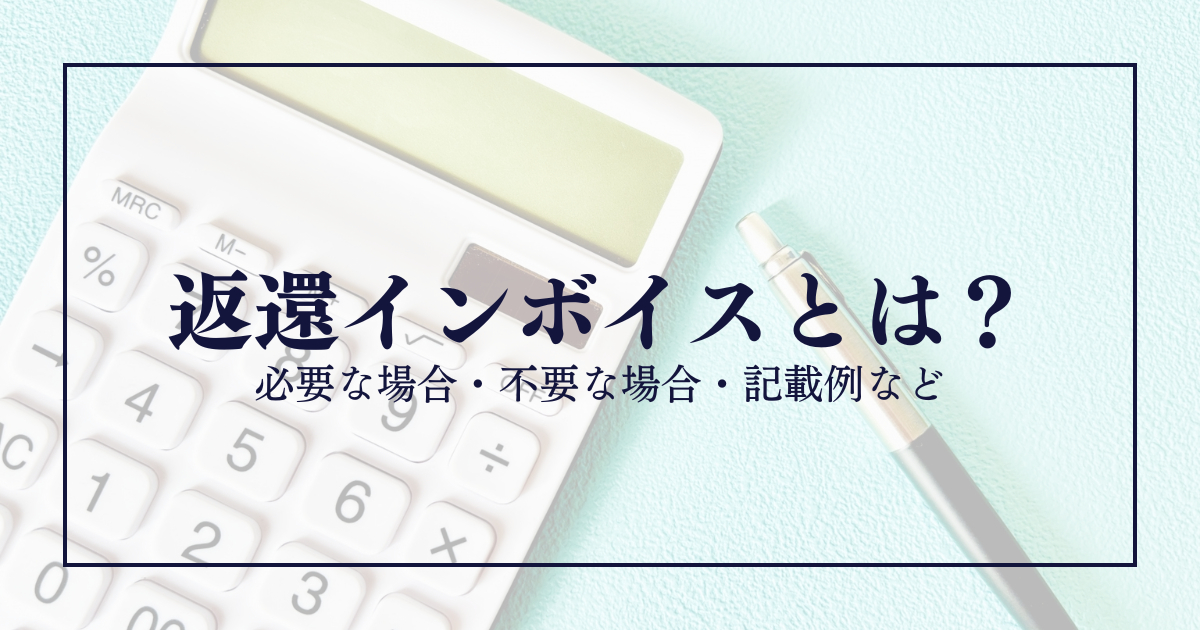
2023年10月のインボイス制度開始以降、通常のインボイス(適格請求書)だけでなく、「返還インボイス(適格返還請求書)」の発行が必要となるケースも存在します。国内の課税取引で値引きや返品が発生した際に発行が義務付けられている書類です。
この記事では、返還インボイスの役割、発行が必要な状況、記載すべき項目などについて、分かりやすく解説します。
迅速かつ正確な対応を進めるために、ぜひお役立てください。
返還インボイスとは?

返還インボイスとは、売り手が買い手に対し、商品やサービスの返品、値引き、または割戻しなどで、既に受け取った金額の一部または全額を返還する際に発行する書類のことです。
取引の透明性と正確な税額管理が求められるため、売り手側に返品や値引き、リベートの支払いといったケースで発行が義務づけられています。
返還インボイスの発行が必要な事業者
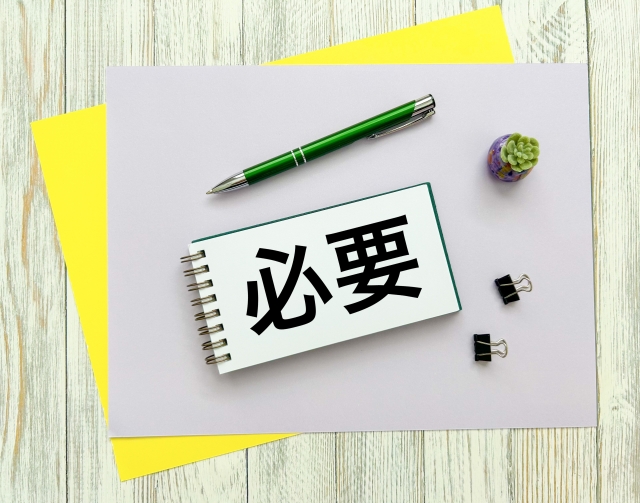
返還インボイスの作成は、すべての事業者に義務付けられているわけではありません。この書類を発行できるのは、一定の条件を満たした事業者に限られます。以下に、対象となる要件を解説します。
1.適格請求書発行事業者に登録済みであること
返還インボイスを正しく発行するには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要です。この登録は所轄の税務署に申請して行い、登録が完了すると専用の登録番号が発行されます。発行する書類にはこの登録番号の記載が求められます。
2.売上の内容に訂正や変更があった場合に限られる
通常の取引に対して発行するものではなく、取引内容に見直しが生じた場合に限って発行が必要となります。たとえば、商品が返品された場合、値引きが適用された場合、あるいは販売奨励金(割戻し)が発生した場合など、元の取引内容に修正が生じたときに活用されます。
返還インボイスの発行が不要となるケースとは

交付が不要となるケースには、例えば以下のようなものがあります。
少額取引の場合
税込み金額が1万円未満の返品や値引きによる売上の返還については、原則として免除されます。
公共交通機関の利用時
船舶、バス、鉄道などの旅客運送においては支払額が3万円未満の場合は適格請求書の交付が不要です。たとえ返金があったとしても適格請求書の発行がもともと免除されている取引については、返還インボイスの発行も不要です。
卸売市場での販売時
生鮮食料品などを卸売業務として出荷者から委託を受けて販売する場合で適格請求書の発行が免除されている取引については、返還インボイスの発行も不要です。
条件次第で、適格請求書と適格返還請求書を一体化して作成可能

適格請求書と適格返還請求書は、本来別々に発行するものですが、一定の条件を満たせば、1枚の書類としてまとめて発行することが可能です。ただし、その際は、それぞれの書類に必要とされる記載事項をすべて漏れなく含める必要があります。
たとえば、取引先に対して前月分の売上実績に応じたリベートを支払っているケースでは、当月の販売に関する適格請求書の要件と、リベートにかかる適格返還請求書の要件の双方を記載する必要があります。
また、各取引先との継続的な契約関係があることを前提とすれば、たとえば「当月の販売金額」から「前月のリベート分」を差し引いた金額(差額)を記載し、それに基づく消費税額をあわせて記載することで、請求書としての形式を整えることも可能です。
このようにすれば、ひとつの請求書の中で、課税売上とその返還分の両方を反映できます。
返還インボイスのひな形を用いた作成方法・記載例
ひな形を用いて作成することも想定されます。ひな形を活用することは、書類作成の手間を軽減し、正確な記録を効率よく行うための有効な手段です。
なお一般的にひな形とは、請求書や領収書、振込依頼書など、よく使われる経理関係の書類ごとに必要事項や書式があらかじめ整えられている書式のことを指します。これを使うことで、手書きやエクセルで一から作成するよりも作業時間を短縮でき、記入ミスの防止にもつながります。ひな形を使用する際には、会社としてのルールや形式に合わせた調整を行う必要もある点には注意が必要です。
国税庁のHPには記載例が掲載されています。その一部を以下に引用します。
引用:国税庁HP
返還インボイスの相殺処理を行う際の注意点

基本的に、相殺処理を行う場合でも行わない場合でも、売上に返品や値引きが発生した際には、返還インボイスの発行が求められます。
相殺処理をする際は、インボイスと返還インボイスを一つの書類にまとめるか、もしくは両方を同時に取引先に送付して、相殺が行われたことが相手に明確に伝わるようにしましょう。
相殺処理は基本的に売掛金と相殺されるため、現金のやり取りは発生しません。会計処理を漏れなく行うことが重要です。
適格返還請求書を発行する際のポイント

発行にあたっては、いくつか押さえておくべき重要な点があります。以下に、注意すべき項目とその具体的な内容をまとめました。
ポイント1.発行の責任は売り手側にある
適格返還請求書の交付義務は、取引の買い手ではなく売り手側に課されています。ただし、この書類の発行義務があるのは、
取引当事者である双方(売り手と買い手)が課税事業者であり、かつ、売り手が「適格請求書発行事業者」として登録されている場合です。
免税事業者や未登録の事業者には、適格返還請求書の発行は認められていません。
そのため、もしインボイス制度に則って請求書のやり取りを行いたい場合は、事前に「適格請求書発行事業者」として登録申請を済ませる必要があります。登録は、所定の申請書をインボイス登録センター宛に郵送することで行えます。
ポイント2.事前の体制整備がカギになる
適格返還請求書は、返品や値引きの際だけでなく、リベートや販売奨励金などを支払う場面でも必要になるため、突発的な対応では間に合わないこともあります。そこで、次のような準備を進めておくと安心です。
- フォーマットをあらかじめ設計しておく
- 発行手順(フロー)を社内で整備しておく
- 専用の発行システムを導入し、作業の効率化を図る
特にシステムを活用すれば、運用面での負担が大幅に軽減され、発行ミスも防止しやすくなります。フォーマットの設計やフロー構築にあたっては、デザインの統一や担当者の明確化などもあわせて検討しておくと、よりスムーズに対応できるでしょう。
まとめ

近年導入されたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるための要件として、適格請求書の保存が義務づけられるなど、これまで以上に正確な記録管理が求められる制度です。
その中でも「返還インボイス(返還請求書)」は、返品・値引き・契約解除といったケースにおいて、通常の請求書とは異なる特別な形式での対応が必要となるため、制度の理解や実務上の注意点が一層重要になります。
こうした業務は、制度そのものがまだ新しく、会計や税務の専門知識がなければ戸惑いやすい分野でもあります。
そのため不明点がある場合や、処理に不安がある場合は、会計業務を専門とするアウトソーシングサービスの活用を強くおすすめします。
会計アウトソーシングを利用することで、制度に精通した専門家のサポートを受けながら、正確かつ効率的に対応を進めることができ、取引先との信頼関係を損なうことなく業務を遂行できます。
さらに、社内での担当者の負担軽減や人的リソースの最適化といった面でも、アウトソーシングは非常に効果的です。専門スタッフに任せることで、返還インボイスに関する煩雑な手続きや記帳・保存管理をスムーズに行うことができ、本業に集中できる時間を確保できます。
特に、人手が限られている中小企業や個人事業主にとっては、限られたリソースを有効に使うための選択肢として、大きなメリットがあります。
法令対応の確実性を高めると同時に、業務全体の効率化を図るうえでも、会計アウトソーシングは非常に心強い存在です。インボイス制度への対応に少しでも不安を感じている方は、ぜひ一度、専門サービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
経理BPOならBPIOにお任せください

経理・労務・総務等のバックオフィス業務の代行だけでなく、業務設計やDX支援など幅広く業務を支援します。
業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
RANKING
お役立ち情報
CASE