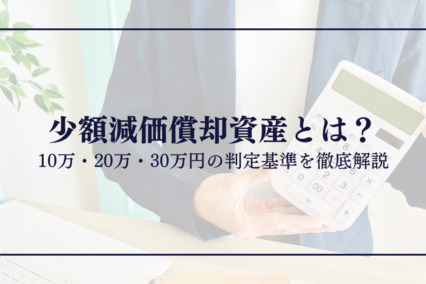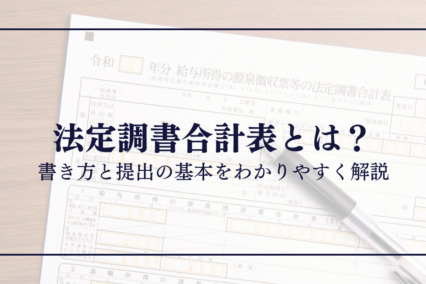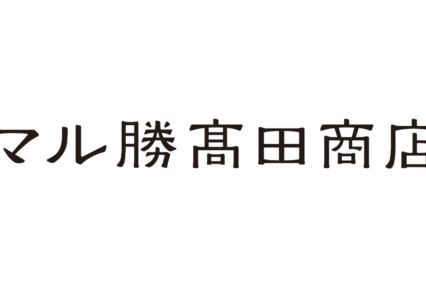2022年1月の改正電子帳簿保存法により、電子取引データの電子保存の義務化がなされました。2年間の猶予期間を経て、2024年1月以降は電子メールやクラウドサービスなどを介して請求書などを授受した場合、電子形式での保存が必須となります。
これらの電子取引データを保存する際は、電子帳簿保存法が定める保存要件に従う必要があります。この保存要件には「真実性の確保」が求められており、これを実現する方法の一つに「タイムスタンプ」の利用があります。
今回の法改正では、このタイムスタンプに関する要件も緩和されました。
そこでこの記事では電子帳簿保存法が求めるタイムスタンプの仕組みや利用方法、そして法改正による要件の緩和について、分かりやすく解説します。
タイムスタンプの基本を理解する

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿の電子データ保存を認める法律として1998年(平成10年)に制定されました。これまでに何度か改正され、保存対象となる国税関係帳簿書類や保存要件が緩和されてきました。
特に2022年(令和4年)1月の改正では、「真実性」確保のためのタイムスタンプ付与要件が緩和されています。
そもそもタイムスタンプとは、紙の書類と比べて複製や改ざんが容易な電子データが「原本であること」を保証するための仕組みで、以下の点を証明する技術です。
タイムスタンプは、「タイムスタンプ局」という時刻認証事業者からサービスとして提供されています。
タイムスタンプ局が電子データに付与する時刻は、上位の時刻配信局による監査を受けており、国家時刻標準機関まで追跡可能な正確な時刻です。この仕組みにより、タイムスタンプ局以外が勝手にタイムスタンプを生成することはできません。
タイムスタンプを導入するにはどうすればいい?

タイムスタンプの仕組みを活用するにはいくつかの準備が必要です。導入にはコストがかかりますが、電子帳簿保存法に基づき電子データを適切に保管するために不可欠な技術です。
インターネット環境の整備
インターネット上でタイムスタンプを付与するためには、安定したインターネット環境が欠かせません。
もしインターネット環境が整っていないと、タイムスタンプだけでなく、電子帳簿保存法に対応したソフトウェア、クラウドサービス、経費精算システムなども利用できない可能性があります。
時刻認証業務認定事業者との契約
データの信頼性を確保するためには、時刻認証業務認定事業者と契約し、タイムスタンプを取得できる環境を整える必要があります。
時刻認証業務認定事業者とは、一般財団法人日本データ通信協会の認定を受けた事業者のことです。直接契約を結ぶこともできますが、多くの場合ベンダーを介して、タイムスタンプ機能が組み込まれたシステムを利用するのが一般的です。
タイムスタンプ付与システムの導入
書類にタイムスタンプを付与できるシステムを導入します。単に付与できるだけでなく、電子帳簿保存法に対応しているシステムやソフトウェアを選ぶのが望ましいでしょう。
電子帳簿保存法に対応しているシステムには、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)から認証を受けていることを示すマークが記載されています。
例えばバクラクやマネーフォワードといった導入実績の多いツールは、拡張機能や使いやすい傾向にあるためおすすめです。
タイムスタンプが必要な保存形式とは?
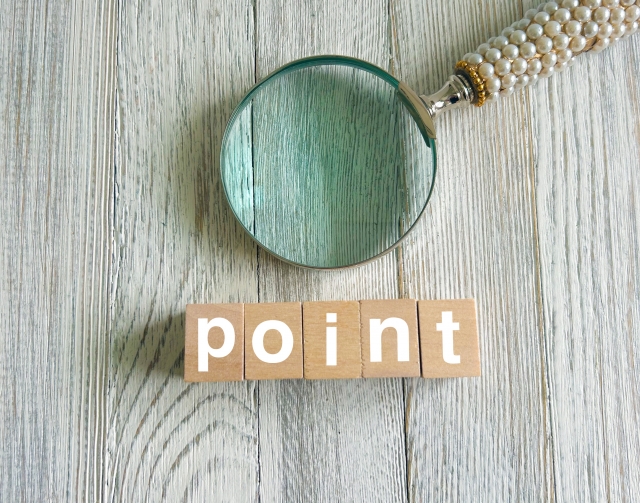
現在タイムスタンプが必要となる保存形式は、「スキャナ保存」と「電子取引」の2つに絞られています。この章ではタイムスタンプが必要となるこれら2つの保存形式について、詳しく解説します。
スキャナ保存
タイムスタンプが必要な保存形式の一つがスキャナ保存です。これは、途中で手書きの記載があるなど、一貫して電子的に作成されていない自社発行書類の控えや、紙で受け取った請求書などの国税関係書類が対象となります。
請求書や納品書など、お金の動きを証明する重要書類の場合は、最長2ヶ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプを付与しなければなりません。一方、見積書や注文書など、まだ取引が確定していない段階の一般書類については、適宜の付与が認められています。
電子取引
電子取引もタイムスタンプが必要となる保存形式です。これは、電子データとして送受信した国税関係書類が対象です。電子取引では、タイムスタンプの付与は必須要件ではないものの、選択要件の一つとなっています。
電子取引を行う際には、以下のいずれかの措置を講じることが定められています。
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取っている
- タイムスタンプのない書類を受け取った場合、すぐにタイムスタンプを付与している
- 訂正・削除の履歴が残るシステムを利用している
- 電子取引データの訂正・削除の防止に関する事務処理規程を策定し、運用している
電子帳簿保存法の改正でタイムスタンプが不要に

2022年の電子帳簿保存法の改正によってスキャナ保存の際、特定の条件を満たせばタイムスタンプの付与が免除されるようになりました。
この条件とは、簡単に言えば「電子データの訂正・削除の履歴が残るか訂正や削除ができないシステムを利用すること」です。
電子取引の保存においても、訂正削除履歴が残る、または訂正削除ができないシステムを利用するか、訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備することで、タイムスタンプは不要となります。
この改正により、事実上、タイムスタンプなしで電子帳簿保存法に対応できるようになったと言えるでしょう。
ただし、タイムスタンプなしでの運用は非効率になるケースもあります。
タイムスタンプ導入にかかるコスト

タイムスタンプの導入には、初期費用や利用頻度に応じた費用が発生します。ここでは、これらのコストについて詳しく見ていきましょう。
初期費用
タイムスタンプシステムの初期費用は、製品によって大きく異なります。初期費用が不要で月額料金のみで利用できるものもあれば、既存のシステムに組み込んで使用するタイプもあります。
システムの設計から導入まで行う場合、初期費用として数十万円程度かかることもあります。
利用ごとの費用
また通常の費用としては、タイムスタンプごとに発生する従量料金制度を採用しているサービスもあります。
これより実際の利用料に関して高額になってくるサービスもありますが、その多くは会計ソフトとの連携など、より高い利便性を提供していることが多いです。また、従量課金ではなく、月額固定料金で発行回数に上限が設けられているプランもあります。
定着までの人件費
タイムスタンプという新たなサービスを導入する際、業務に定着するまでには、一時的に人件費が余分にかかる可能性があります。
タイムスタンプについて理解し、操作に慣れるまでは、発行作業に時間がかかることも珍しくありません。しかし、一度定着してしまえば、ほとんどの場合で人件費の削減が見込めるでしょう。
まとめ

ここまでタイムスタンプについて解説してきました。タイムスタンプの取り扱いについてご不明点がある場合など会計業務について不安があるケースについては経理アウトソーシングをご利用されるのがおすすめです。
会社の規模が拡大し、従業員が増えるにつれて、経費計算の業務量は増加し、担当者の負担も大きくなります。また、法改正への対応も求められるため、担当者は常に最新情報を把握し、広範な業務をこなす必要があります。
経理業務を外部委託(アウトソーシング)することで、担当者の人件費だけでなく、パソコンやソフトウェアなどの作業環境を整備するコストも削減できます。経理業務のアウトソーシングを検討する際は、自社の規模に合ったサービスを選ぶようにしましょう。
ぜひご利用をご検討ください。
経理BPOならBPIOにお任せください

経理・労務・総務等のバックオフィス業務の代行だけでなく、業務設計やDX支援など幅広く業務を支援します。
業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
RANKING
お役立ち情報
CASE