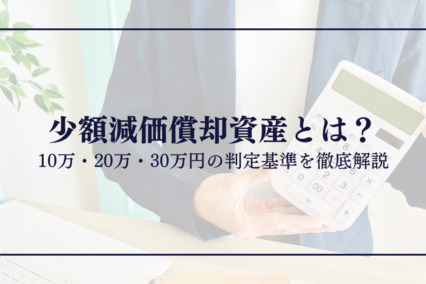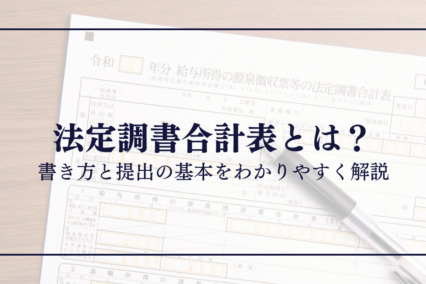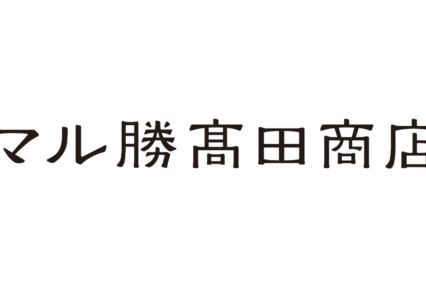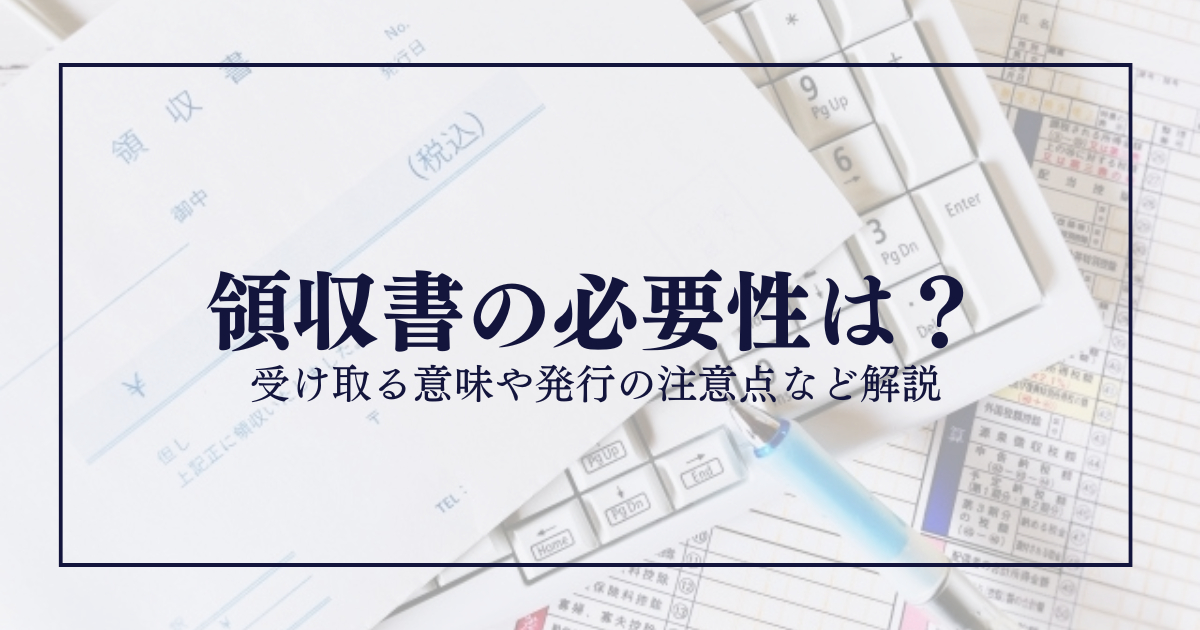
領収書は、ビジネスや日常生活で非常に重要な役割を担っています。これは「証憑(しょうひょう)」の一種とみなされ、税務処理や取引確認をスムーズに行うために欠かせない証拠書類です。
この記事では領収書が必要とされる理由や正しい書き方、注意点などを解説します。
領収書とは?必要とされる理由と主な役割
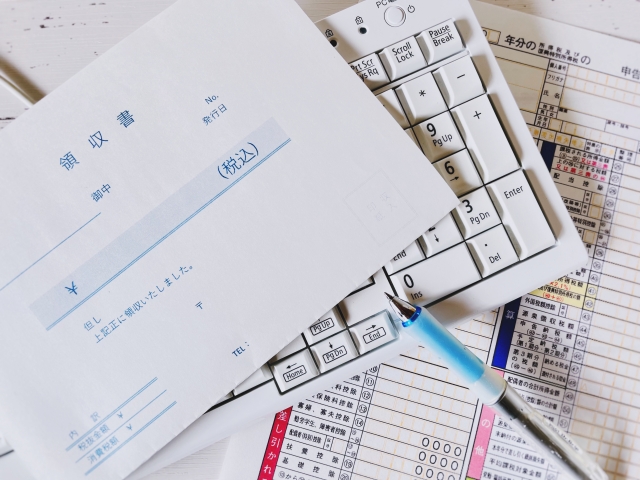
領収書とは、取引において金銭の授受があったことの証明となる基本的な書類です。領収書には主に3つの重要な役割があります。
二重払いや過払いを防ぐ
領収書は商品・サービスの代金が確実に支払われた事実を示すため、すでに支払い済みの取引が二重に請求されたり、誤って過払いが生じたりするリスクを減らします。
税務申告の証憑書類となる
法人や個人事業主が確定申告をする際、経費を計上するためには領収書などの証憑書類を根拠資料として保存することが義務付けられています。領収書がなければ、税務調査時に取引の説明が困難になり、脱税を疑われ、追徴課税を受けるおそれがあります。
不正行為を防ぐ
従業員による経費の不正申請(例:架空の交通費や宿泊費の申請、個人的な費用を接待費として計上)を防ぐためにも、領収書の提出を必須とすることで、不正行為を困難にできます。この点では、取引の詳細が把握できるレシートのほうが適している場合もあります。
民法により、代金を支払った側は、受け取った側に対して領収書の発行を請求する権利が法的に認められています。
領収書の正しい書き方と必要項目

領収書は、金銭の授受が確実に行われたことを証明し、不正な改ざんを防ぐために、特定の項目を正確に記載する必要があります。基本的な記載項目は以下の通りです。
タイトル
上部中央または左側に「領収書」と明記し、一目でわかるように太字や大きな文字で記載することが望ましいです。
領収日
金銭の授受が行われた日付を記載します。後日発行する場合でも、実際に支払いがあった日を遡って記載します。銀行振込の場合は、入金された日付を記入します。
年号は西暦・和暦どちらでも構いませんが、「25」や「R7」といった略称は用いず、「2025年4月1日」のように年月日を省略せず正確に記入してください。
支払先の氏名または名称
支払う側の個人名または法人名を正確に記載することが重要です。会社名を省略したり、「上様」と記載したりする領収書は、経費として認められない可能性があります。
ただし、小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の相手に発行される特定の業種では、簡易的な適格簡易請求書として宛名の省略が認められています。宛名は、改ざんや不正を防ぐため、原則として代金を受領した者が記入しなければいけません。
領収金額
改ざん防止のため、金額の先頭に「¥」または「金」、末尾に「-」や「※」、「也」などを記載し、3桁ごとにカンマを入れるのが基本です。記載金額は税込です。
但し書き
何に対する支払いかを具体的に記載します。「お品代」のような曖昧な表現は避け、「通信費として」「飲食代として」などと詳細に書くことが望ましいです。品目が多く書ききれない場合は、代表的な品目のみを記載し「他〇点」と添えたり、納品書を添付したりすることで対処可能です。
書類作成者の氏名または名称
領収書を発行した個人名や屋号、会社名、店舗名などの正式名称、住所、連絡先を正確に記載します。押印は法的には必須ではありませんが、偽造防止や信頼性向上のために推奨されます。
ただし、収入印紙を貼る場合は、消印として押印または署名が必要です。
通し番号
必須ではありませんが、各取引の識別や証憑整理を効率化するために付けることが推奨されます。
インボイス制度導入後の領収書
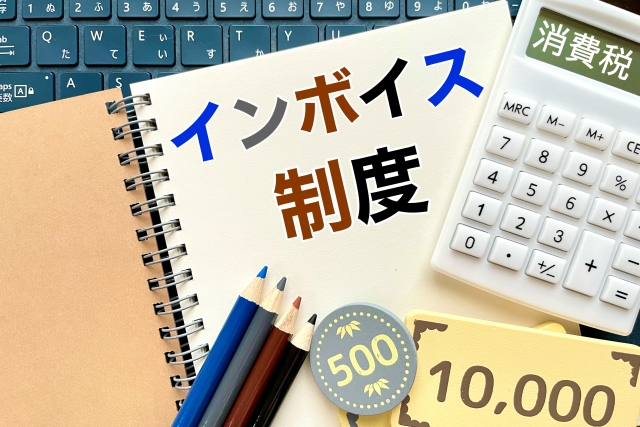
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、領収書の記載項目と役割が大きく変わりました。
買手側の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として、売手側から発行された適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。領収書も、一定の要件を満たすことで適格請求書として扱うことができます。
インボイス対応の領収書にルール上必要な追加の記載項目
インボイス対応の領収書にはインボイス制度導入前と異なり、以下の項目を記載する必要があります。
税率ごとに区分した消費税額と適用税率
軽減税率(8%)対象品目がある場合は、その旨と税率を明記します。
標準税率10%と軽減税率8%が混在している場合、品目ごとの合計金額(税込・税別どちらでも可)、適用された税率やそれぞれの税率ごとに区分された消費税額を記載しなければなりません。
消費税の端数処理は、1つのインボイスにつき税率ごとに1回のみと定められています。
発行者の登録番号
適格請求書発行事業者として税務署に登録されると付与される「T+13桁」の登録番号を記載する必要があります。この登録番号がないと、原則として仕入税額控除は受けられません。
領収書発行時の注意点

領収書を発行する側は、記載内容の正確さを確保しつつ、印紙税法を遵守することに特に留意しなければなりません。
正しく正確な記載
誤った内容が記載された領収書は、証憑書類としての役割を果たせないため、金額、宛名、品名などに誤記がないよう十分に注意しましょう。
収入印紙の貼付
原則として、税抜5万円以上の金額で現金払いされた領収書には、金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。
収入印紙が不要なケース
クレジットカード決済や一部のキャッシュレス決済(後払い方式を領収書に明記した場合)、PDFやメールなどでデジタル発行された領収書には、収入印紙は不要です。
必要な収入印紙を貼らなかった場合のペナルティ
収入印紙が必要であるにもかかわらず貼付しなかった場合、発行者は、本来貼付すべき収入印紙額の3倍に相当する過怠税を科されるおそれがあります。
領収書とレシートの二重発行の回避
同じ取引に対して領収書とレシートを両方発行すると、経費の二重計上につながるリスクがあるため、避けるべきです。
再発行は原則不可
領収書は原則として一度しか発行されません。「同時履行の原則」があり、紛失などを理由とした再発行は、代金支払いと発行のタイミングが同時でなくなるため、発行者側は拒否する権利があります。水増し請求や二重請求などのトラブルを避けるためでもあります。もし再発行する場合は、「再発行」や「再」といった記載を加えて不正防止対策を講じます。
控えの保存
発行者側は、発行した領収書の控えを保存しておくのが一般的です。
領収書の控えは確定申告書の提出期限の翌日から、個人事業主は青色申告の場合には原則7年間、そして青色申告で事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の場合と白色申告の場合には5年間保存が必要です。
法人は確定申告書の提出期限の翌日から、原則7年間(繰越欠損金がある場合は原則10年間)の保存が義務付けられています。
インボイスとして発行した領収書の写しも、交付または提供した日の属する課税期間の末日から2ヶ月を経過した日から7年間保存が必要です。
領収書受領時の注意点

領収書を受け取る側も経費計上や税務調査に備え、適切な取り扱いと保管が求められます。
記載情報の確認
領収書を受け取ったらすぐに、記載情報に誤りがないか確認しましょう。
原則再発行不可
領収書は原則再発行されないため、受け取ったらすぐに記載内容を確認し、破棄や紛失しないように厳重に保管する必要があります。
レシートと領収書はどちらか一方の受取
二重計上を防ぐため、レシートと領収書の両方を同時に受け取ることはできません。
正しい保管
領収書は税務上、適切な方法で一定期間の保管が義務付けられています。
代替書類の利用
銀行振込明細書やクレジットカードの利用明細は、必要項目が記載されていれば領収書の代用として使用できます。公共交通機関の運賃など、一部の取引では領収書が不要なケースもあります。
まとめ

ここまで領収書について詳しく解説してきました。領収書の取り扱いにご不明点などがある場合は経理アウトソーシングの利用がおすすめです。
経理アウトソーシングを導入すると、コスト削減や業務品質の向上、リソースの確保、コンプライアンス強化といった多彩なメリットが得られます。一方で、委託先との連携不足がミスを誘発するリスクなどもあります。
これらの利点を最大限に活かすためには、計画的に導入を進めることが重要であるといえるでしょう。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 与信管理
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 仕訳
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
RANKING
お役立ち情報
CASE