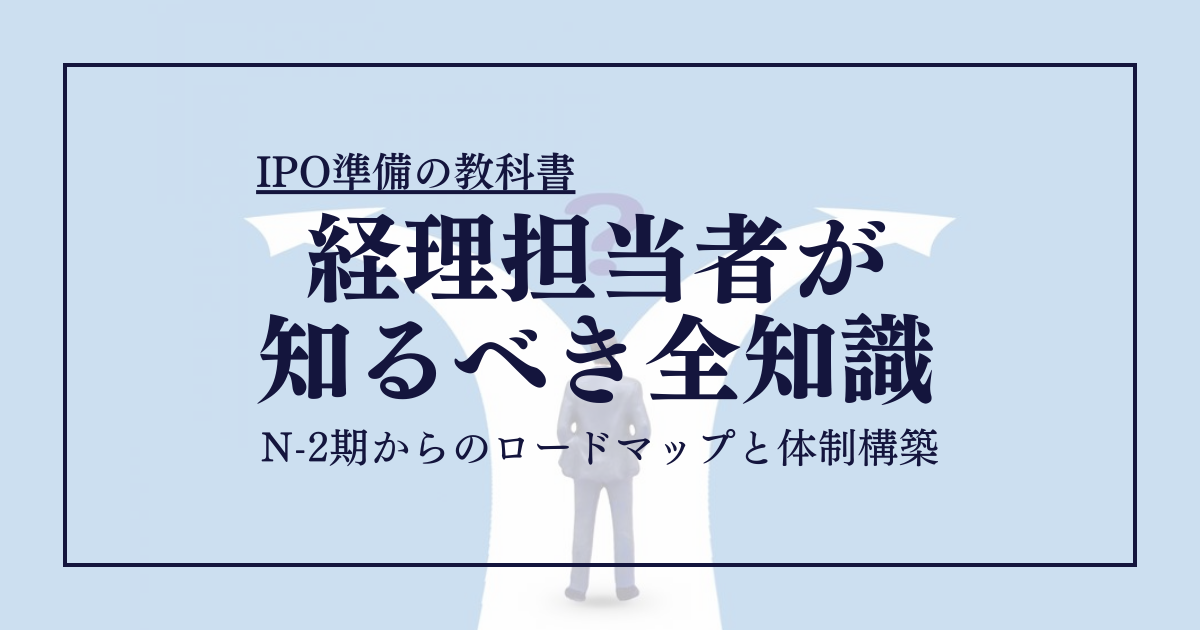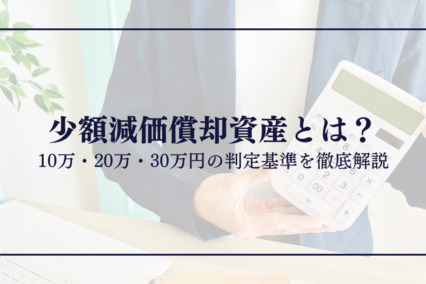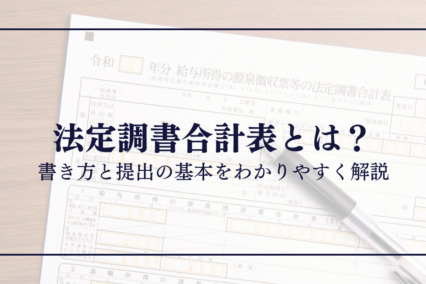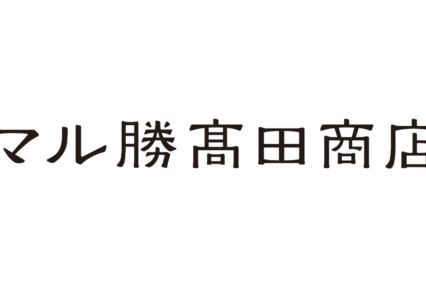企業が非連続な成長を遂げるための重要な経営戦略の選択肢となるIPO(新規株式公開)。
その華々しいイメージとは裏腹に、成功の裏側には、極めて緻密で強固な管理体制の構築が不可欠です。
中でも、企業の財政状態と経営成績を社会に示す責任を負う経理部門の準備は、上場審査の根幹をなし、プロジェクト全体の成否を左右するほどの重要性を持っています。
本記事では、IPO準備の最も重要なN-2期にフォーカスし、経理担当者が知っておくべき知識を体系的に解説します。
はじめに:IPO準備、経理の役割が成功の鍵を握る

企業の成長戦略における重要な選択肢となるIPO(新規株式公開)。その達成には、事業の成長性はもちろんのこと、強固な管理体制が不可欠です。
特に、企業の財政状態と経営成績を正確に社会へ示す役割を担う経理部門は、IPO準備プロジェクトの成否を左右する中心的な存在と言っても過言ではありません。
IPO準備は、単に過去の数値をまとめる作業ではありません。上場企業として求められる会計基準への準拠、迅速かつ正確な決算体制の構築、そして投資家からの信頼を得るための内部統制の整備など、その業務は多岐にわたります。
【要注意】多くの企業が陥る、IPO準備における3つの落とし穴

IPO準備の道のりは決して平坦ではありません。特に経理部門は、上場企業としての適格性を問われる重要な役割を担うため、多くの課題に直面します。ここでは、多くの企業が陥りがちな3つの典型的な落とし穴について解説します。
落とし穴①:月次決算の遅延と不十分な会計処理
非上場時には許容されていたかもしれない月次決算の遅延は、IPO準備においては致命的な問題となります。上場企業には、投資家保護の観点から、迅速かつ正確な情報開示が義務付けられます。月次決算の遅延は、会社の経営状況をタイムリーに把握できていない証左と見なされ、管理体制の不備を指摘される原因となります。
また、求められる会計処理の適切性も厳しく問われます。
求められる会計処理の適切性も、上場企業の水準へと格段に引き上げられます。過去の会計処理に誤りがあった場合に遡及修正が必要なのは当然ですが、より重要なのは、そもそも準拠すべき会計基準のレベルが非上場時とは比較にならないほど高度になる点です。
この対応には膨大な時間と労力を要します。また、監査法人は客観的な第三者として、会社を無条件に信頼するのではなく、あくまで証拠に基づいて会計処理の妥当性を判断します。そのため、不適切な処理が発覚すれば、監査が円滑に進まなくなる可能性も考えられます。
落とし穴②:内部統制の脆弱性
IPOを実現するためには、適切な内部統制が整備・運用されていることが必須条件です。内部統制とは、企業の業務の適正性を確保するための仕組みであり、財務報告の信頼性が最も重要な目的です。
しかし、ルールや規定を作成しただけで、実際の業務が伴っていない形骸化した状態に陥る企業は少なくありません。例えば、承認フローが守られていない、職務分掌が不明確であるといった状態は、不正や誤謬のリスクを高め、上場審査において重大な欠格事由と判断される可能性があります。
落とし穴③:専門知識を持つ人材の不足
IPO準備には、上場企業特有の会計基準や開示制度、内部統制の整備・運用と、それに対応する内部統制報告制度(通称J-SOX)など、高度な専門知識が求められます。しかし、これらの知識と実務経験を兼ね備えた人材は市場でも希少であり、多くの企業が人材不足という壁に直面します。
日常業務に加えて膨大な準備作業が発生するため、既存の経理メンバーだけでは対応が困難になるケースがほとんどです。人員を補充しようにも、採用には時間がかかり、育成も追いつかないというジレンマが、IPO準備の遅延を引き起こす大きな要因となっています。
【全体像】IPO準備における経理のロードマップ
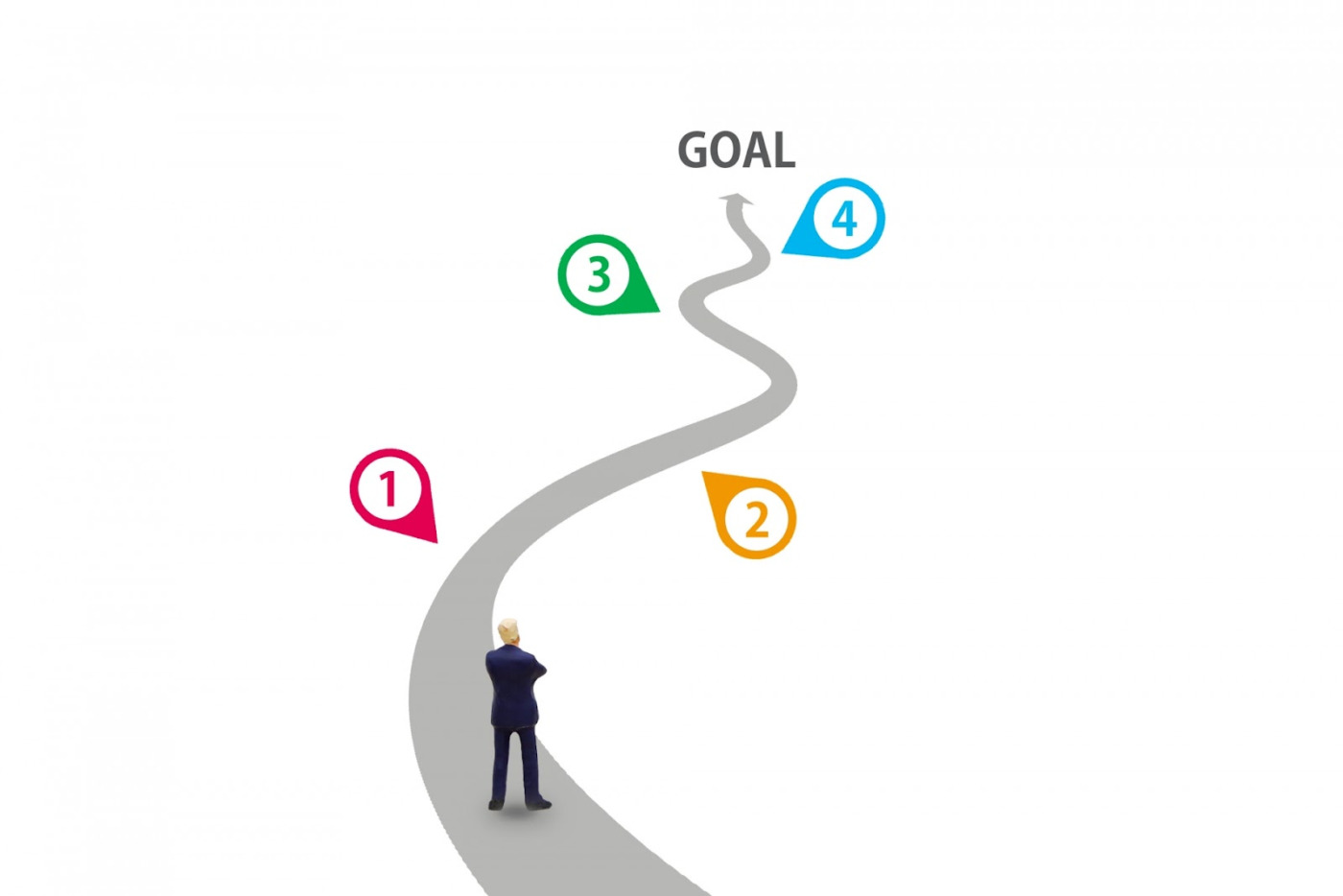
IPO準備は、一般的に申請期の2年前(N-2期)から本格化しますが、その前段階からの準備も重要です。ここでは、経理部門が関わるIPO準備の全体像を、時系列に沿ったロードマップとして示します。
N-3期以前:IPOプロジェクトのキックオフとショートレビューの実施
この時期は、本格的な準備に向けた助走期間です。まずは、IPOを目指すことを全社的なプロジェクトとして正式にキックオフします。経理部門としては、監査法人やコンサルタントなどの外部専門家と連携し、現状の会計処理や管理体制における課題を網羅的に洗い出すことが重要です。この段階で課題を明確にすることで、後の計画がスムーズに進みます。
N-2期:会計監査の開始|会計・管理体制の構築
N-2期は、IPOの土台を作る最も重要な期間です。上場企業として求められる会計基準に準拠するための会計方針を固め、月次決算を早期化(一般的に5営業日以内)する体制を構築します。また、原価計算制度や固定資産管理など、これまで曖昧だった可能性のある管理体制を一つひとつルールとして明確化し、運用していきます。
N-1期:内部統制の運用
N-2期で整備した会計制度や管理体制を、実際に1年間運用する期間がN-1期です。特に、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度(J-SOX)への対応が本格化します。業務フローの文書化やリスクの識別・評価を行い、内部統制が有効に機能していることを証明する必要があります。また、この期から上場申請書類(Ⅰの部、Ⅱの部)の作成に着手することになります。
申請期:最終準備と審査対応
いよいよ上場申請をおこなう期です。主幹事証券会社や証券取引所による厳しい審査が待ち受けています。経理部門は、審査で要求される膨大な資料を作成し、経営陣と一緒に、想定問答のブラッシュアップを含めた事前準備を担います。上場申請書類である「Ⅰの部」や「Ⅱの部」の作成も完成となります。
【N-2期】IPOの土台を築く、上場水準の経理体制構築

IPO準備の成否は、N-2期にどれだけ強固な土台を築けるかにかかっていると言っても過言ではありません。この時期に構築すべき「守りの経理体制」について、具体的なポイントを解説します。
会計方針の決定と会計基準への準拠
まずは、自社の会計処理のルールブックである「経理規程」や「会計方針」を明確に文書化し、上場企業に求められる会計基準(金商法基準)に準拠させる必要があります。収益認識基準や固定資産の減損会計など、論点となりやすい項目については、監査法人とも協議の上、方針を固めておくことが重要です。
月次決算の早期化(5営業日以内)
上場企業には迅速な情報開示が求められるため、月次決算を翌月5営業日以内に完了させる体制の構築を目指します。これを実現するためには、単に経理担当者の努力に頼るだけでなく、業務プロセスの見直しや会計システムの導入・改修が不可欠です。
原価計算制度の整備・導入
製造業やIT企業など、原価計算が重要な業種においては、正確な原価計算制度の確立が必須です。製品やサービスごとの損益を正しく把握できていなければ、信頼性のある財務諸表を作成することはできません。自社のビジネスモデルに合った原価計算方法(実際原価計算、標準原価計算など)を導入し、継続的に運用できる体制を整える必要があります。
固定資産・棚卸資産の管理体制強化
固定資産や棚卸資産は、管理が煩雑になりがちな資産です。固定資産については、現物と台帳を一致させ、減価償却計算が正しく行われていることを確認する体制を強化します。棚卸資産についても、定期的な実地棚卸のルールを定め、評価方法(先入先出法、移動平均法など)を明確にし、滞留在庫の評価損を適切に計上する仕組みを構築することが求められます。
あわせて、こうした実績管理だけでなく、計画的な設備投資や在庫管理を行うための予算管理体制を整備し、予実分析を通じて経営判断に活かす仕組み作りも不可欠です。
【N-1期】内部統制の本格運用と開示体制の構築

N-2期で構築した体制を実際に運用し、上場後を想定した本番さながらのアクションをするフェーズがN-1期です。ここでは、特に重要となる「内部統制」と「開示体制」の準備について解説します。
J-SOX対応:内部統制報告制度の構築と運用
J-SOX対応は、N-1期における経理部門の重要課題の一つです。これは、財務報告の信頼性を確保するための社内体制を構築し、経営者自らがその有効性を評価・報告する制度です。全社的な内部統制から、決算・財務報告プロセス、そして売上や仕入といった重要な業務プロセスに至るまで、リスクを識別し、それに対応するコントロール(統制活動)が、N-1において問題なく運用されるか確認します。
業務フローの文書化(整備・運用状況の記録)
J-SOX対応の一環として、各業務プロセスを文書化することが求められます。具体的には、「業務フロー図」「業務記述書」「リスクコントロールマトリクス(RCM)」といった3点セットを作成します。これにより、誰が、いつ、何をしているのかが可視化され、内部統制が有効に機能していることを客観的に示す証拠となります。この文書化作業は、自社の内部統制が有効であることを経営者自身が評価・報告するための基礎となります。同時に、監査法人による監査や上場審査でも重要な資料となります。
関連当事者取引の整理と解消
オーナー経営者やその親族、役員などが関係する会社との取引(関連当事者取引)は、上場審査において特に厳しくチェックされる項目です。取引の必要性や価格の妥当性が客観的に説明できない場合、利益相反や不正の温床と見なされる可能性があります。原則として、IPO準備の過程でこれらの取引は整理・解消することが求められます。
開示(ディスクロージャー)体制の構築
上場企業は、投資家保護の観点から情報開示を行う義務を負います。この開示は、主に以下の3つに大別されます。
- 法定開示:金融商品取引法に基づく開示(有価証券報告書など)
- 適時開示:証券取引所の規則に基づく開示(決算短信、重要事実の発生など)
- 任意開示:会社が自主的な判断で行う、上記以外の情報提供
N-1期には、この開示体制を構築する必要があります。社内で発生した重要な情報を迅速に収集し、開示の要否を判断し、正確な開示資料を作成・公表するための一連のプロセスと担当部署を明確に定めておくことが重要です。
【申請期】上場承認に向けた最終関門|審査対応の総仕上げ

最終関門である申請期では、これまでの準備の成果が問われます。監査法人や主幹事証券会社といった外部の専門機関との連携を密にし、審査を乗り越えるための最終準備を進めます。
証券会社・取引所による審査への対応
主幹事証券会社と証券取引所は、それぞれ独自の視点から企業の「上場適格性」を審査します。経理部門は、事業計画の合理性、予算実績管理体制、会計処理の妥当性などに関する詳細な質問に回答する中心的な役割を担います。質問会では、経営陣と一体となって、自社の管理体制の堅牢性を論理的に説明する能力が求められます。
上場申請書類(Ⅰの部、Ⅱの部など)の作成
上場申請の際には、「Ⅰの部」「Ⅱの部」をはじめとする膨大な申請書類を提出する必要があります。「Ⅰの部」は投資家向けの目論見書となり、企業の事業内容や財務状況を詳細に記載します。「Ⅱの部」は取引所への説明資料であり、より詳細な管理体制やコンプライアンス状況などを記述します。経理部門は、これらの書類における財務情報の作成に責任を持つ、極めて重要なパートを担います。
資本政策の最終調整と実行
資本政策は、IPO準備において長期的な視点で検討される重要課題です。株主構成の安定化といった論点はN-1期までに最終調整を終えておき、申請期には、主幹事証券会社と連携しながら、上場時の資金調達に関する具体的な計画を最終化します。
具体的には、市況や機関投資家の需要などを勘案しながら、公募・売出の規模や価格といった発行条件を慎重に決定していきます。この条件は、上場承認後に実行される資金調達の成否を左右する、極めて重要な意思決定です。
上場申請に必要な監査報告書(N-2期・N-1期)
上場を申請する際には、申請書類の一部として、直前2期分(N-2期およびN-1期)の財務諸表と、それに対する監査法人の監査報告書を提出する必要があり、原則として「無限定適正意見」であることが求められます。これらは、会社の信頼性を客観的に証明する上で、極めて重要な書類となります。
申請期の期末監査への対応
上記とは別に、現在進行中である申請期の会計年度についても、当然ながら期末監査を受ける必要があります。これは上場申請書類には含まれませんが、上場審査と並行して進められるこの監査を無事に完了させることも、最終的な上場を果たすための絶対条件です。
人材不足をどう乗り越えるか?IPO成功に必要な経理チームと外部活用のポイント

IPO準備という壮大なプロジェクトを成功させるには、強力な経理チームが不可欠です。しかし、多くの企業が専門知識を持つ人材の不足という課題に直面しています。ここでは、その課題を乗り越えるための考え方と具体的な方策を解説します。
IPO準備で経理担当者に求められるスキルセットとは
IPO準備を担う経理担当者には、日常の経理業務のスキルに加え、特殊な能力が求められます。具体的には、上場企業会計基準に関する深い知識、開示制度や会社法・金融商品取引法への理解、内部統制(J-SOX)の構築・運用経験、そして監査法人や証券会社と対等に交渉できるコミュニケーション能力などが挙げられます。これらすべてを一人で満たすことは困難であり、チームとして能力を補完し合うことが重要です。
外部専門家(コンサルタント、アウトソーシング)活用のメリット
「IPO準備に関する業務は、すべて自社で内製しなければならない」という考えは、必ずしも正しくありません。むしろ、多くの企業がIPO準備の過程で外部専門家を有効に活用し、成功を収めています。
社内リソースだけで対応が難しい場合、外部専門家の活用が極めて有効な選択肢となります。IPO支援に特化したコンサルタントやアウトソーシングサービスを利用することで、専門知識やノウハウを即座に補完できます。また、彼らは多くの企業のIPO準備を支援した経験から、つまずきやすいポイントや審査の勘所を熟知しており、プロジェクトを効率的に推進し、手戻りを防ぐことができます。
採用・育成と外部活用の最適なバランス
理想は、IPO後も企業を支える核となる人材を社内で育成することです。しかし、IPO準備は待ったなしで進みます。そのため、短期的な課題解決や専門性の高い領域については外部専門家を活用し、その間に社内メンバーがOJTを通じて知識やスキルを吸収していく、というハイブリッドな体制が現実的かつ効果的です。外部専門家を単なる「外注先」ではなく、「チームの一員」として巻き込むことで、ノウハウの社内移転もスムーズに進むと考えられます。
専門家のサポートで、IPO準備のハードルを乗り越える

IPO準備は、企業にとって未知の領域への挑戦です。自社だけで全ての課題を解決しようとすると、時間的にも人的にも限界があります。専門家のサポートを適切に活用することで、これらのハードルを効率的に、そして確実に乗り越えることが可能になります。
課題整理からロードマップ策定までを一貫して支援
経験豊富な専門家は、まず企業の現状を客観的に分析し、IPOに向けて何をすべきかという課題を網羅的に洗い出します。その上で、各社の状況に合わせた最適なロードマップと、具体的なアクションプランを策定します。これにより、企業はゴールまでの道のりを明確に描き、迷うことなく準備に着手することができます。
決算早期化や内部統制構築の実務をハンズオンでサポート
専門家の支援は、計画策定だけにとどまりません。月次決算早期化のための業務プロセス改善や、J-SOX対応における3点セット(業務フロー図、業務記述書、RCM)の作成など、実務レベルでのハンズオン支援も提供します。担当者と一緒になって手を動かすことで、ノウハウが社内に蓄積され、IPO後も自律的に運用できる体制が構築されます。
貴社のチームの一員としてプロジェクトを推進
IPO準備は経理・財務部門が中心となって進められますが、実質的には全社を巻き込んだ一大プロジェクトです。
BPIOは、単なる外部アドバイザーではなく、貴社のプロジェクトチームの一員として伴走します。監査法人や証券会社との専門的な折衝への同席、経営会議での助言はもちろん、「人手が足りない」「実務の進め方がわからない」といった場面では、担当者様と一緒になって手を動かし、上場申請書類の作成までハンズオンでサポートします。このようなパートナーの存在は、担当者や経営陣にとって大きな精神的支えにもなります。
「何から相談すればいいか分からない」「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫だろうか」といった段階でも、まったく問題ありません。まずは貴社の状況や課題の整理からお手伝いさせてください。担当者様が一人で悩みを抱え込まないための、頼れるパートナーとなることをお約束します。
まとめ:計画的な準備がIPOの成否を分ける

本記事では、IPO準備における経理担当者が知るべき知識を、N-2期を中心にロードマップに沿って網羅的に解説しました。月次決算の早期化や内部統制の構築といった体制整備から、申請書類の作成、審査対応まで、経理部門が担う役割は非常に広く、かつ専門性が高いことがお分かりいただけたかと思います。
多くの企業が陥りがちな落とし穴を避け、この壮大なプロジェクトを成功に導くために最も重要なことは、早期から全体像を把握し、計画的に準備を進めることです。特に、すべての土台となるN-2期の取り組みが、その後の成否を大きく左右します。
また、IPO準備は社内のリソースだけで完結させることが難しいプロジェクトです。人材不足やノウハウ不足といった課題に直面した際には、躊躇なく外部専門家の力を活用することも、成功への近道と言えるでしょう。
BPaaSや経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
RANKING
お役立ち情報
CASE