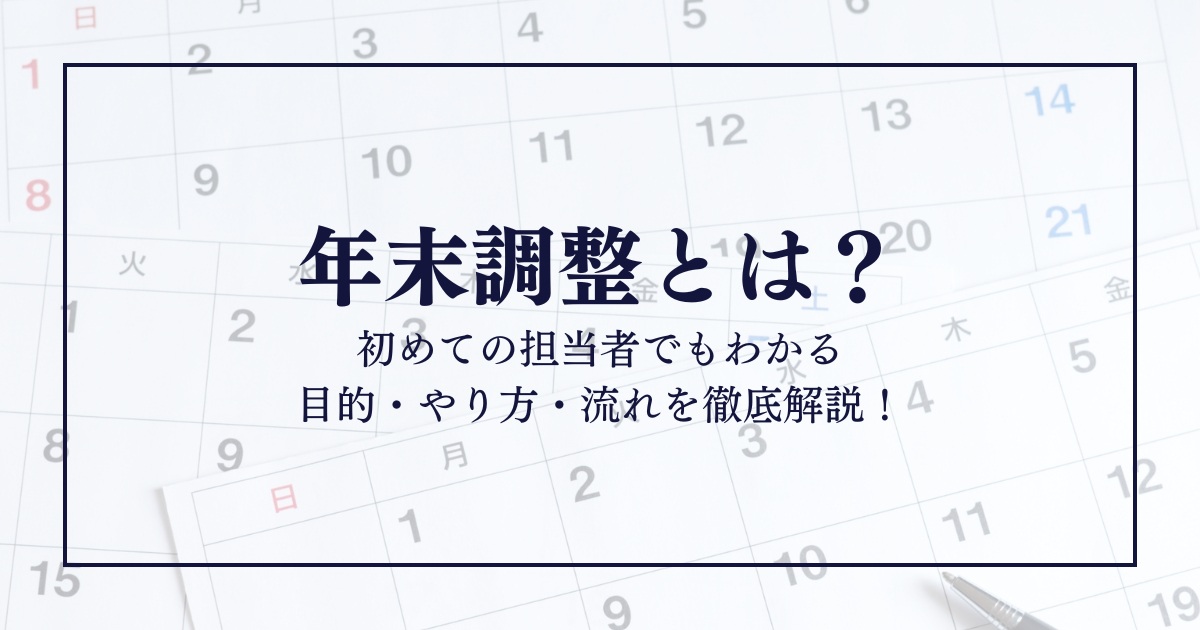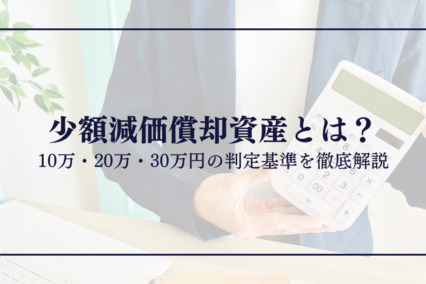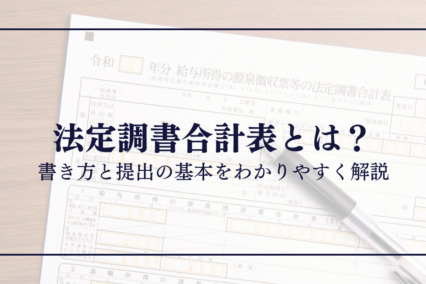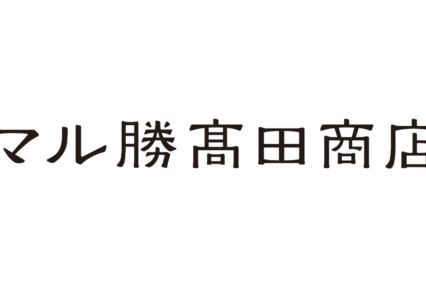毎年秋から冬にかけて、経理や人事の担当者が慌ただしくなる業務の一つに「年末調整」があります。従業員にとっては馴染みのある言葉ですが、初めて担当する方にとっては「何から手をつければ良いのかわからない」と不安に感じるかもしれません。
年末調整は、従業員の所得税を正しく計算し、納税を完了させるための重要な手続きです。この記事では、年末調整の目的や仕組みといった基礎知識から、担当者が行うべき具体的な業務の流れ、年間スケジュールまで、初めての方でも理解できるようわかりやすく解説します。
年末調整とは?目的と仕組みをわかりやすく解説
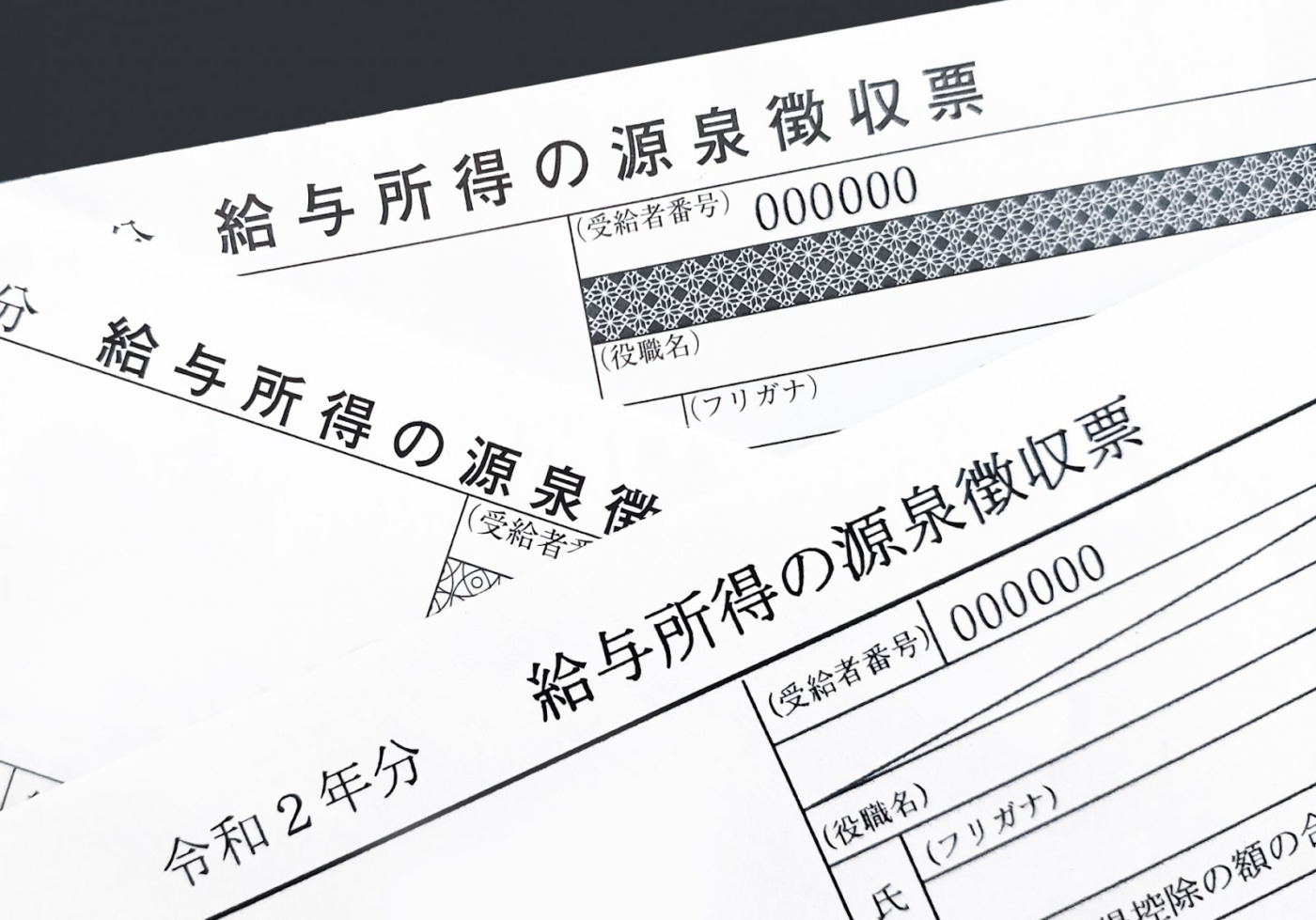
年末調整とは、会社が従業員に代わって、毎月の給与や賞与から源泉徴収(天引き)した所得税の合計額と、その年の正しい所得税額との差額を精算する手続きのことです。
毎月の給与から天引きされる所得税は概算額
会社は、毎月従業員に給与を支払う際、「源泉徴収税額表」に基づいて所得税を天引きし、国に納付しています。しかし、この時点での所得税額はあくまで概算です。
なぜなら、月々の源泉徴収の計算には、従業員が支払った生命保険料や地震保険料などの控除が反映されていないためです。また、年の途中で扶養家族の人数に変動があった場合なども、毎月の計算とはズレが生じます。
年間の正しい所得税額を計算し精算する手続き
そこで、1年間の給与総額が確定する年末のタイミングで、各種控除を適用して正しい所得税額(年税額)を再計算します。
この年税額と、1年間に天引きされた所得税の合計額を比較し、差額を精算するのが年末調整の目的です。天引き額が多すぎた場合は差額を従業員に還付し、不足していた場合は追加で徴収します。この精算は、一般的に12月または翌年1月の給与で行われます。
年末調整と確定申告の3つの違い

年末調整とよく似た言葉に「確定申告」があります。どちらも所得税を精算する手続きですが、対象者や時期などが異なります。担当者として、従業員から質問された際に答えられるよう、違いを理解しておきましょう。
1:手続きを行う人
年末調整は、会社(給与の支払者)が従業員に代わって計算から納税までを行います。
一方、確定申告は、納税者本人が自ら税務署に対して行います。
2:対象となる所得
年末調整の対象は、原則として会社から支払われる給与所得のみです。
確定申告は、給与所得の他に、個人事業主の事業所得や、不動産所得、株式の譲渡所得など、あらゆる所得が対象となります。
3:手続きの時期
年末調整は、その名の通り年末(11月〜翌年1月)にかけて行われます。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行うのが原則です。
年末調整の対象となる人・ならない人

自社で雇用している従業員が、全員年末調整の対象となるわけではありません。ここでは、対象となる主なケースと、対象外となるケースについて解説します。
年末調整の対象となる主なケース
年末調整の対象となるのは、原則として、その年の初めに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している従業員です。具体的には、以下のような人が該当します。
- 1年を通じて勤務している正社員や契約社員、パート・アルバイト
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人(前職の源泉徴収票がある場合)
年末調整の対象外で確定申告が必要なケース
一方で、以下のようなケースに該当する従業員は、年末調整の対象外となり、原則として自身で確定申告を行う必要があります。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受け取っており、自社に扶養控除等申告書を提出していない人
- 副業の所得が年間20万円を超える人
- 災害減免法(※)により、その年の給与に対する所得税の徴収猶予や還付を受けた人
- 年の途中で退職し、再就職していない人
※大規模な災害によって損害を受けた場合に、所得税が軽減・免除される制度のことです。
【担当者向け】年末調整のやり方と年間スケジュール

ここからは、担当者向けの具体的な業務の流れを、年間スケジュールに沿って解説します。年末調整の業務は10月頃から始まり、翌年1月末まで続きます。
【10月下旬~11月】必要書類の準備と配布
まず、従業員に記入してもらうための各種申告書を準備し、配布します。同時に、提出期限や注意事項などをアナウンスしましょう。
主な配布書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- (対象者のみ)住宅借入金等特別控除申告書
【11月~12月】従業員からの書類回収と内容確認
従業員から提出された申告書を回収し、内容に不備や漏れがないかを確認します。特に、生命保険料控除証明書などの添付書類が揃っているか、金額の転記ミスがないかなどを入念にチェックする必要があります。
この確認作業は、年末調整業務の中で最も時間と手間がかかる部分です。不備があれば従業員に差し戻して修正を依頼するため、早めに回収を進めることが重要です。
【12月】年税額の計算と過不足額の精算
全従業員の申告書内容が確定したら、年末調整の計算ソフトなどを用いて年税額を算出します。そして、1年間の源泉徴収税額との差額(過不足額)を確定させます。
算出した過不足額は、12月または翌年1月の給与で精算します。還付の場合は給与に上乗せし、徴収の場合は給与から天引きします。精算後、従業員一人ひとりに「源泉徴収票」を発行・交付します。
【翌年1月】法定調書と給与支払報告書の作成・提出
最後に、税務署と各市区町村へ提出する書類を作成します。
- 税務署への提出書類
- 法定調書合計表
- 源泉徴収票
各市区町村への提出書類
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
これらの書類は、原則として翌年の1月31日が提出期限です。期限に遅れるとペナルティが課される可能性もあるため、計画的に進めましょう。
年末調整で知っておきたい主な所得控除

所得控除とは、個人の事情に合わせて所得金額から一定額を差し引くことができる制度です。控除額が大きいほど課税対象の所得が減り、結果的に所得税が安くなります。ここでは、代表的な所得控除を紹介します。
基礎控除・配偶者控除・扶養控除
合計所得金額に応じて受けられる「基礎控除」や、配偶者や親族を扶養している場合に受けられる控除です。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料などを支払っている場合に受けられます。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
国民年金や国民健康保険料、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金などを支払っている場合に、その全額が控除されます。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築した場合に受けられる控除です。2年目以降の年末調整で適用を受けるには、税務署から送付される申告書と金融機関の残高証明書が必要です。
年末調整に関するQ&A

ここでは、担当者がよく直面する疑問についてQ&A形式で回答します。
Q1.従業員が書類の提出期限に遅れた場合は?
会社の定めた期限までに申告書が提出されなかった場合、会社は年末調整を行う義務はありません。その場合、従業員自身で確定申告を行ってもらう必要があります。生命保険料控除などを受けられず、所得税を多く納めることになる可能性があるため、期限内に提出するよう周知することが大切です。
Q2.副業をしている従業員の年末調整はどうすれば良い?
年末調整は、主たる給与を支払っている1社でしか行えません。副業の所得が年間20万円を超える場合は、主たる給与の年末調整を済ませた後、従業員自身が副業の所得と合算して確定申告を行う必要があります。
Q3.年の途中で退職した従業員の年末調整は必要?
原則として、年の途中で退職した従業員の年末調整は行いません。会社は退職後1か月以内に源泉徴収票を発行し、本人に交付します。その従業員は、年内に再就職した場合は新しい勤務先で、再就職しなかった場合は自身で確定申告を行い、税金の精算をします。
年末調整の業務負担や属人化にお悩みならBPIOへ

年末調整は、毎年の法改正への対応や、煩雑な書類確認、計算など、担当者に大きな負担がかかる業務です。また、特定の担当者しか業務内容を把握していない「属人化」の状態に陥りやすく、その担当者が退職した際に、業務が滞るリスクも抱えています。
このような課題を解決する方法として、業務プロセスそのものを見直すことが有効です。
年末調整業務のアウトソーシング(BPO)
年末調整に関わる一連の業務を、専門知識を持つ外部の企業へ委託(アウトソーシング)することで、担当者の負担を大幅に軽減できます。煩雑な書類チェックから、毎年の法改正への正確な対応まで一括して任せられるのが大きな魅力です。
その際、アウトソーシング先を選ぶ上で重要となるのがコンプライアンス体制です。特に、源泉徴収票の作成など税理士の独占業務にあたる専門的な業務は、委託先の企業が提携する会計事務所などと連携して、適法に対応する必要があります。こうした専門家との連携体制が整っているかを確認することが、安心して業務を委託するための重要なポイントとなります。
BPIOでは、このコンプライアンス体制を徹底しており、税理士の独占業務は当社が提携する「SEVENRICH会計事務所」と連携して適切に対応いたします。専門家とのシームレスな連携により、担当者の皆様が本来のコア業務に集中できる環境作りを、ワンストップで支援します。
クラウドシステムの導入支援
年末調整に対応したクラウドシステムを導入すれば、申告書のペーパーレス化や計算の自動化が可能です。BPIOでは、お客様の状況に最適なシステムの選定から導入、運用までをトータルでサポートし、業務効率化と属人化の解消を実現します。
まとめ:年末調整をスムーズに進めるために

年末調整は、従業員の所得税を正しく確定させるための年に一度の重要な手続きです。初めて担当する方は戸惑うことも多いかもしれませんが、年間スケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。
まずは全体の流れを理解し、各ステップで何をすべきかを明確にしておきましょう。もし業務の負担や進め方に不安がある場合は、専門家やアウトソーシングサービスの活用を検討することも、有効な選択肢の一つです。
BPaaSや経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 与信管理
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 仕訳
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
RANKING
お役立ち情報
CASE