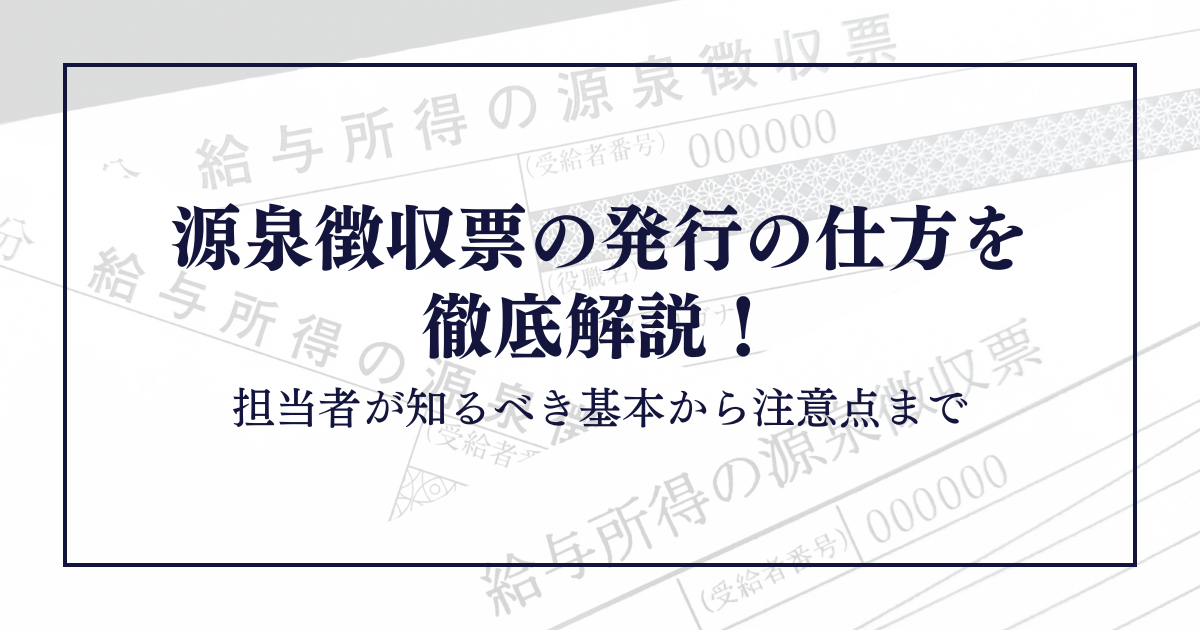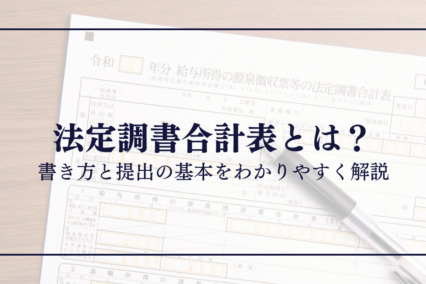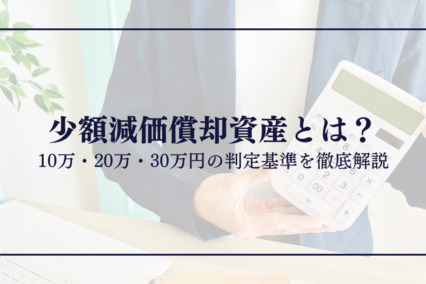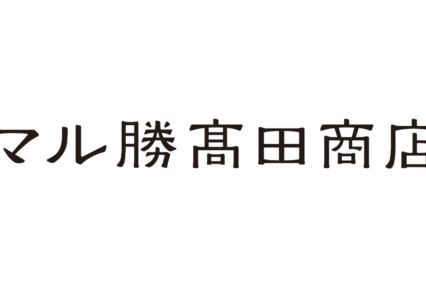企業の経理や人事担当者にとって、年末調整と並行して対応が必要になる業務の一つが「源泉徴収票の発行」です。 従業員にとって重要な書類であると同時に、所得税法によって発行が義務付けられているため、正確な知識と手順の理解が求められます。
本記事では、源泉徴収票の発行業務を初めて担当する方や、改めて手順を確認したい方に向けて、発行の基本から作成手順、ケース別の注意点、業務効率化につながる電子交付までをわかりやすく解説します。
源泉徴収票とは?発行は企業の義務
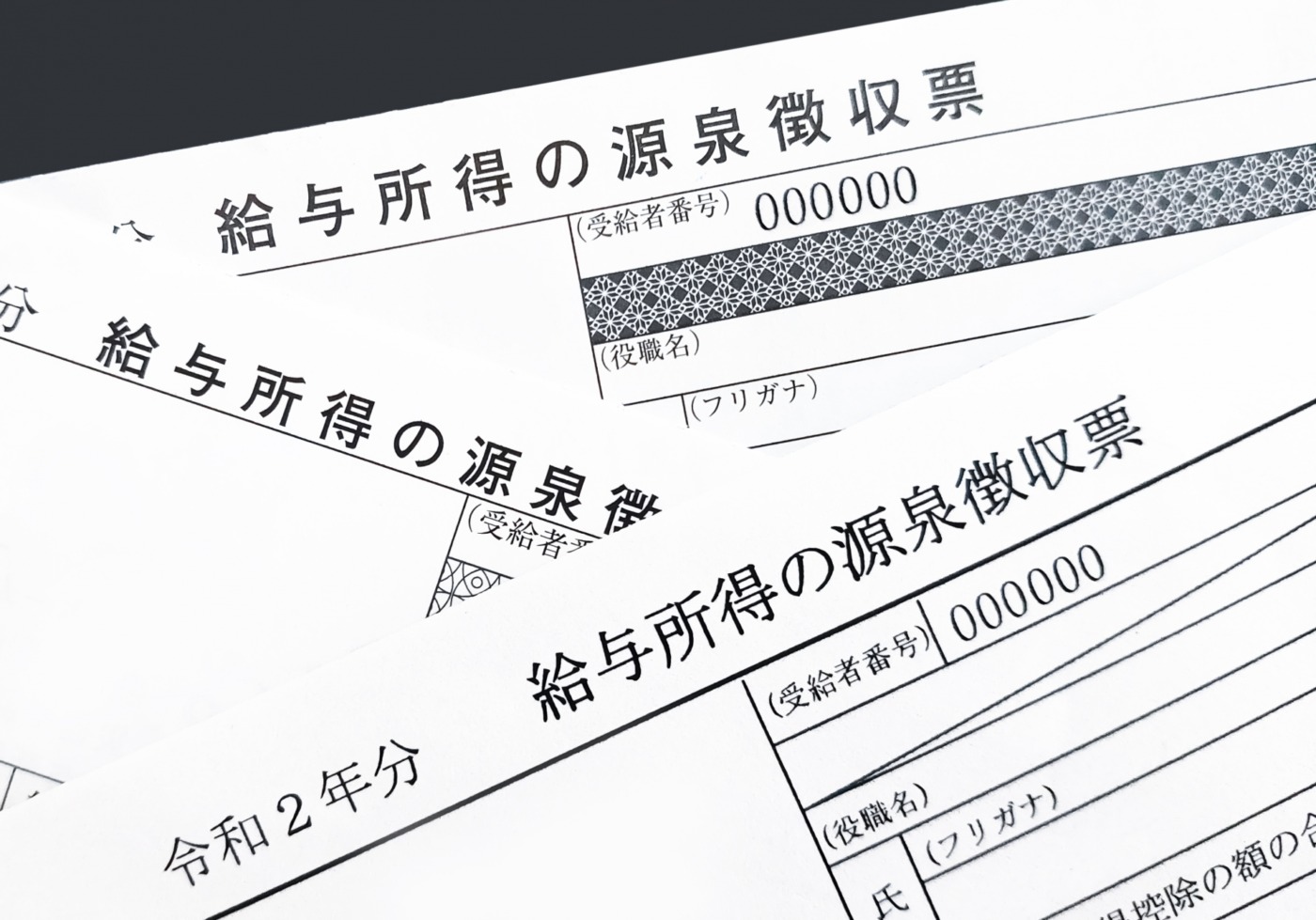
まず、源泉徴収票がどのような書類であり、なぜ発行しなければならないのか、その基本的な役割と法律上の義務について確認しておきましょう。
源泉徴収票の役割と重要性
源泉徴収票は、企業(給与支払者)が従業員(給与所得者)に対して1年間に支払った給与や賞与の総額と、そこから徴収した所得税(源泉徴収税額)の金額を証明する公的な書類です。
従業員は、この源泉徴収票をもとに確定申告を行ったり、転職先の企業で年末調整を受けたり、住宅ローンなどの審査で自身の収入を証明したりします。 企業にとっては、従業員が納めるべき税金を正しく徴収し、国に納付したことを証明する重要な役割を担っています。
発行対象者と発行のタイミング
源泉徴収票の発行は、所得税法第226条で定められた企業の義務です。 正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、役員など、給与を支払ったすべての人に対して発行する必要があります。
発行する主なタイミングは以下の2つです。
- 年末調整の後:その年の最後の給与を支払った後、年末調整の計算が完了したら発行します。
原則として、翌年の1月31日までに交付する必要があります。 - 従業員の退職時:従業員が年の中途で退職した場合、退職日から1ヶ月以内に発行・交付しなければなりません。退職者はこの源泉徴収票を使って、転職先で年末調整を受けるか、自身で確定申告を行います。
源泉徴収票の発行方法と基本的な手順

源泉徴収票の発行は、大きく分けて「情報準備」「作成」「交付」の3つのステップで進めます。
ステップ1:必要な情報を準備する
源泉徴収票を作成するためには、まず年間の給与支払いに関する正確な情報が必要です。主に以下の情報を準備します。
- 支払金額:その年に支払った給与・賞与の総額
- 給与所得控除後の金額:支払金額から給与所得控除額を差し引いた金額
- 所得控除の額の合計額:社会保険料控除や生命保険料控除などの合計額
- 源泉徴収税額:年間の所得税として徴収した合計額
- 控除対象扶養親族の数や氏名
- 社会保険料等の金額
- 生命保険料や地震保険料の控除額
- 従業員の現住所
- マイナンバー
これらの情報は、毎月の給与計算台帳や、年末調整時に従業員から提出された各種申告書をもとに集計します。
ステップ2:源泉徴収票を作成する
必要な情報が揃ったら、源泉徴収票を作成します。作成方法には主に以下の3つの方法があります。
- 手書きで作成する:税務署で配布されている用紙や、国税庁のウェブサイトからダウンロードしたPDFに直接手書きで記入する方法です。少人数の事業所であれば対応可能ですが、記入ミスや計算間違いのリスクがあります。
- 給与計算ソフトを利用する:多くの給与計算ソフトには、年末調整の計算から源泉徴収票の発行までを自動で行う機能が搭載されています。毎月の給与データと年末調整の情報を入力すれば、自動で計算・作成されるため、ミスが少なく効率的です。
- 国税庁の「年末調整計算シート」などを利用する:国税庁が提供している無料のツールやExcelシートなどを活用する方法です。手書きよりは計算の手間を省けますが、データの入力は手動で行う必要があります。
ステップ3:受給者へ交付する
作成した源泉徴収票は、定められた期限までに従業員へ交付します。 原則として書面での交付が必要ですが、後述するように一定の要件を満たせば電子データでの交付(電子交付)も認められています。
郵送で交付する場合は、個人情報保護の観点から、親展で送るなどの配慮が求められます。
【ケース別】源泉徴収票発行時の注意点

源泉徴収票の発行は、相手の状況によって対応が少しずつ異なります。ここでは、特に注意が必要なケースについて解説します。
退職した従業員に発行する場合
前述の通り、年の途中で退職した従業員には、退職日から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。 退職者は転職先での年末調整や自身での確定申告に必要となるため、迅速な対応が不可欠です。
本人から発行依頼の連絡がなくても、企業側から最後の給与が確定次第、速やかに発行・送付するよう心がけましょう。
役員に発行する場合
役員に支払う「役員報酬」も給与所得に該当するため、従業員と同様に源泉徴収票の発行が必要です。 使用人兼務役員の場合は、使用人としての給与と役員報酬を合算した金額で作成します。
パート・アルバイトに発行する場合
パートやアルバイトであっても、企業が給与を支払っている以上、源泉徴収票の発行義務があります。 年間の給与支払額が103万円以下で所得税が源泉徴収されていない場合でも、支払総額を記載した源泉徴収票の発行が必要です。
再発行を依頼された場合の対応
従業員が紛失などを理由に再発行を依頼してきた場合、企業はこれに応じる必要 義務があります。 発行履歴を確認し、過去に作成したデータをもとに再度印刷して交付してください。 再発行である旨を明確にするため、書類の余白に「再発行」と記載しておくと親切です。
源泉徴収票の電子交付で業務を効率化しよう

従来は書面での交付が原則でしたが、現在は従業員の承諾を得ることで電子データによる交付が認められています。ペーパーレス化は、企業の業務効率化に大きく貢献します。
電子交付のメリットとは?
源泉徴収票を電子交付することには、企業側・従業員側の双方にメリットがあります。
企業側のメリット
- 用紙代、印刷代、郵送費などのコスト削減
- 封入や郵送作業の手間を削減
- 書類の保管スペースが不要になる
従業員側のメリット
- e-Tax(電子申告)での確定申告がスムーズに行える
- 紛失のリスクが低減する
- いつでもデータを確認できる
電子交付を行うための要件
源泉徴収票を電子交付するためには、事前に以下の要件を満たす必要があります。
- 受給者(従業員)からの承諾:電子交付を行う前に、必ず対象となる従業員一人ひとりから「書面または電子メールなどの電磁的方法により」承諾を得る必要があります。承諾がない従業員には、従来通り書面で交付しなければなりません。
- 真正性の担保:発行する電子データが改ざんされていないことを担保する措置(電子署名など)が必要です。
給与計算システムや年末調整システムには、これらの要件に対応した電子交付機能を持つものも多く、導入を検討する価値は高いと考えられます。
源泉徴収票の発行に関するよくある質問

Q1. 源泉徴収票の発行を拒否することはできますか?
A. できません。 源泉徴収票の交付は所得税法で定められた給与支払者の義務です。正当な理由なく交付しない場合、所得税法違反となり、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があります。
Q2. 作成した源泉徴収票は税務署への提出も必要ですか?
A. 一定の条件下で提出が必要です。 年末調整の対象となった役員・従業員のうち、その年の給与総額が一定額を超える場合(役員は150万円超、一般の従業員は500万円超など)は、「給与支払報告書」とあわせて市区町村へ源泉徴収票を提出する必要があります。なお、給与支払い報告書の提出自体は、全従業員が対象です。
Q.3 発行期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
A. 気づいた時点ですぐに発行・交付してください。 意図的でなく、事務処理の遅れなどで期限を過ぎてしまった場合でも、義務がなくなるわけではありません。従業員が確定申告などで困らないよう、判明次第、速やかに対応することが重要です。
まとめ:正確な源泉徴収票発行で、企業の信頼と業務効率を高めよう

源泉徴収票の発行は、年に一度の重要な経理業務です。従業員の所得を証明し、納税に関わる大切な書類であるため、記載内容や発行のタイミングを正確に把握し、ミスなく進める必要があります。
手書きでの作成から給与計算ソフトの活用、さらには電子交付の導入まで、発行方法はさまざまです。自社の規模や状況に合わせて最適な方法を選択し、効率的かつ正確な発行業務を目指しましょう。
BPaaSや経理BPOならBPIOにお任せください

経理・労務・総務等のバックオフィス業務の代行だけでなく、業務設計やDX支援など幅広く業務を支援します。
業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
RANKING
お役立ち情報
CASE