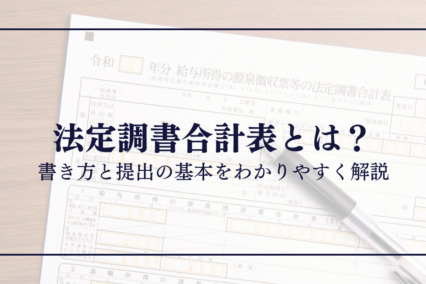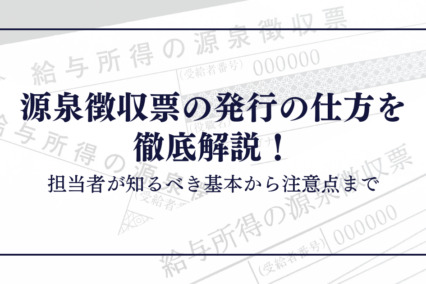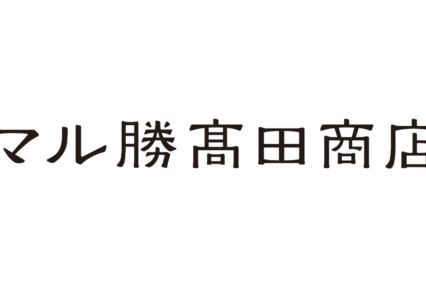従業員に給与を支払う際には、源泉所得税を差し引く必要があります。また、差し引いた源泉所得税は、原則として支払い月の翌月10日までに納付しなければなりません。
この記事では従業員の所得税の支払いについて計算方法を解説し、納付手順なども紹介していきますのでぜひご参考にしてください。
従業員の所得税の計算方法

給与と賞与と退職金の源泉徴収税額の計算方法はそれぞれ異なります。以下に詳細を説明します。
給与
給与に対する源泉徴収税額は国税庁が提供する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表または日額表)」を基に計算します。この表を利用し、社会保険料控除後の給与金額そして扶養親族の人数を元に算出した金額が源泉徴収税額です。
従業員が「甲欄」か「乙欄」のどちらに該当するかを最初に確認します。
甲欄: 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を実施した従業員が該当します。この申告書は入社時や年末調整の前に提出が必要です。
乙欄: 「扶養控除等申告書」を提出していない従業員が該当します。例えば、他の会社から主な給与を受け取っている場合や申告書の未提出が理由です。
扶養控除等申告書を提出していない場合は、税率が高い「乙欄」に基づいて源泉徴収を行うため、給与手取りが大幅に減少する可能性があります。申告書を提出しており、控除後の給与額が月8万8,000円未満であれば、源泉徴収税額が0円となります。
賞与
賞与については、国税庁が定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の利用により計算します。基本的には、扶養親族の人数や社会保険料控除後の給与額を基に算出します。
特定の条件に該当する場合(例: 前月に給与支払いがない、または賞与額が前月給与の10倍を超える)では、賞与の税額算出表を使わず、「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を使用します。
賞与の計算手順は、扶養親族数を基に表の該当箇所を確認し、賞与額に掛けるべき税率を求めた後、その率を賞与額に乗じて税額を算出します。
退職金
退職金に対する源泉徴収税額は、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を使用して計算します。最初に勤続年数に応じた「退職所得控除額」を計算します。
勤続年数20年以下: 40万円 × 勤続年数
勤続年数20年超: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
※勤続年数は切り上げ計算です。
次に、退職金額から控除額を引いた後、その結果を2分の1にした金額が課税退職所得金額となります。この金額を基に速算表を使用し、税率や控除額を参照して所得税額を算出します。計算式は以下の通りです:
(課税退職所得金額 × 税率 - 控除額)× 102.1%
給与、賞与、退職金に対する計算方法を正しく適用することで、適切な源泉徴収税額を求めることができます。
- あわせて読みたい
源泉徴収の流れ
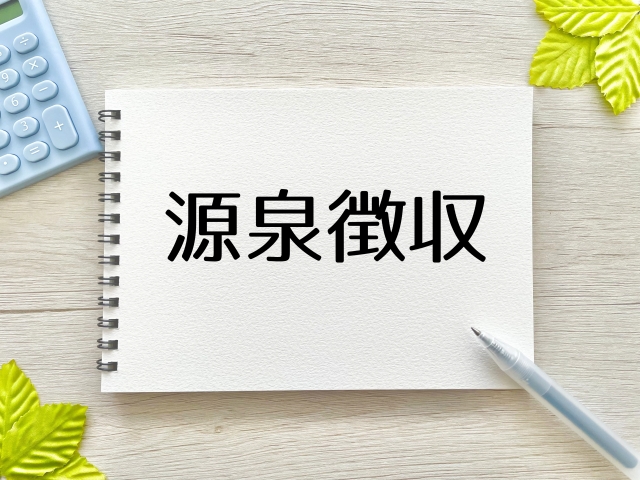
源泉徴収義務者は所得税の源泉徴収を実施し、その税額を国に納める義務を持つ個人事業主や法人のことを指します。これに該当するのは、給与を支払う会社や個人事業主、または源泉徴収が必要な報酬や料金を支払う人々です。給与を支払う場合は会社や個人事業主に限らず、学校なども源泉徴収義務者に該当します。
ただし例外として、従業員がいない場合や常時雇っているのが家事使用人2人以下である場合には、使用人に支払う給与や退職金から源泉徴収を行う必要はありません。また、弁護士報酬や原稿料、講演料を支払っている場合であっても、従業員を雇用していない個人事業主や会社員などは、源泉徴収義務を負いません。
源泉徴収義務者に求められる対応は以下の3点です。
源泉徴収を実施
源泉徴収義務者には、所得税の源泉徴収の責務があります。これは、従業員に支払う給与や、源泉徴収対象となる個人事業主への報酬などを支払う際に、事前に所得税相当額を控除する形で行われます。
源泉徴収税額の納付とその期限
源泉徴収義務者には、源泉徴収した税額の納付の責務があります。差し引いた所得税は、対象となる給与や報酬が支払われた月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。ただし、従業員が常時10人未満の事業所であれば、ケースによって年2回にまとめて納付することが認められます。
源泉徴収票の発行
源泉徴収義務者には、源泉徴収票の交付が義務付けられています。従業員に給与や退職金を支払い、それに対して源泉徴収を行った場合、必ず源泉徴収票を作成し、本人に渡さなければなりません。交付方法は原則として書面ですが、一定の要件を満たせば電子交付も認められます。
一方で、弁護士報酬や原稿料、講演料などに対する源泉徴収については、法律上、源泉徴収票を発行する義務はありません。ただし、受取側が確定申告で必要とすることが多いため、実務上は発行するのが一般的です。
- あわせて読みたい
従業員などは源泉徴収票をいつ受け取れる?

源泉徴収票の受け取り時期については、基本的に年末調整が完了した12月以降となります。
一般の従業員やアルバイト
源泉徴収票は、年末調整が終わった後に発行されるのが通常です。そのため、12月の給与明細と一緒に受け取ることが一般的です。
退職者の場合
退職者の場合は、最後の給与が確定した後、おおむね1か月以内に源泉徴収票が発行されます。ただし、退職時点では受け取れないケースもあり、支払者によっては年末調整の時期にまとめて発行する場合もあります。万が一、年末を過ぎても届かない場合は、早めに問い合わせて発行を依頼しましょう。
再就職した場合
再就職した際には、年末調整は再就職先の企業が行います。この場合、前職の会社から発行された源泉徴収票が必要です。これがないと、再就職先で正しく年末調整を行うことができません。前職の源泉徴収票が届いたら、速やかに再就職先へ提出することを忘れないようにしてください。
源泉徴収税の納付手段

源泉徴収税は、以下のような方法で納付が可能です。現金での窓口納付に加え、クレジットカード、インターネットバンキング、e-Taxを利用したダイレクト納付、コンビニ納付、スマホアプリによる納付も選べます。
現金での納付
金融機関や管轄の税務署窓口で納付書を使用して現金で納付します。この方法では手数料がかからず、領収書が発行されます。ただし、窓口ではクレジットカードは利用できませんので注意が必要です。
クレジットカードでの納付
オンライン上でクレジットカードを使って納付します。国税庁が指定する受託者により納税手続きが進められますが、一度に1,000万円以上の納付はできず、決済手数料が発生します。
ダイレクト納付
e-Taxを利用して、口座振替により納付を行う方法です。利用するためには、e-Taxの利用開始手続きを済ませ、管轄税務署に専用の届出書を提出する必要があります。
インターネットバンキングでの納付
インターネットバンキングやATMを使用して電子的に納付する方法です。この方法を利用するには、事前にe-Taxの利用手続きを完了しておく必要があります。
スマホアプリによる納付
国税庁が指定した受託者のWebサイトを経由して、スマホのPay払い機能を利用して納付します。対応しているPay払いには、「PayPay」「d払い」「au PAY」などがあります。
コンビニでの納付
QRコードや税務署が発行したバーコード付き納付書を使用して、コンビニで支払う方法です。ただし、コンビニではクレジットカードや電子マネーは利用できません。
いずれの方法も選択可能ですので、確実かつ便利な手段を選んで納付を行いましょう。
まとめ

所得税とは、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。この税金は、本人が直接申告して納付する方法と、企業が源泉徴収を行い代わりに納付する方法の2つに分かれます。企業が源泉徴収を行う場合は、源泉所得税を計算し、納付する義務を負います。また、所得税や源泉所得税の計算は非常に複雑です。
煩雑で時間のかかる作業を効率的にこなすためには、会計アウトソーシングの利用を強くお勧めします。専門の知識を持った専門家が最新の税法を踏まえ、適切な処理を行うことで、税務リスクを最小限に抑えることができます。また、業務負担を軽減し、より重要な経営戦略に集中できる環境を整えることが可能になります。会計アウトソーシングは、コストパフォーマンスに優れ、業務の効率化を図りながら、適切な会計実務を実現するための有効な手段と言えます。
経理BPOならBPIOにお任せください
株式会社BPIOが展開する「BPIO」は、バックオフィス業務を3つの軸で改善するBPOサービスです。

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
RANKING
お役立ち情報
CASE