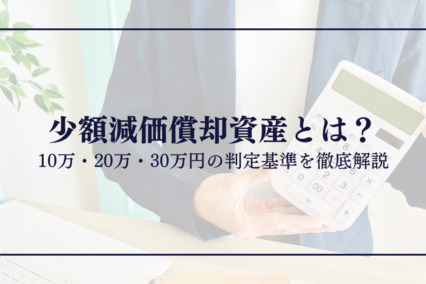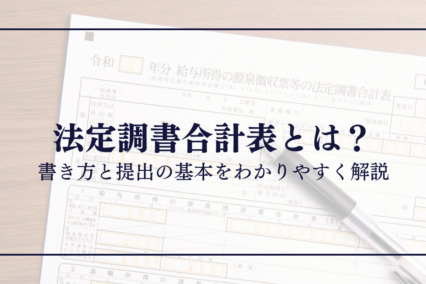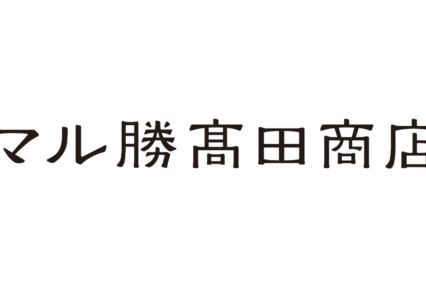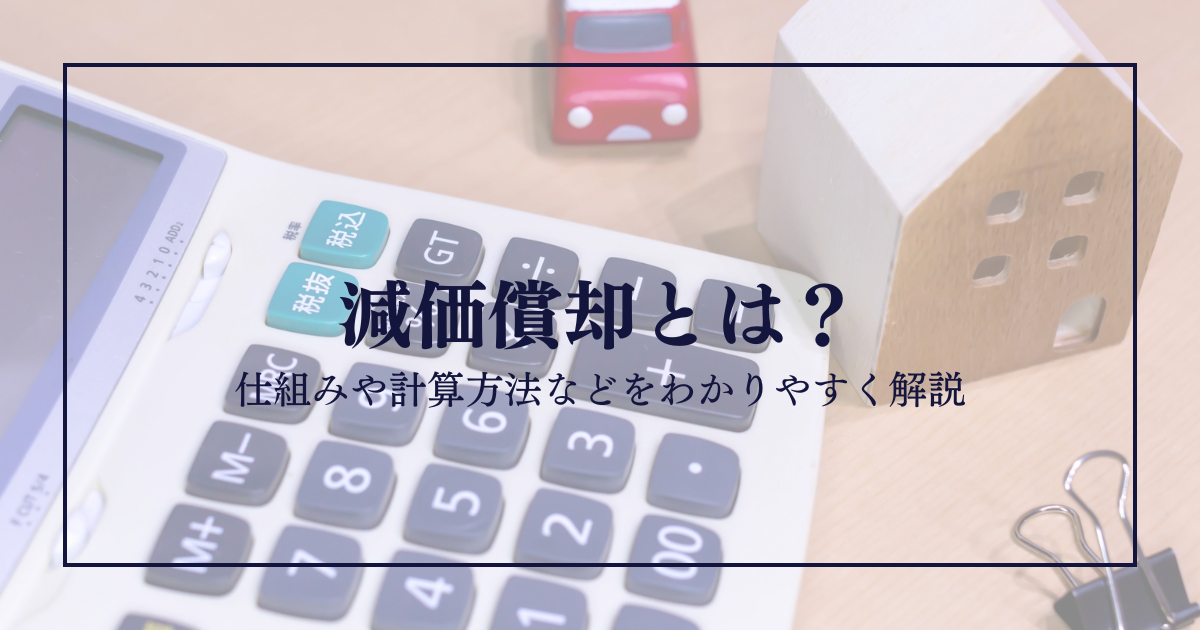
2025.05.13
減価償却とは?仕組みや計算方法などをわかりやすく解説
会社や店舗を運営するために使用される長期的な固定資産には備品や車両などがあり、これらは「有形固定資産」に分類されます。このような資産は決められた期間にわたってその取得原価を分割していく必要があり、そのための会計処理が「減価償却」です。
減価償却の仕組みは十分に理解していないと複雑で、算出方法や仕訳方法にもいくつかのバリエーションがあります。経理担当者としては、基本的な部分からしっかりと把握しておくことが重要です。そこで今回は、減価償却の概念や計算方法など、基礎的な知識について詳しく解説します。
減価償却とは?

減価償却とは、経費を計上する方法の一つです。
減価償却の対象となる資産は「減価償却資産」と呼ばれ、具体的には建物、車両、機械設備、ソフトウェア、特許権などが該当します。
これらの資産は時間の経過とともに価値が徐々に減少するため、購入時に全額を経費として処理するのではなく、減少分を考慮しながら複数年に分けて費用として計上します。
また、減価償却を適用すると、実際の資金の支出と減価償却費の計上時期が一致しません。購入時に一括で支払いを済ませていた場合でも、費用としては複数年にわたり計上されます。
そのため、2年目以降は現金の支出がなくても経費として処理される点に留意しましょう。
減価償却が必要な理由と目的
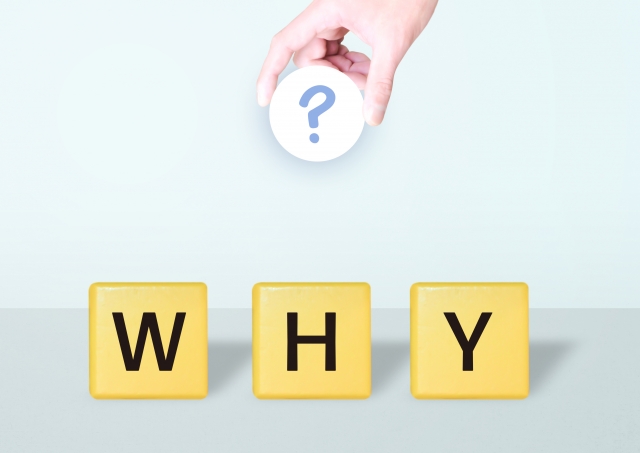
減価償却は、時間が経過することで固定資産の価値が減少する分を費用として計上する方法であり、費用と収益を一致させる観点からも重要な手法です。
これらの資産は長期間にわたって使用され、売上などの収益を生み出し続けます。もしこれらの固定資産を購入時点で一括費用計上してしまうと、その資産の使用による収益と費用が一致せず、正確な期間損益を算出することができません。
企業会計の基本原則は、一定の期間内で発生した費用と収益を対応させることを求めており、これを「費用収益対応の原則」と呼びます。
例えば、商品を仕入れた段階で費用を計上するのではなく、実際にその商品が販売されたタイミングで費用計上を行います。こうすることで、商品の売上と仕入れの費用が直接的に対応します。
一方固定資産に関しては、収益を得る期間を使用期間とみなして減価償却を行い、その結果、収益と費用を適切に対応させ、正確な期間損益を算出することができます。
減価償却を行わない場合の影響
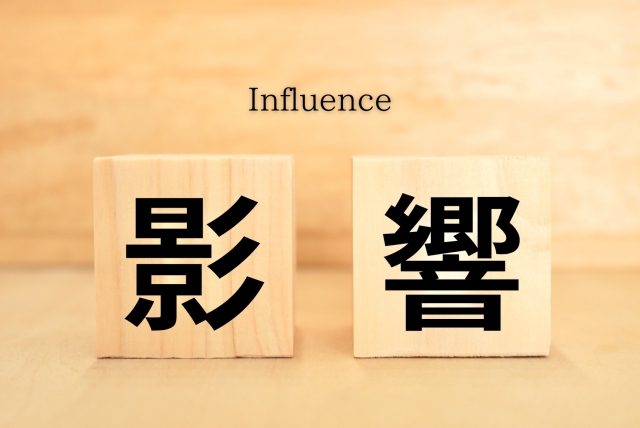
個人事業主の場合
個人事業主は、購入した固定資産について基本的に耐用年数を基に減価償却処理を行う必要があります。これを行わないと、経費として認められず、結果的に課税所得が多くなり、税負担が増える可能性があります。
法人の場合
法人では、会計で計上した減価償却費のうち、償却限度額に達する分は法人税の計算において損金に加算されます。
非上場企業などでは減価償却費の計上が義務ではありませんが、これを行わない場合、損金に算入されず、法人税の計算で高額な税金を支払うことになるため、税負担が大きくなります。
- あわせて読みたい
減価償却の計算方法

定率法
法人の場合、一般的に定率法を用いて会計処理を行うことが求められます。
定率法の特徴は、初年度に最も高い償却費が計上され、その後は償却費が年々減少していくことです。定額法よりも若干複雑ではありますが、資産を早く償却できるため、他の事業への投資がしやすくなり、初年度に大きな節税効果を得られるといったメリットがあります。
定額法
定額法は、定率法と異なりシンプルな方法であり、初年度から最終年度まで償却費が一定である点が特徴です。個人事業主の場合は、原則として定額法を使用して会計処理を行います。
減価償却のポイントと注意点

減価償却処理を行う際には、適用条件を正確に判断することが重要です。特に注目すべき点です。
取得価額が10万円以上かどうか
減価償却が必要かどうかは、取得価額に基づいて判断します。
例えば、1台8万円のパソコンの場合10万円未満となり、減価償却処理は不要です。この場合、消耗品費として処理します。
しかし、店舗に5か所の窓があり、1セット5万円のカーテンを5セット購入した場合は、セットとして考え、減価償却が可能です。
税込経理か税抜経理かの判断
減価償却資産の取得価額を判定する際、経理方法によって基準が異なります。税抜経理方式では「税抜価格」、税込経理方式では「税込価格」を基に判断します。
例えば、ある中小企業が本体価格28万円のパソコンを購入した場合、消費税10%で2.8万円の追加費用が発生します。
税抜経理の場合、取得価額は28万円とし、少額減価償却資産として経費処理が可能です。
税込経理の場合、取得価額は約31万円となり、30万円を超えるため少額減価償却資産としては扱えません。通常の固定資産として処理されます。
このように、経理方法によって取得価額の基準が変わることに留意する必要があります。
資産ごとに耐用年数が異なる
資産の種類によって耐用年数が異なることには注意が必要です。これにより、各資産の耐用年数を個別に管理する必要が生じます。
そのため、決算時には残りの耐用年数を確認することが重要です。予め、デジタル庁が提供する「E-GOV 法令検索」などで関連する耐用年数を調べておくと良いでしょう。また、新品と中古品では耐用年数が異なり、中古品の場合は使用可能期間が短いため、償却年数もその分短くなります。
まとめ

ここまで減価償却について説明してきました。減価償却費の計上に関しては会計アウトソーシングの利用をおすすめします。その理由は多岐にわたります。
まず、減価償却は複雑な計算が必要なため、誤った処理が税務上の問題を引き起こす可能性があります。会計アウトソーシングを活用することで、専門的な知識を持った専門家が最新の税制や会計基準に基づいて正確に減価償却を計算・処理し、税務リスクを最小限に抑えることができます。
また、会計業務の一部をアウトソーシングすることで、社内のリソースを本業に集中させることができ、業務効率が向上します。特に、減価償却の計上は定期的に行う必要があり、アウトソーシングによってこれを一貫して管理できるため、業務の負担が大幅に軽減されます。
さらに、アウトソーシングを利用すれば、最新の会計ソフトウェアやシステムを活用した精度の高い処理が可能となり、会計担当者の負担を減らすだけでなく、迅速かつ正確な対応が求められる税務調査にも対応しやすくなります。
加えて、会計アウトソーシングを利用することで、コストの予測がしやすくなる点も大きなメリットです。内製での経理業務にかかるコストや時間を考慮すると、アウトソーシングによる費用はコストパフォーマンスが良い場合が多いです。税務や会計処理の専門家に任せることで、経営資源を効率的に活用し、業務の精度向上とコスト削減を同時に実現することができます。
減価償却費の計上を正確かつ効率的に行いたいのであれば、会計アウトソーシングの活用は非常に有益であり、企業の経営効率化やリスク軽減に大いに貢献することでしょう。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
RANKING
お役立ち情報
CASE