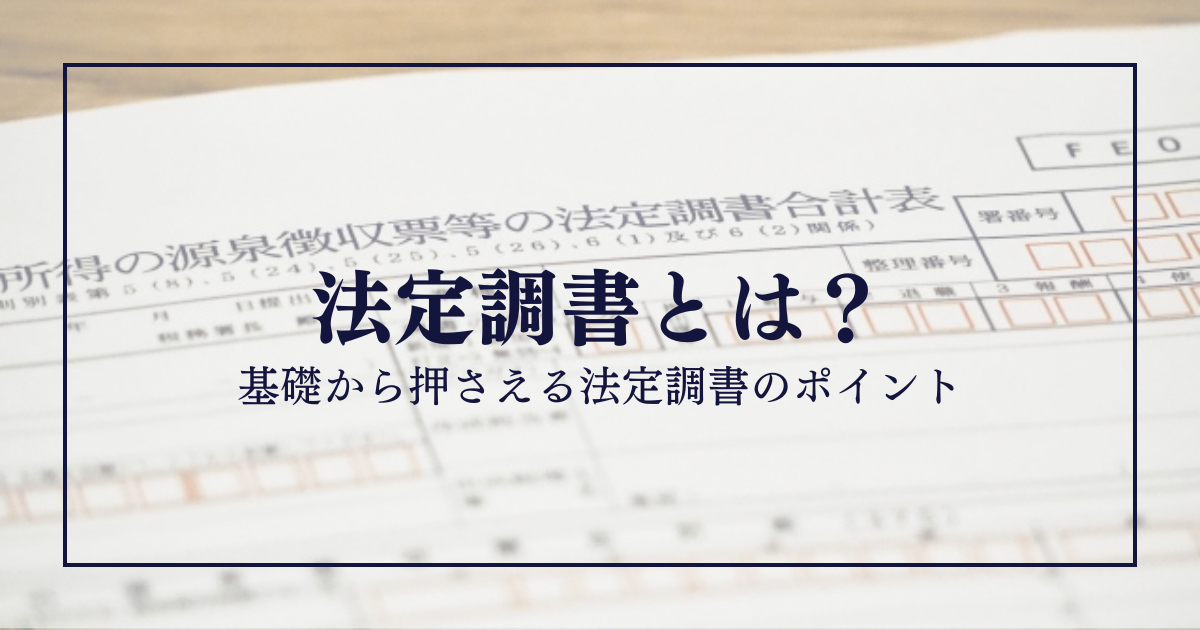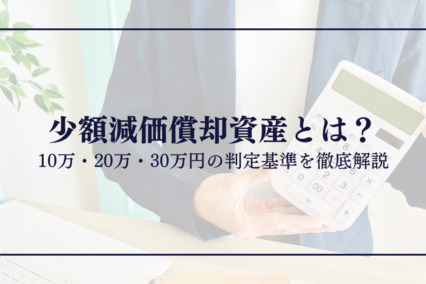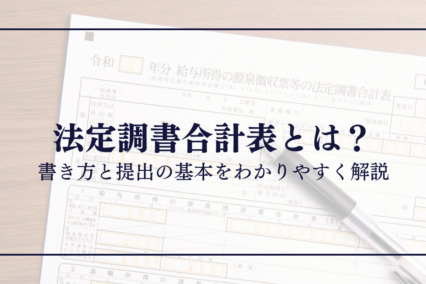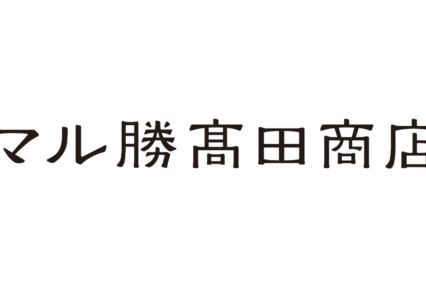法定調書にはさまざまな種類があり、代表的なものとしては源泉徴収票や支払調書などがあります。特に年末調整時には複数の法定調書を作成することが一般的であり、法定調書が何であるか、どのように作成すべきかを正確に理解しておくことが重要です。
そこでこの記事では、事業者がよく作成する代表的な法定調書の種類やその内容、税務署への提出方法について説明し、法定調書作成時の注意点にも触れます。
法定調書とは?
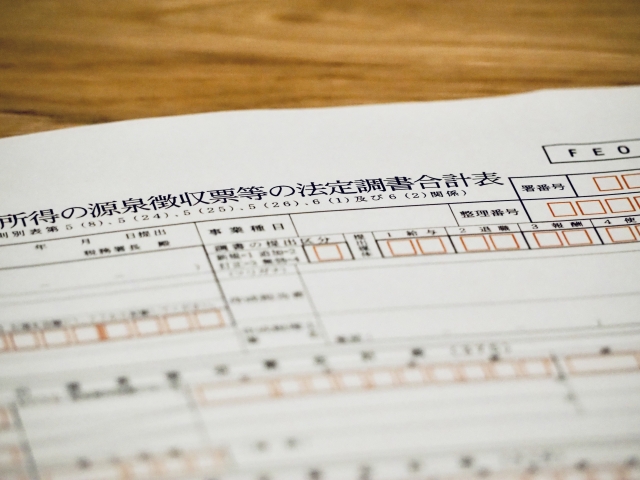
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税を確保するための国外送金等に関する調書提出義務に関する法律」に基づき、納税者が税務署に提出することが義務付けられている書類を指します。これには多数の種類があり、現在では約60種類の法定調書が存在しています。
法定調書の活用目的とは?

例えば、A社がBさんに200万円の報酬を支払った場合、A社はその支払いに関する支払調書を税務署に提出します。その後、Bさんが200万円の事業所得を申告して確定申告を行えば、支払調書に記載された金額とBさんの申告内容は一致し、適切に申告されたことが確認できます。
一方、Bさんが確定申告をしなかったり、200万円より少ない金額で申告した場合、支払調書の内容と一致しないため、どちらかに誤りがあることが明らかになります。その結果、税務署は「お尋ね」の通知を送るなどの対応をすることになると想定されます。
つまり、支払調書は脱税を防止する仕組みとなっており、正しい申告を促す役割を果たしています。そのためにも確定申告は正確に行いましょう。
法定調書の種類と提出が必要な人
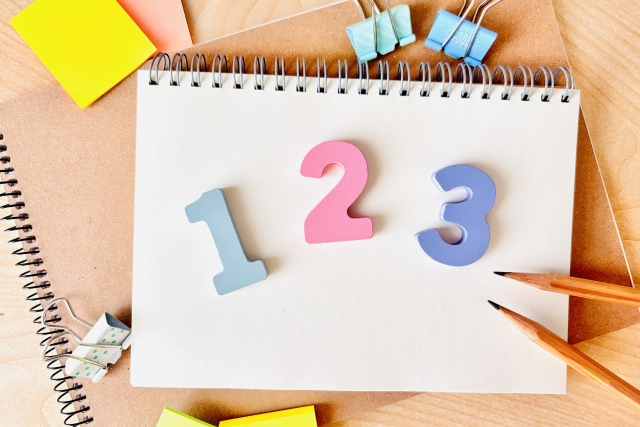
法定調書の提出義務がある者は、その種類によって異なります。
給与所得の源泉徴収票に関しては、給与や賞与、またはこれらに類似する報酬を従業員に支払う者が対象となります。
退職所得の源泉徴収票については、法人役員に退職手当を支払う者や一時恩給などを支給する者が該当します。ただし、死亡退職の場合は退職手当金等受給者別支払調書を提出することになるため、退職所得の源泉徴収票や特別徴収票は提出する必要はありません。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に関しては、外交員報酬や税理士報酬などを支払う者が該当します。所得税法に基づく報酬の確認が求められます。
不動産使用料等の支払調書に関しては、不動産の賃借料や関連する権利金、船舶(総トン数20トン以上)や航空機の賃借料などを支払う法人や不動産業者として活動する個人が該当します。
給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
給与所得の源泉徴収票は、通常、年末調整後に会社が社員やアルバイトに配布する書類であり、税務署への提出は求められません。しかし、以下の条件を満たす場合、年末調整を行っている会社でも給与所得の源泉徴収票を法定調書として税務署に提出する義務があります。
- 法人の役員で、その年の給与等が150万円を超える場合
- 弁護士、司法書士、税理士などで、その年の給与等が250万円を超える場合
- 上記以外で、その年の給与等が500万円を超える場合
また、社員やアルバイトが住む市町村に提出する「給与支払報告書」は、上記の条件に関係なく、必ず提出しなければなりません。
給与支払報告書は、源泉徴収票と同じく、その年に支払われた給与額などを記載した書類です。ただし、従業員本人への交付はなく、1月1日時点で従業員が居住する市区町村に提出します。この報告書に記載された給与額を基に、翌年度の住民税が決まるため、非常に重要な書類です。年末調整が終了した後、各市区町村が指定する期限(原則として1月末日)までに、全従業員分の給与支払報告書を作成し、必ず提出するようにしましょう。
また、源泉徴収票と給与支払報告書の違いについて説明します。
源泉徴収票は、従業員や税務署への提出のほか、市区町村にも2部提出しなければなりません。この市区町村への提出分が「給与支払報告書」と呼ばれています。源泉徴収票は納付した所得税を証明するために税務署に提出し、給与支払報告書は住民税の計算を行うために市区町村に提出する書類です。
| 書類名 | 提出先 | 税金の種類 | 電子申告サイト |
| 源泉徴収票 | 税務署 | 所得税 | e-Tax(国税電子申告・納税システム) |
| 給与支払報告書 | 市区町村 | 住民税 | eLTAX(地方税ポータルシステム) |
給与支払報告書と源泉徴収票はフォーマットがほぼ同じですが、給与支払報告書には「普通徴収」と「特別徴収」を選択する項目があり、住民税は給与支払報告書に基づいて計算されます。
報酬・料金・契約金・賞金の支払調書
報酬、料金、契約金、および賞金の支払調書は、所得税法や相続税法などの関連法規に基づき、事業者が税務署に提出しなければならない「法定調書」の一つです。原則として、取引先に対して報酬などを支払った年の翌年1月31日までに、税務署に提出する必要があります。
この支払調書は、一般的に事業者がフリーランスなどの取引先に対して報酬や契約金を支払った場合に作成されるものです。支払調書は支払先への交付義務はありません。ただ慣習としてサービスで発行されることはあることは珍しくありません。
しばしば「支払調書」といえば、報酬、料金、契約金、および賞金の支払調書を指すことが多いです。
もし、報酬、料金、契約金、および賞金の支払調書を含む法定調書を提出しなかった場合、事業者は最大で1年の懲役刑または50万円以下の罰金を課せられる可能性があるため、注意が必要です。
支払調書の受取人は売上を適切に管理して確定申告する必要があります。
提出期限について

法定調書は原則としてその計算対象となる翌年の1月31日までに提出する必要があります。従業員に源泉徴収票を渡すだけでは年末調整の手続きは完了したことにはならないため、提出期限を守り、期日管理をしっかりと行うことが重要です。
源泉徴収票の保管ルール

給与支払者(提出義務者)は、源泉徴収票を作成する前に「源泉徴収簿」を作成します。この源泉徴収簿は帳簿に該当するため、7年間保存する義務があります。源泉徴収簿に源泉徴収票に関連する情報を記録しておけば、従業員から源泉徴収票の再発行を求められた際にも対応可能です。
一方、源泉徴収票自体は、本人、市区町村役場、税務署にそれぞれ提出されるため、紙で保存する必要はありません。つまり、提出した源泉徴収票の控えを保管する義務はないということです。
さらに、所得税法施行規則に基づき、従業員から提出された源泉徴収に関連する申告書類も7年間の保存義務があります。
法定調書提出期限遅れを防ぐための対策

法定調書の提出期限は厳守しなければなりません。期限内に提出できた場合でも、内容に不備があると再提出を求められることになり、その結果として提出期限を過ぎてしまう恐れがあります。また、虚偽の内容が含まれていた場合は、提出しなかった場合と同様に罰則が科されることがあるため、注意が必要です。以下の点を事前に確認し、不備や虚偽がないように準備を進めましょう。
マイナンバーを事前に収集する
2016年から、法定調書にはマイナンバーの記載が必須となっています。従業員や取引先からマイナンバーを取得していないと、書類作成が遅れる原因になります。もし提出を拒否された場合は、マイナンバー提供が法的に義務付けられていることを伝え、早めに提出してもらうよう依頼しましょう。マイナンバーは個人情報に関わるため、取り扱いには十分に注意が必要です。提供をお願いする際には、マイナンバー取り扱いに関する注意点を説明することも大切です。
電子申告の義務化
2021年から源泉徴収票の提出する枚数が100枚以上になる場合、電子申告が義務付けられました。この場合、e-Taxや電子媒体を使って法定調書を提出することになります。e-Taxは法定調書の提出だけでなく、納税関連書類の作成・送信にも使用されます。操作は複雑ではないので、早めにシステムを導入し、使い方に慣れておきましょう。e-Taxでの提出は24時間可能で、税務署に出向く必要がありませんが、提出直前に不備があると期限を過ぎてしまうことがあるため、余裕を持って準備することが重要です。
- あわせて読みたい
まとめ

以上法定調書について解説しました。
法定調書の作成に関してご不明点がある場合、会計アウトソーシングの利用をおすすめします。専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルが会計業務をサポートします。
これによりミスを防ぎ、安心して業務を進めることができるでしょう。さらに、煩雑な手続きを専門家に任せることで、貴社の負担を軽減し、コア業務に集中できるようになります。
今回の記事が皆様の法定調書に関する理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
経理BPOならBPIOにお任せください

業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
RANKING
お役立ち情報
CASE