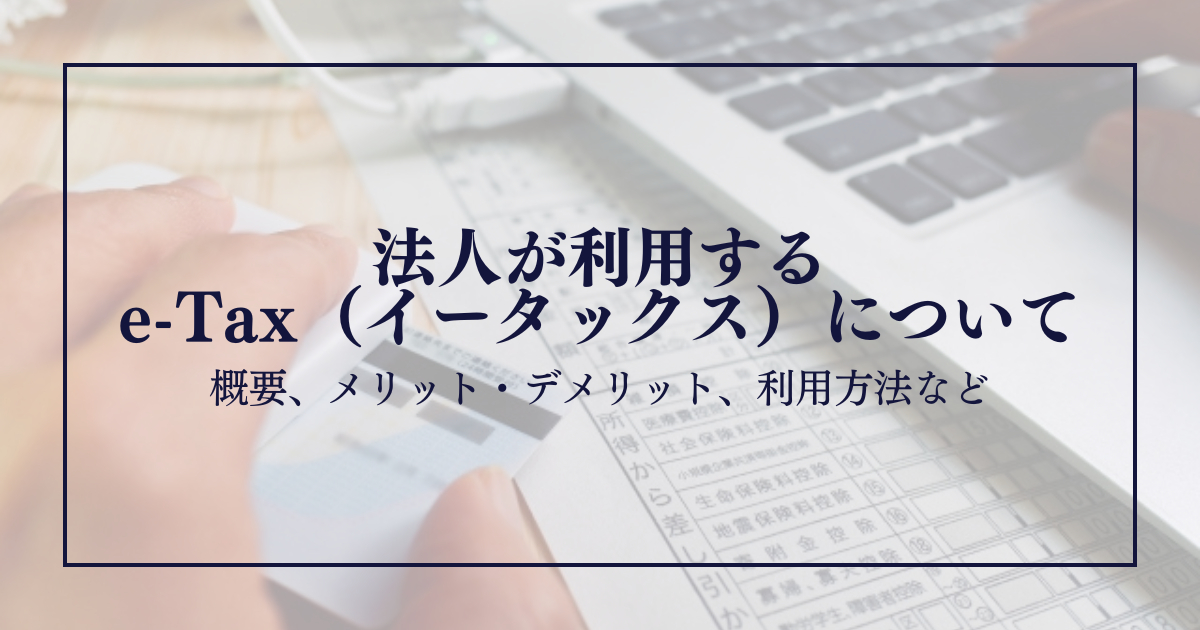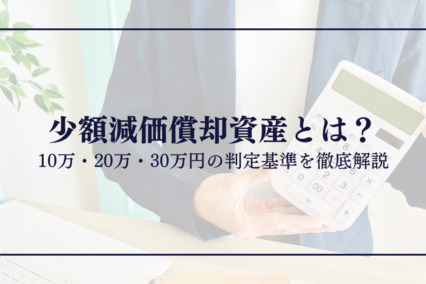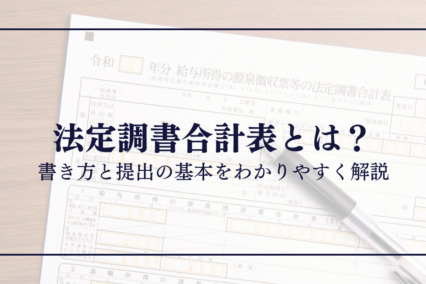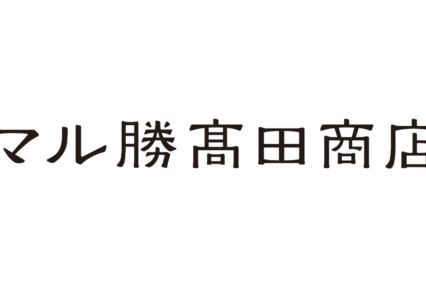法人税申告の際に「もう少し手続きが簡単になればいいのに…」と感じたことがある方も少なくないのではないでしょうか。
そんなときに活用したいのが「e-Tax」です。e-Taxを利用すれば、申告手続きだけでなく、納税までもスムーズに進めることが可能です。
そこで本記事では、e-Taxの概要から利点・注意点、そして導入の流れについて詳しくご紹介します。
e-Taxってどんなシステム?

e-Taxは、2004年から全国で導入された国税庁が提供する電子申告・納税のためのオンラインシステムです。これを活用することで、各種手続きがスムーズに行えるようになります。
納税は、ダイレクト納付に加えてインターネットバンキング等でも対応可能です。さらに、e-Tax対応の会計ソフトを使えば、申告から納税までをPCなどで完結することもできます。
e-Taxには、用途や使用環境に応じた複数のソフトウェアが用意されています。たとえば、パソコンから利用する場合には、インストール型の「e-Taxソフト」があり、その他にも目的に応じて選べるツールがいくつか提供されています。
なおe-Taxと似た言葉としてeLTAX(エルタックス)というものがあります。
国が提供する電子申告システム「e-Tax」では、法人税・消費税・源泉所得税などの各種申告および納税手続きが可能です。
一方、地方税共同機構が運営する「eLTAX(エルタックス)」を利用すれば、地方法人税や事業税、住民税(特別徴収分)など、地方税に関する申告・納付をまとめて行うことができます。
申告・申請・届出について
それぞれの言葉の意味を簡単に説明すると、次のようになります。
- 申告:主に法人税や消費税など、税金の金額を自分で計算して税務署に届け出る手続きのことです。
- 申請:「これを適用してもいいですか?」と税務署の許可を得る必要がある手続きです。たとえば「青色申告の承認申請書」は、申請が認められた場合にのみ利用できる制度です。
- 届出:「こういうことを行いました」と税務署に報告する手続きで、承認は不要です。
e-Taxを使うメリット・デメリット

e-Taxのメリット
税務署にいかなくても申告手続きが完結できる
インターネット環境さえあれば、職場からe-Taxにアクセスして、そのまま確定申告ができます。e-Taxを使えば法人税の納付もオンラインで済ませることが可能です。
印刷や税務署への持参・郵送などの手間がなくなり、移動時間や郵送費を削減できるのも大きな利点です。
申告内容の修正も簡単に対応できる
税務申告後に内容のミスに気付いた場合でも、申告期限内ならe-Taxなら再度申告データを送信するだけで修正が完了します。修正報告の手間も不要で、送信した最新のデータが自動的に上書きされます。
当然ですが申告期限は守る必要がありますのでその点は注意が必要です。
還付金の受け取りがスピーディー
e-Taxで申告した場合、書面で申告したときよりも還付金の振り込みが早くなることがあります。
特に2006年11月以降法人税・消費税の還付申告をe-Tax経由で行うと、一般的に申告後約3週間ほどで還付されるケースが多いです。
e-Taxのデメリット
e-Taxは一度慣れてしまえば非常に便利なツールですが、利用者によっては以下のようなデメリットを感じることがあります。
事前の準備が求められる
e-Taxを利用するためにはe-Taxにログインするための「利用者識別番号」と「暗証番号」も事前に取得しておく必要があります。これらは、オンラインもしくは税務署でのe-Tax開始届出の手続きを通じて取得可能です。
操作が難しく感じられる場合がある
e-Taxを初めて利用する方にとっては、操作方法や各種設定が煩雑に思えることがあります。たとえば、電子証明書の有効化、カードリーダーの接続・設定、あるいはパソコンの動作環境の整備など、初心者にはハードルが高く感じられることもあるでしょう。
さらに、利用者識別番号の発行や、複数の暗証番号の管理など、慣れていない人には少々面倒に感じられるかもしれません。
対応環境に制限がある
e-Taxを使用するには、あらかじめ対応しているOSやウェブブラウザである必要があります。古いPC環境やブラウザでは正常に動作しないことがあり、場合によっては新しい機器の導入や、最新バージョンへのアップデートが求められることもあります。
e-Taxの導入ステップ

この章ではe-Taxの導入方法について解説します。
電子証明書の取得
e-Taxの利用には、あらかじめ認定された認証局から発行される電子証明書が必要です。この証明書は、電子署名法に基づく特定認証業務として正式に認可を受けた機関が提供するものに限られます。
e-Taxでは以下の2点を確認するために、電子証明書および電子署名を使用します。
- そのデータの作成者が誰であるかデータが送信時から変更されていないか(改ざんの有無)
電子証明書は、インターネット上の手続きにおいて重要なアイテムであり、電子署名はデータの信頼性を裏付けるために欠かせません。
なお、各認証局によって利用料や有効期間は異なりますので、詳細はそれぞれの機関へ確認してください。
また、「所得税徴収高計算書」「納税証明書の交付請求」など一部の機能を使う場合には、電子証明書は不要です。
利用者識別番号を取得
利用者識別番号は法人がe-Taxを利用する際に必要なIDであり、この番号がないとe-Taxソフトにログインすることができません。
利用者識別番号の取得方法は2つあります。
1つ目は、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を使って、開始届を提出する方法です。このコーナー内で「開始届出(法人用)新規」を開き、「法人番号」・「法人名称」・「納税地情報」・「提出先税務署」を入力します。
もし「法人番号」がわからない場合は、「国税庁 法人番号公表サイト」から確認できます。次に、「法人の代表者情報」「本店情報」などを入力し、オンラインまたは書面で提出すると手続きが完了します。
2つ目は、「法人設立ワンストップサービス」を用いる方法です。デジタル庁のポータルサイトを通じて、法人設立に関する手続きや書類の申請を一括で行うことができます。このサービスを利用するには、法人の代表者のマイナンバーカードを利用します。
e-Taxソフトのダウンロードとインストール
e-Taxを使用して手続きを行うために、最終的に法人のパソコンにe-Taxソフトをダウンロードしてインストールします。ダウンロードは、e-Taxの公式サイトにある「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」から行うことができます。
このコーナーでは、ダウンロードを行う前に必要なパソコンの設定(「利用環境の確認」や「信頼済みサイトおよびポップアップブロックの許可設定」など)についても案内されていますので、ダウンロード前にそれらの確認をしておくことをおすすめします。
参考URL:https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm
- あわせて読みたい
まとめ

今回はe-Taxについて解説しました。適切な税務申告に利用されるe-Taxですが、税務申告の元となる決算書の作成などの会計業務については会計アウトソーシングを利用するのがオススメです。
決算書は企業の財務状況を示す重要な資料であり、その正確性が企業の信頼性に大きく影響します。誤った決算書の作成は、企業の信用に関わる問題を引き起こす可能性があります。
特に経理業務が煩雑で、細かな確認作業が必要となる決算書作成は、経験と知識を要する作業です。
そこで、会計アウトソーシングを利用することで、専門のプロフェッショナルによる正確で迅速な決算書作成が可能になります。アウトソーシングを導入することで、専門知識の活用、業務負担の軽減、コストパフォーマンスの向上などが期待できます。
会計アウトソーシングを活用することで、企業は正確かつ効率的な決算書作成を実現し、財務の透明性を高めることができます。
企業経営における安定性を確保するためにも、信頼できる会計パートナーと協力することは非常に重要です。企業は本業に専念でき、長期的な成長を促進することができます。
経理BPOならBPIOにお任せください

経理・労務・総務等のバックオフィス業務の代行だけでなく、業務設計やDX支援など幅広く業務を支援します。
業務を効率化し、コア業務に集中できる環境をご提供し、関わる全ての会社に最適なバックオフィス環境を実現するBPOサービスです。
ご興味がありましたら、ぜひ一度下記のボタンよりサービス概要のご確認や、お気軽にお問い合わせくださいませ。
カテゴリー
- 仕入税額控除
- 法定福利費
- マイグレーション
- タイムスタンプ
- 経理代行
- 出張費
- 財務分析
- 電子領収書
- 経理業務委託
- 保険料
- 法人税
- 領収書
- 経理業務
- 固定資産
- 法定調書
- 経理お役立ち情報
- 電子帳簿保存法
- ペーパーレス化
- 定款
- コスト削減
- 税務調査
- 役員報酬
- e-Tax
- IPO準備
- 経理BPO
- リコンサイル
- eLTAX
- 効率化
- ERP
- 所得税
- 現金出納帳
- 退職者
- バックオフィス業務
- 源泉徴収
- 前受金
- 法定調書合計表
- ひとり企業
- 源泉徴収票
- 勘定科目
- 支払予定表
- 年末調整
- 人件費削減
- 決算書
- 小口現金
- 償却資産税
- 免税事業者
- 経理コンサルティング
- 貸借対照表
- 証憑
- 減価償却
- 経理情報
- 旅費交通費
- 損益計算書
- 決算
- 少額減価償却資産
- インボイス制度
- 定額減税
- キャッシュフロー計算書
- 売上債権
- デジタルインボイス
- 経理アウトソーシング
- 交際費
- 会計システム
- 売掛金
- 未払金
- BPaaS
- 福利厚生費
- 会議費
- 経理
- 扶養控除
RANKING
お役立ち情報
CASE